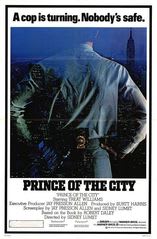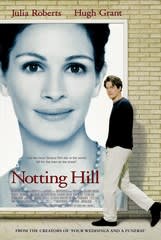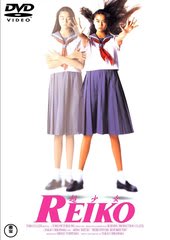(原題:歸来 Coming Home)張藝謀監督作品とも思えない、腑抜けた出来だ。もちろん、これまでの彼のフィルモグラフィが全て良作であったわけではなく、凡作・駄作もいくつかある。しかし本作は文化大革命という歴史的イベントを題材に、過去何度かコンビを組んで成果を上げてきたコン・リーを主演に据えているにもかかわらずこの程度のレベルに終わっているのは、この作家としての衰えを感じさせて寂しい気持ちになる。
70年代、それまで長い間当局側に拘束され遠隔地に送られていた男イェンシーが収容所から逃亡。妻と娘の住む町にたどり着くが、官憲に捕まってしまう。妻のワンイーはそんな彼を駅で見送るしかなかった。それから数年経った77年、文化大革命が終結しイェンシーは20年ぶりに解放され、故郷に戻って家族と再会する。ところが妻は心労で記憶障害になっており、夫の顔も覚えていない。イェンシーは他人として向かいの家に住み、成長した娘タンタンの助けを借りながら、何とか妻の記憶を取り戻そうと奮闘する。
イェンシーは冒頭の逃亡劇の時点で十数年間も家に帰っていないが、その際はワンイーは夫をしっかりと認識していた。それからわずか数年しか経たないのに、これほどまで(何の伏線も暗示もなく)急激にメンタル障害が悪化しているというのは、乱暴な作劇と言わざるを得ない。しかも、部屋の中には物の名前や役割などを指示する張り紙が多くあって、ワンイーが認知症患者である様子が示されるが、こんな症状を抱える者に一人暮らしをさせている設定には無理がある。
またイェンシーは必死になって妻に自分を思い出させるように苦労するのだが、認知症を患う者に対してピンポイント的に“夫の記憶”だけを取り戻させようとするのは、筋違いなのではないか。病状を心因性忘却症に限定して、罹患したプロセスも明かすべきだった。そのあたりを押さえておかないから、イェンシーの頑張りは空振りを続けて観る側はカタルシスを得られない結果になる。
最大限に穿った見方をすれば、ワンイーの忘却症は文化大革命の象徴なのかもしれない。つまり、多くの中国人にとって“忘れてしまいたいこと”であるという解釈だ。しかし、たとえそうだとしても本作の御膳立ては粗雑に過ぎる。
張監督の今回の仕事はメリハリが感じられず、漫然と話が進むだけで、気勢の上がらないラストに行きつくのみ。コン・リーはもちろん夫役のチェン・ダオミンも熱演なのだが、それが空回りしている状態だ。唯一興味を覚えたのは、娘タンタンを演じるチャン・ホエウェンの扱いだ。バレエのシーン等で溌剌とした存在感を発揮するが、明らかに同じ張監督の「初恋のきた道」のチャン・ツィイーや「至福のとき」のドン・ジエと同じ位置付けで、つまりは“これからプッシュしたい”という意図が透けて見える(爆)。新進女優を取り立てることに関しては、相変わらず積極的のようだ。