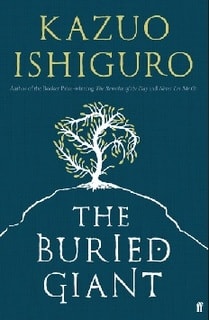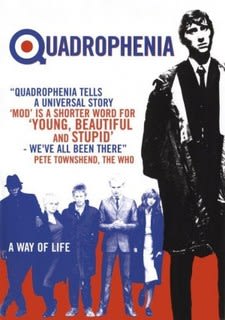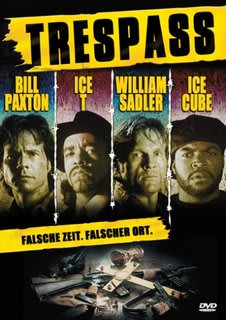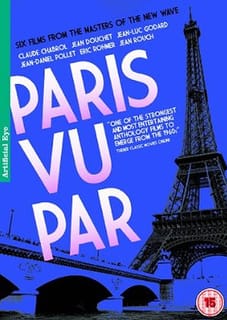随分と乱暴な筋書きである。展開は行き当たりばったりで、まさに御都合主義が横溢している。ならば面白くないのかというと、そうでもないのだ。それはキャラクター設定の妙に尽きる。強烈な印象を受ける人物を画面の真ん中に据えれば、映画はサマになってしまう。SABU監督としても「ポストマン・ブルース」(97年)以来の快作と言えるのではないか。
台湾の殺し屋ロンは、ナイフを使った確かな仕事ぶりで“その筋”からの信望も厚い。ある時、彼は東京・六本木にいるヤクザを殺す仕事を請け負う。しかし、失敗して逆にピンチに陥ってしまう。相手のスキを突いて何とか逃げ出し、北関東のとある田舎町へと流れてくるが、日本語が分からない彼は途方に暮れる。そこで偶然知り合ったのが、心を閉ざした少年ジュンとその母親で台湾人のリリーだった。やがて地元の人々との交流も生まれ、ロンは得意の料理の腕を活かして牛肉麺の屋台を始める。それが成功し、ジュンとリリーとの間にはまるで家族のような関係性を持つに至るが、そこにヤクザの手が迫ってくる。
主人公が“料理が得意な殺し屋”という設定は、やや無理筋ながらまだ許せる。だが、絶体絶命のロンが逃亡に成功する理由が、敵のボスに復讐しようとしている男が“偶然に”割り込んでくるというのは、都合が良すぎるだろう。さらに逃亡先で“偶然に”台湾人の親子に出会い、住み家として適当な廃屋が“偶然に”近くにある。さらに、ジュンとリリーを苦しめる地元の暴力団が、くだんの六本木のヤクザと“偶然に”繋がっているのだから呆れる。終盤の処理に至っては、あまりにも乱雑だ。
しかし、主要登場人物の個性は際立っていて、かなり説得力がある。チャン・チェン扮するロンは無愛想で無口だが、内に秘めた激しい感情を鮮明に表現していて圧巻。活劇場面での乾坤一擲のナイフさばきも冴える。そんな彼が逃げ延びた町の者達との交流を通して、徐々に人間らしさを取り戻していく筋書きは予想通りながら、そのプロセスは丁寧に描かれていて説得力がある。
薄幸を絵に描いたようなリリーの造型も良い。心の拠り所を見つけたと思ったら、そのたびに理不尽な境遇に追い込まれ、さらなる転落を強いられるヒロインを台湾女優イレブン・ヤオは懸命に演じる。諏訪太朗や大草理乙子、歌川椎子といった舞台畑の芸達者が顔を揃えているのも嬉しい。子役のバイ・ルンインや敵役の岸建太朗もイイ味を出している。
地方都市の沈んだ雰囲気と、ギラギラした六本木や台北との対比は悪くない(古屋幸一のカメラは要チェック)。第67回のベルリン国際映画祭に出品されているが、この程度では正直受賞は無理だと思う(事実、無冠だった)。だが、捨てがたい魅力はある。観て損は無い映画だ。