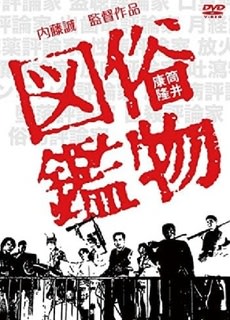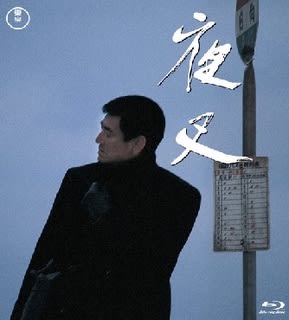84年作品。前々年の82年は日活の創立70周年であり、それを記念して作った名場面集映画だ。なお、当時の同社の名称は平仮名の“にっかつ”であり、ロマンポルノを主に手掛けていたのだが、本作で取り上げられているのは60年代までのいわゆる“日活アクション映画”の数々である。本作の構成は、年老いた殺し屋がかつて共演したライバルを捜し求めて彷徨するというスタイルを取っている。
面白いのは、この映画の公開当時の観客に“日活アクション映画”の概要を説明しようという意図がまったく感じられないこと。さまざまな映画から引用された断片的なショットを、脈絡も無く積み上げていくだけなのだ。同じ頃に作られた「生きてはみたけれど 小津安二郎伝」(83年)は小津映画の何たるかを体系的に示そうとしていたが、それとは対照的なシャシンである。
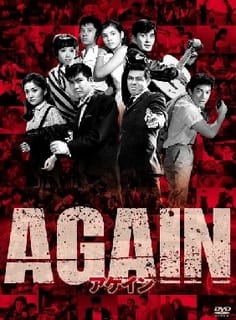
この手法は一見むちゃくちゃだが、別にこれは悪くないと思える。なぜなら、この“日活アクション映画”自体が無国籍風で混沌としたスタイルを取っていたからだ。もちろん私は“日活アクション映画”をリアルタイムで観た世代には属していない(笑)。しかしながら、この映画を観ていると、全盛期の日活映画の持っていた雰囲気や魅力が何となく伝わってくるから不思議なものである。もっともそれは、当時の“日活アクション映画”が多くの若手スターを輩出し、ブームが去った後も彼らが活躍する姿を見ているからなのかもしれない。
引用している作品は「狂った果実」「赤いハンカチ」「帰らざる波止場」「ギターを持った渡り鳥」「泥だらけの純情」「紅の流れ星」など全38本。その中でも「嵐を呼ぶ男」の有名なドラム合戦のシーンを、石原裕次郎主演の井上梅次監督版(57年)と、渡哲也主演の舛田利男監督版(66年)を交互にシンクロさせて編集する場面は本作のハイライトであろう。
監督は作家の矢作俊彦で、構成や脚本も担当している。映画畑とはあまり関係ない人材によるシャシンなので、いろいろと思い切った施策を講じることが出来たのだと思われる。ただし、このネタで上映時間が1時間42分というのは少し長いような気がする。38本をさらに絞り込んで、本当にインパクトの高い場面を再編集して1時間強にまとめたら、もっと訴求力が大きくなったと想像する。なお、宇崎竜童による音楽は良かった。
面白いのは、この映画の公開当時の観客に“日活アクション映画”の概要を説明しようという意図がまったく感じられないこと。さまざまな映画から引用された断片的なショットを、脈絡も無く積み上げていくだけなのだ。同じ頃に作られた「生きてはみたけれど 小津安二郎伝」(83年)は小津映画の何たるかを体系的に示そうとしていたが、それとは対照的なシャシンである。
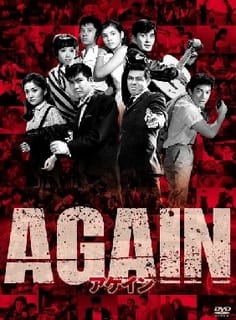
この手法は一見むちゃくちゃだが、別にこれは悪くないと思える。なぜなら、この“日活アクション映画”自体が無国籍風で混沌としたスタイルを取っていたからだ。もちろん私は“日活アクション映画”をリアルタイムで観た世代には属していない(笑)。しかしながら、この映画を観ていると、全盛期の日活映画の持っていた雰囲気や魅力が何となく伝わってくるから不思議なものである。もっともそれは、当時の“日活アクション映画”が多くの若手スターを輩出し、ブームが去った後も彼らが活躍する姿を見ているからなのかもしれない。
引用している作品は「狂った果実」「赤いハンカチ」「帰らざる波止場」「ギターを持った渡り鳥」「泥だらけの純情」「紅の流れ星」など全38本。その中でも「嵐を呼ぶ男」の有名なドラム合戦のシーンを、石原裕次郎主演の井上梅次監督版(57年)と、渡哲也主演の舛田利男監督版(66年)を交互にシンクロさせて編集する場面は本作のハイライトであろう。
監督は作家の矢作俊彦で、構成や脚本も担当している。映画畑とはあまり関係ない人材によるシャシンなので、いろいろと思い切った施策を講じることが出来たのだと思われる。ただし、このネタで上映時間が1時間42分というのは少し長いような気がする。38本をさらに絞り込んで、本当にインパクトの高い場面を再編集して1時間強にまとめたら、もっと訴求力が大きくなったと想像する。なお、宇崎竜童による音楽は良かった。