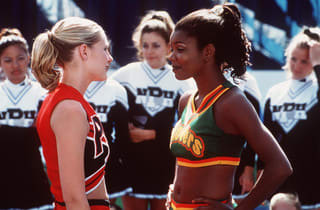とても興味深い内容だ。激変する市場トレンドに対する企業のあり方を、実にヴィヴッドに示している。現時点でも、本書の題材になっている企業と同じような“症状”に見舞われているメガカンパニーが少なくないことを考え合わせると、読む価値は大いにあると言って良い。
1ドルの売り上げで70セントの高収益を得るといわれる世界最大のフィルム会社ソアラ。92年当時にその日本法人に勤めていた中堅社員の最上栄介は、いきなり新事業のデジタル製品の販売戦略担当を命じられる。画像をデジタルデータとして保存する機器とソフトを売れというのだ。その頃はパソコンはまだ高嶺の花。ましてやソアラがリリースする製品は図体ばかりが大きくて機能も貧弱だ。
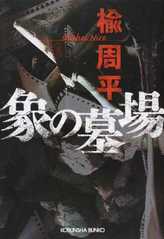
こんなものが市場に受け入れられるはずがないと誰しも思ったが、案の定、在庫の山を築いただけであった。しかし、本社はそれに懲りずに矢継ぎ早にデジタル関係のアイテムを繰り出してくる。社員は右往左往するばかりだが、やがてソアラ内部の紛糾を尻目にデジタルカメラが普及し、フィルムはその役割の大半を終えようとしていた。
誰でも分かる通り、劇中に登場するソアラというのはコダック社のことだ。しかも作者の楡周平はそこに勤めていた。臨場感があるのは当然だろう。実はコダック社は70年代にはすでにフィルムのない世界を予見していた。従来路線のままではダメだと自覚していたからこそ、製薬会社を買収する等の多角化を図ったのだが上手くいかなかった。その理由は、銀塩フィルムの市場があまりにも大きかったからだ。
現状でも十分な利益率が保証されているのに、どうしてワケの分からないデジタル部門に全面シフトチェンジする必要があるのか・・・・という固定観念に会社の上層部は囚われていたのであろう。そのため、同社が発売するデジタル機器は銀塩の世界に片足を突っ込んだままの、極めて中途半端なシロモノに過ぎなかった。そんな売れない製品を持て余している間に、完全に世の中の動きから置いて行かれたのである。また、過度な株主優先の外資系企業の実態や、ドライな社員気質の描写も面白い。
それにしても、一世を風靡した企業が逆にその実績に絡め取られ、新たな一歩を踏み出せないまま破綻(または破綻寸前)に追い込まれた例は、現在の日本でも枚挙にいとまがない。会社が大きくなってくると幹部が“官僚化”し、消費者をなめてかかるようになるのは仕方のないことなのだろうか。あの有名企業やこの大手企業の苦境を見ると、それを痛感する。