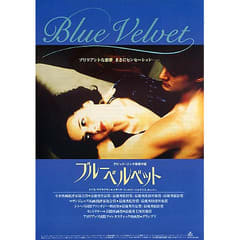2012年に惜しまれつつ世を去った若松孝二監督による95年作品で、間違いなく彼の代表作の一つ。70年代前半に活躍した天才的サックス・プレイヤー阿部薫(町田康)と、その妻でエキセントリックな作風で知られた小説家鈴木いづみ(広田玲央名)の破滅的な愛を描く。実話を元にした稲葉真弓の原作の映画化だ。
ジャン=ジャック・ベネックスの「ベティ・ブルー」やアンジェイ・ズラウスキの「狂気の愛」といった同タイプの作品と比べても、数段本作のクォリティは高い。観る前はこの題材と時代設定からして若松監督の「われに撃つ用意あり」みたいな全共闘世代の甘ったれた思い出話を延々と聞かされるのかと思っていた。ところが映画は薄っぺらい世代論などはね返してしまうほどの強靭な求心力を持つ秀作に仕上がっている。
実際に主人公たちと親交のあった若松監督が、その壮絶な生き方を目の当たりにして、彼らの映画を作ることが同世代の自分の使命だと(某映画祭のシンポジウムで、監督はそう話していた)確信したほどの気合いの入った作品。時代背景に対する先入観みたいな二次的ファクターは入る余地はない。

とにかく主演二人の演技の素晴らしさに圧倒される。私は登場人物について何も知らない。しかし、スクリーン上で描かれる彼らは当時のカリスマだった薫といづみそのものだ(たぶん実際こういうキャラクターだったと思わせる)。今でも二人が生きていてそこに実在するかのような錯覚を覚えてしまう。
二人に見えているのはお互いだけだ。駆け引きや、斜に構えるところは微塵もなく、真正面からぶつかり合い傷ついて消耗していく。周囲の何物にもとらわれることなく、ただ純粋な愛情だけを差し出す二人の姿を追っていくと、恋愛のある種の理想形をそこに見てしまうのだ(それが結果として破滅に向かっていくとしても)。
誰だって心の中ではストレートに想いを相手にぶつけたいと思っている。ただ、周囲や何やらのしがらみで出来ないだけだ。70年代前半という時代背景を越えて、現代にも通じる普遍的なヒーロー&ヒロイン像を創り出したこの映画の成果は大きい。
薫の演奏シーンはフリージャズというジャンルを超越した凄い迫力。二人以外のキャラクターの扱いがイマイチなのは残念だが、目をつぶろう。そして映画の始めと終わりを二人の娘のナレーションで綴ったのも、ハードな展開に柔らかいニュアンスを与えたという意味では正解だった。また、このヴォルテージの高い作品をわずか3週間で撮り上げたという事実には驚嘆あるのみだ。
ジャン=ジャック・ベネックスの「ベティ・ブルー」やアンジェイ・ズラウスキの「狂気の愛」といった同タイプの作品と比べても、数段本作のクォリティは高い。観る前はこの題材と時代設定からして若松監督の「われに撃つ用意あり」みたいな全共闘世代の甘ったれた思い出話を延々と聞かされるのかと思っていた。ところが映画は薄っぺらい世代論などはね返してしまうほどの強靭な求心力を持つ秀作に仕上がっている。
実際に主人公たちと親交のあった若松監督が、その壮絶な生き方を目の当たりにして、彼らの映画を作ることが同世代の自分の使命だと(某映画祭のシンポジウムで、監督はそう話していた)確信したほどの気合いの入った作品。時代背景に対する先入観みたいな二次的ファクターは入る余地はない。

とにかく主演二人の演技の素晴らしさに圧倒される。私は登場人物について何も知らない。しかし、スクリーン上で描かれる彼らは当時のカリスマだった薫といづみそのものだ(たぶん実際こういうキャラクターだったと思わせる)。今でも二人が生きていてそこに実在するかのような錯覚を覚えてしまう。
二人に見えているのはお互いだけだ。駆け引きや、斜に構えるところは微塵もなく、真正面からぶつかり合い傷ついて消耗していく。周囲の何物にもとらわれることなく、ただ純粋な愛情だけを差し出す二人の姿を追っていくと、恋愛のある種の理想形をそこに見てしまうのだ(それが結果として破滅に向かっていくとしても)。
誰だって心の中ではストレートに想いを相手にぶつけたいと思っている。ただ、周囲や何やらのしがらみで出来ないだけだ。70年代前半という時代背景を越えて、現代にも通じる普遍的なヒーロー&ヒロイン像を創り出したこの映画の成果は大きい。
薫の演奏シーンはフリージャズというジャンルを超越した凄い迫力。二人以外のキャラクターの扱いがイマイチなのは残念だが、目をつぶろう。そして映画の始めと終わりを二人の娘のナレーションで綴ったのも、ハードな展開に柔らかいニュアンスを与えたという意味では正解だった。また、このヴォルテージの高い作品をわずか3週間で撮り上げたという事実には驚嘆あるのみだ。