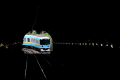(お達者世代のカブリツキ@石山坂本線車内)
石山坂本線を走る車両は、それぞれ運転台側のスペースが優先座席になっております。本来であれば初めて乗る路線はガッツリと前でカブリツキたいところではあるのですが、よっぽど空いている状況でもないとこのスペースに若輩者が足を踏み入れるのはハードルが高い(笑)。よってカブリツキゾーンは妙に平均年齢の高い様相を呈するわけでありますが、別にマニア風でもない地元のジイちゃんバアちゃん連中も、何となくみんな前の方を向いてポーっと流れる景色を見ている。そんなお達者世代のカブリツキ。
三井寺から乗った電車が途中の近江神宮前行きだったので、強制的に近江神宮前駅にて電車を降ろされる。日中は2本に1本が近江神宮前行きなので、ここから終点の坂本までは約15分ヘッドとちょっと列車頻度が下がります。近江神宮前止まりはホームにて乗客を降ろした後、引き上げ線がないので下り本線上で上りの石山寺行きの通過を待ち、先行電車が駅を出るとやおら片渡り線を使って折り返して来ます。近江神宮前駅は京津線・石山坂本線全車両のメンテナンスを行う錦織車庫(錦織工場)を併設しており、大津線全体の運転上のキーポイントとなる駅です。以前は電車の改造や製造もここでやっていたそうだが。
狭いスペースに目いっぱいの留置線を詰め込んだようなせせこましい錦織車庫。大半の電車は出払っておりますが、そんな現役車両の留守を預かるように車庫の片隅には地上時代の京津線の雄・80形が静態保存されております。塗装が剥がれてあまり良い保存状態とは思えませんが、裾絞りの曲線も優美なヨーロピアンスタイルのボディは未だに存在感十分。
名前の通り駅の北西には近江神宮があり正月などは参拝客でかなり混雑するようですが、見た感じ駅前に何がある訳でもなさそうなので自販機で買ったコーラを飲みながら後続の電車を待つ。皇子山の駅から坂を上り、「紀の国わかやま国体」ラッピングの707編成が到着。なんで大津でわかやま国体なんだ?と思うのですが、カヌーは琵琶湖を会場にしてやるんだって。へえ。
近江神宮前を出た電車は、琵琶湖の北岸をやや高度を上げ、比叡山の山裾を北へ向かって走ります。この辺りに来るとやや駅間距離も長くなり、大津市街に比べるとずいぶんとスピードの乗った走りを見せてくれるのでありますが、車窓右側には水田の向こうに琵琶湖と、遠く鈴鹿山脈が眺められます。そーいや去年のGWは遠州鉄道に乗りに行った事を思い出す。去年はとほつあわうみ、今年はあわうみの旅。
近江神宮前から約10分で終点の坂本駅。何だかデザイナーズ風のおしゃれな外観の駅です。ここからは坂本ケーブルで比叡山延暦寺へ登る事が出来ます。そして坂本駅と言えば高校野球ファンにはおなじみの比叡山高校!村西哲幸を擁して春夏連続出場と言うのが記憶に新しいですが、オッサンパヲタとしては1981年シーズンに15勝0敗と言う驚異的な記録を残し、田中のマーくん以前の元祖無敗男として名を馳せた日本ハムの間柴茂有だね。ヘビみたいな顔してて、当時の大沢監督、江夏と並ぶとまあカタギに見えなかったw
坂本は古くからの比叡山の門前町で、「穴太衆(あのうしゅう)」と言われた石工の集団によって築かれた石積みの家並みが続く。穴太衆は近江国を中心に城郭の建築に多く携わり、坂本の2つ前にその名も「穴太」と言う駅があって、その辺りの出身らしい。そういや琵琶湖から鈴鹿山地を越えた三岐鉄道の北勢線にも同じ読みで「穴太」駅(三重県いなべ市)があるんだが、なんか関係があるのだろうか。さらに考えを膨らますと、三重県の旧県名「安濃津(あのつ)県」との関係は…?と思いは尽きないのであるが、良く分からないので誰かまとめて下さいw