今朝、朝食がてら、区役所へ行って、期日前投票を済ませてきました。
来週の日曜日は「夏のロングドライブ第二弾」として、この夏二度目の帰省からクルマで帰ってくる予定にしています。順調ならば昼頃には帰着しているはずですので、投票に行けるとは思いますけれど、一応、念のためということで…。
大昔、「不在者投票」なるものを体験したことがありましたが、その時は、不在者投票をする理由とか、投票日当日の所在地の住所なんかを書かされた後、投票用紙を封筒に入れて係員に渡したか何とかした記憶があります。
一方、きょうの期日前投票は、投票整理券(だか投票所入場券だか)の裏側に印刷されている「宣誓書」に署名して、あらかじめ列挙されている期日前投票する理由から該当するものにチェックして、それから先は、普通の投票と同じでした。
選挙人名簿と照合する人、投票用紙を発行してくれる人、投票立会人の人たちはもちろん、記入台や投票箱も、投票日と同じ「セット」になっていました。
それにしても、期日前投票の開始日から投票日前日までの毎日、7~8人の人間を確保しておくってのは、随分とお金 がかかるでしょうねぇ。ここまでやって、投票率が高ければまだしも、30~40%台(無風に近い首長選挙とか、市議会議員選挙だとあり得る)だとうんざりです。係員や立会人の人たちだって、市民の冷たい視線と本人のやりがいの無さでつらいと思いますよ。
がかかるでしょうねぇ。ここまでやって、投票率が高ければまだしも、30~40%台(無風に近い首長選挙とか、市議会議員選挙だとあり得る)だとうんざりです。係員や立会人の人たちだって、市民の冷たい視線と本人のやりがいの無さでつらいと思いますよ。

実は私、昨日も区役所に行きました。期日前投票をしようと思って。
ところが、係員さんに「最高裁判所裁判官の審査は明日(23日)からですが、よろしいですか?」と言わまして、「よろしくないです 」と、出直すことにしました。8月6日の記事「最高裁判所裁判官の国民審査」で書きましたように、この制度にかなりの不満を持つ私としては、せっかくの権利を放棄するのはどうかと思いますものね。
」と、出直すことにしました。8月6日の記事「最高裁判所裁判官の国民審査」で書きましたように、この制度にかなりの不満を持つ私としては、せっかくの権利を放棄するのはどうかと思いますものね。
そういうこと(?)で、最高裁判事の国民審査のことをもうちょいと書きます。
昨日、期日前投票に出かける前、今回の審査の対象となる裁判官はどんな人たちなのだろうかと調べてみました。っつうか、衆院選立候補者&政党も含めて、「公報」がまだ来ていない
衆院選の方は、候補者個人によほどの問題がない限り、政党本位で選べば良いわけで(と私は思っています。今の仕組みならばね)、各党のマニフェスト(のようなもの)やマスコミ報道などで、ある程度の情報は得られます。
ところが、最高裁判事となると、さっぱりです。まさか、最高裁の判例をひもとくわけにはいかないでしょう。
いったい、公報はいつ来るのだろうかと思って調べてみました。すると、公報の配布期日については都道府県の選挙管理委員会が「規程」を定めているようでして、いくつかの自治体の規程をパラパラと読んでみますと、概ね、審査日(総選挙の投票日)の4~5日前までに都道府県選管が市町村選管に配布し、市町村選管が有権者に配布するのは審査日の2日前まで、というのが相場のようです。
つまり、投票日(審査日)の2日前、金曜日までに配布すれば良いという規程が多いのですよ。
投票率を上げるべく、期日前投票をしやすくしつつある一方で、「最高裁判所裁判官国民審査公報」の規程は旧態依然としているわけですな。

それはともかく、審査対象となる裁判官のプロフィールなり関わった判決なんぞを一覧で見られるものがないか、ネットで探すと、こんなのにぶち当たりました。
これは、自ら「平和と民主主義を求める国民的な大運動であった60年安保闘争のなかから生まれた法律家団体です」と謳っているように、政治的な中立とは無縁の日本民主法律家協会(日本共●党の友好団体のはず)が作ったビラです。
ビラの反対側は、この団体の主義主張が濃厚に打ち出されています(表紙にどでかく書かれた「最高裁を憲法と人権の砦に変えよう!」の、特に「砦」には思いっきり引いてしまいます )が、上に載っけたページは「主な関与判決」が恣意的に選び出されている可能性があるにせよ、まぁ、審査対象の裁判官がどんな方なのかを知る手だてにはなりそうです。
)が、上に載っけたページは「主な関与判決」が恣意的に選び出されている可能性があるにせよ、まぁ、審査対象の裁判官がどんな方なのかを知る手だてにはなりそうです。
ビラはこちらからダウンロードできますので(上にもPDFファイルへのリンクを貼ってます)、ご興味がありましたらどうぞ。
それにしても、法律家の団体が、「最低でも、1000万台の×印票、そして、棄権の自由を徹底して2000万台の棄権票を目標に運動をしてきました」というのは、どうなの?って感じです。

公報の配布日程もさることながら、どうして国民審査の期日前投票が今日23日からなのでしょうか? 衆院選の期日前投票と同じタイミングにすればよいのに、と思います。
衆院選と違って、投票用紙にあらかじめ審査対象者の氏名を印刷しておかなければならないから? でも、立候補を締め切るまで誰が立候補するか判らない衆院選と違って、審査を受けることになる裁判官は事前に判るはずでしょう。
まったく、何から何までいい加減な制度 だと思います。
だと思います。
と、ここで、最高裁判所裁判官の国民審査と同じように、「何も書かなければ信任、×を書いたら不信任」的な投票をやっている国があることを思い出しました。
そう、自称「共和国」です。「共和国」の最高人民会議の代議員選挙は、各選挙区に候補者は一人しかいなくて、投票用紙にはあらかじめ候補者の名前が印刷されているんだとか。
そして、候補者に賛成(信任)する人はそのまま投票、反対(不信任)の人は投票用紙に斜線を引いて投票するのだそうです。
今年3月に行われた第12期代議員選挙では、投票率が99.98%、候補者への賛成票率が100%と、およそまともではない結果が出ていますが(こちらをご参照)、こんな投票方法をとっていたら、当然でしょう。立会人が見ている前で、投票用紙に書き込みができますか?
でも、そうして考えると、賛成票率が100%であるのは不思議ではないにしろ(開票さえやっていないという噂もある)、投票率の高さが凄いです。
寝たきりであろうと、当日急病になろうと、有権者の99.98%が投票するというこの国民の熱意 、民主国家のカガミです(どこが
、民主国家のカガミです(どこが )。つくづく、こんなカガミの国に生まれなくて良かったと思います。
)。つくづく、こんなカガミの国に生まれなくて良かったと思います。
 先立つネタ:最高裁判所裁判官の国民審査
先立つネタ:最高裁判所裁判官の国民審査























 )です。
)です。 のようなもので、こんな風に使います。
のようなもので、こんな風に使います。

 かも…。
かも…。 」とばかりにエントリーしておりました。
」とばかりにエントリーしておりました。 を
を





 を使うことはありえないですよね。
を使うことはありえないですよね。








 で戻ってきました(図らずも、
で戻ってきました(図らずも、 めちゃくちゃ
めちゃくちゃ が
が

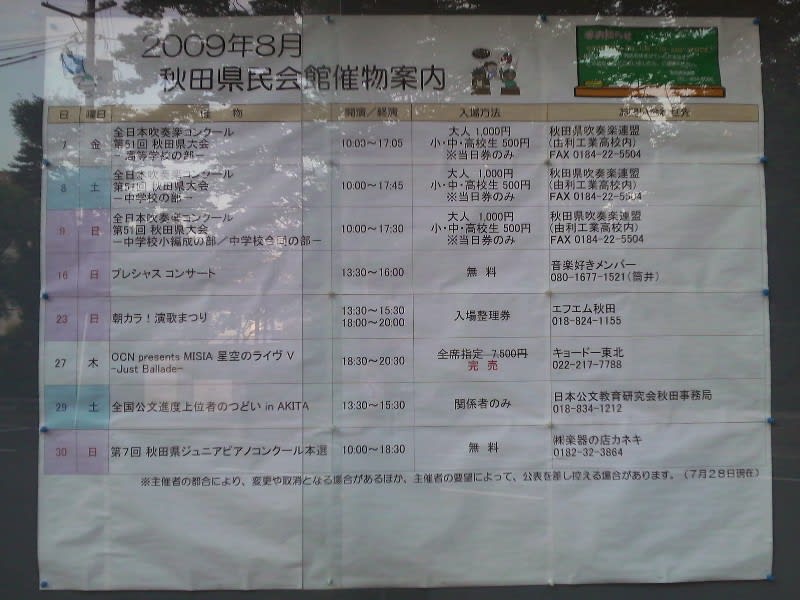

 の風情が漂っています。
の風情が漂っています。





















