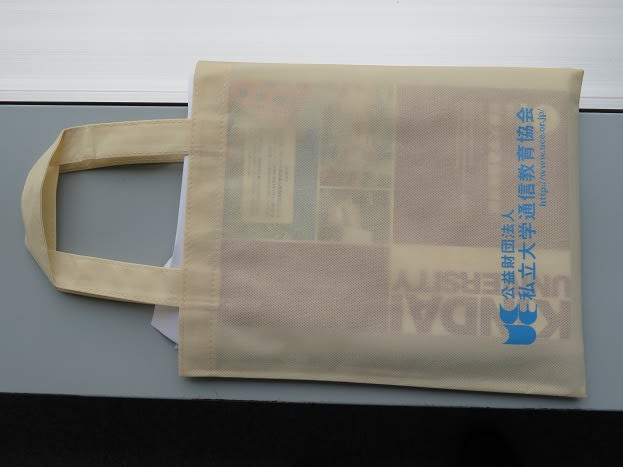先般、放送大学から成績通知書が送られてきました。
2022年第2学期に取得した単位は「研究指導」の8単位のみ。評価は「B」。まあ、力量の至らなさが詳らかになったわけですが、それと一緒に同封されていた「単位習得状況一覧(単位認定書)2022年度第2学期」を見てみると、〇A×7単位、A×12単位、B×14単位となっています。GPAではAを切ってしまいましたが、大学院の学修の価値は、概ね修士論文。その修士論文の評価ともいえる「研究指導」は「A」と「B」・・・。違うテーマの論文を「〇A」2本で揃えらえたら、地力あるね!って印象なのに、、、
とはいえ、この記事で言いたいのはそこではありません。7+12+14=33単位で修士の学位を2つ頂けるってこと。「えっ、大学院って、そんなにお手軽に学位が取れるの?」って思えてしまいません??
放送大学大学院の場合、ミニマム30単位で大学院を修了できます。アカデミックスキルズ1単位を取得すると31単位になりますが、確か、必須じゃなかった気がします。
他大学院を修了した者は10単位免除の20単位で修了できます。2つのプログラムを修了する場合、本来なら20単位+20単位=40単位が必要となるはずですが、重複して認定されるケースがあり、私は人間発達科学プログラムを履修している際、意識して社会経営科学プログラムの単位を履修したため、33単位で2つの修士を取得することができました。
大学を卒業するのに多くの大学で124単位必要なのですが、大学院を修了する場合、多くの大学が30単位です。そう考えると、わずか30単位(単位数的には大学の1/4未満)で修士が取れる!なんだかできそうに思えてきませんか?
でも、大学院での学位取得において、ミニマムは30単位ですが、すべての大学院が30単位というわけではありません。武蔵野大学大学院の場合、ミニマム40単位でした。それでも、40単位ならなんとかなりそうです。しかし、例えば「法科大学院」なんて一時ブームになりましたが、京都大学の法科大学院で法学既修者でない者が学位を目指すと、3年間で96単位必要とのこと・・・いただける学位は法務博士(専門職)となりますが。ちなみに、WIKIでは『「法務博士(専門職)」の学位は専門職学位の1つであり、「博士」の語を含むものの、学位請求論文の審査を経て授与される「博士の学位」とは別個のものである』とされています。 ちょっと違うので比較することの是非が問われますが。
ちょっと前にも書きましたが、一度学位を取得すると、単位免除の恩恵を受けることがあります。まあ、放送大学のように、124単位が16単位になるケースは稀ですが。アカデミックの世界って、学んだ者に対して優しい感じがします。今までの努力が報われる世界。その進化形が学位授与機構?多方面で取得した単位を学位に変換してくれる存在。設立の趣旨からすると、私のような利用者を想定していなかったでしょうが、以前は、半年ごとに各分野の学位を取得することができ、一気に専門性を高めましたから。
学位がすべてではないし、学位をたくさん持ってても何の意味もありません。しかし、学位を目標にして学ぶことで、何かしら成長しているはずという自己満足。そんな自己満足にしか過ぎないことですが、学位として形に残ることが、なんとなく安心感を与えてくれるわけで。