昨日、Dr.Kさんが、伊万里の初期の物と思われる野香炉をブログアップされました。
ウチにも香炉はいっぱいあるのですが、屋外の物(墓場用)となると・・・・・そうそう、お墓の花生けがあったはず、とあちこちさがし回ったあげく、雑花器(^^; )ばかりが入っている段ボール箱の中に隠れているのをひっぱり出しました(^.^)

口径 3.4㎝、底径 4.8㎝、高 22.1㎝。江戸前ー中期。

じつはこの品、私にしては珍しく高額の物を買ったときに、骨董屋がオマケにくれた物です。
主人曰く、「お墓で香をたく物で、けっこう時代があるよ」。
でも香に使うにしては、どう見ても細長すぎます。やはり、入れるのは花でしょう。

胴には、鋭い面取りがなされています。

いかにも美濃物らしい糸切り底。
この品が、本当に墓の花生け用なのかどうかは不明です。下部の鉄釉が掛かっていない部分を土に埋めて使うのかも知れません。

そんな雑器なのですが、一応美濃物ですから、例によって欲目で眺めてみると・・・・


面取りで生じた曲線は、なかなかのフォルムです。

内側は底まで鉄釉が掛かっているのですが、口縁付近の内と外には、

黒化した鉄釉の流れが、微妙な味をだしています。
茶ごころのある人がとり上げれば、化けるかもしれませんね(^.^)












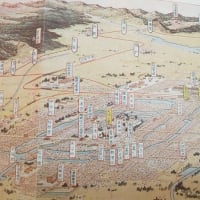




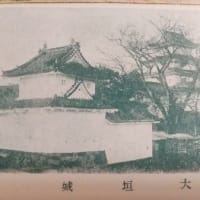
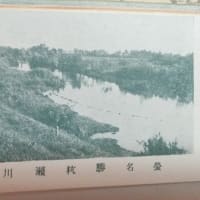







底の年輪みたいな輪形とナタで削ったみたいな力強さがいいと思いました。線香でなく、やっぱり花です(^-^)/
色も渋いので、何を入れても様になりそうです。
ただ、この頃、意識しすぎるのか、花を入れるところまでなかなかいけません🤔
また、面取りの曲線など、心憎いほどですね(^_^)
お墓用の花生けだとすれば、よくぞ残ったというところですね!
これは、茶室での花生けに化けそうですね(^_^)
大きなオマケでしたね(^-^*)
我が家の野香炉(?)は、結局は、平戸系の木原東窯製の染付香炉のようで、古くとも元禄くらいなようです。
入りそうだと思って拝見しました。
細長くてバランスを取るのに苦労しそうですが、花入れとして面白いと思います。
線香立てとしての使用なら、お墓がお洒落になりそうですね(^_-)-☆
考えてみれば、昔は土の上に石が置いてあるだけの墓でしたから、こういう花生けをその前に設置したら、けっこうなものだったでしょうね。私も数年前までは、竹を切って、墓用の花筒を毎年作っていました。バカにならない数で手間が大変でした(^^;
ということで、今回の品は、中級武士の墓用花生けと決定しました(^.^)
野香炉は木原に落ち着きましたか。ヒビ焼きだけが木原ではないでしょうから。木原窯については資料が少ないので、これからに期待ですね。
この陶器も、姿形からして竹ですね。そのままで倒れませんが、小々あぶなっかしいでです。でも、花との相性は良さそうです。
越後美人さんなら、この花器を最大限に活かしていただけること間違いないです。