 >
>画像はマウスオン・クリックです。
いつもよく通る道沿いの梨畑に、今まっ白な梨の花が一斉に咲き誇っています。
桜や桃の花が散る頃咲き出した梨の花は、まるでそこだけ春の雪が下りたように
白く、遠くからでも分ります。
道路脇に車を止めて棚造りされたいる梨畑を見せてもらいました。
梨の花をこうして見るのは初めて、、、、
棚の上で上向きに咲く真っ白な梨の花は青空にくっきりと奇麗です。
梅や桜の花びらにも似ていますが、赤いおしべが可愛いこと!!
梨農家の方にとっては、これからが一番忙しい時期とか。
受粉作業が待っているんですね。
秋にはたわわに実った美味しい梨が出来ることでしょう。
 >
>画像はマウスオンです。
所用で行った市役所の裏庭に咲いている、これは真っ白いハナミズキです。
大きな枝ぶりに満開のハナミズキの白い花がゆったりと咲いていました。
このハナミズキは、アメリカヤマボウシともいわれるようで、かつて日本からワシントン
に贈られたソメイヨシノの返礼として贈られた花だったようです。
アメリカから渡来したときに、日本の山法師に似ているところから付いた名前とか。
今では花色も白からピンク、赤に近いものまで様々のようですが、総苞の白いものが
原種で淡紅色や紅色は園芸種のようです。
このハナミヅキ、白や紅色の花弁状の4枚は葉の変形で、総苞片と呼ばれ、
真ん中の球状の小塊が花なんだそうですね。
知りませんでした。
 >
>画像はマウスオン・クリックです。
我が家にも小さいですが、白い花が咲いています。
ご近所からの頂き物ですが、これ何の花か分りますか??
花は白い小さい小花ですが、花は丹頂鶴の頭、長い茎を首、葉の姿を羽根に見立
てたと言われる丹頂草です。(別名:イワヤツデ、ユキノシタ科)
花の時期以外は、根元が扁平な球根のようで枯れたような状態になりますが、毎年
今頃になると可愛い花をつけててくれます。
ほったらかしなのに健気ですね。(笑)
ドウダンツツジも咲き出しました。
すずらんのような白い可愛い花が下がっています。
庭の隅のユキヤナギも、よくみると白い可憐な花ですね。
******************
コメント編集中、誤って皆様からたくさん頂いたコメントを消してしまいました。
うっかりミスであっという間の出来事に呆然です。
本当に申し訳ありませんでした。
souuさん、チーコさん、non_nonさん、marucoさん、松ぼっくりさん、yoccoさん、
naoママさん、jisamaさん、ももちゃんの飼い主さん、satomineさん、(順不同)
皆様ほんとうほんとうにごめんなさい!!
以後十分気をつきますのでお許しを!!!
幸い原文は残っていましたので再投稿いたしますが、コメントは結構です。






















 >
> >
>
 説明文1';san1.filters[0].play();">
説明文1';san1.filters[0].play();"> 説明文2';san1.filters[0].play();">
説明文2';san1.filters[0].play();"> 説明文3';san1.filters[0].play();">
説明文3';san1.filters[0].play();"> 説明文4';san1.filters[0].play();">
説明文4';san1.filters[0].play();"> 説明文5';san1.filters[0].play();">
説明文5';san1.filters[0].play();"> 説明文1';san1.filters[0].play();">
説明文1';san1.filters[0].play();"> 説明文1';san1.filters[0].play();">
説明文1';san1.filters[0].play();"> 説明文1';san1.filters[0].play();">
説明文1';san1.filters[0].play();"> 説明文2';san1.filters[0].play();">
説明文2';san1.filters[0].play();"> 説明文3';san1.filters[0].play();">
説明文3';san1.filters[0].play();"> 説明文4';san1.filters[0].play();">
説明文4';san1.filters[0].play();"> 説明文5';san1.filters[0].play();">
説明文5';san1.filters[0].play();"> 説明文1';san1.filters[0].play();">
説明文1';san1.filters[0].play();"> 説明文1';san1.filters[0].play();">
説明文1';san1.filters[0].play();"> モンセラ';tyu.filters[0].play();">
モンセラ';tyu.filters[0].play();"> ベロナ';tyu.filters[0].play();">
ベロナ';tyu.filters[0].play();"> ダブルダッチ';tyu.filters[0].play();">
ダブルダッチ';tyu.filters[0].play();"> フオックスロット';tyu.filters[0].play();">
フオックスロット';tyu.filters[0].play();"> モンテカルロ';tyu.filters[0].play();">
モンテカルロ';tyu.filters[0].play();"> 桃太郎';tyu.filters[0].play();">
桃太郎';tyu.filters[0].play();">
 説明文1';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">
説明文1';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();"> 説明文2';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">
説明文2';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();"> 説明文3';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">
説明文3';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();"> 説明文4';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">
説明文4';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();"> 説明文8';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">
説明文8';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();"> 説明文5';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">
説明文5';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();"> 説明文6';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">
説明文6';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();"> 説明文7';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">
説明文7';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();"> 説明文8';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">
説明文8';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();"> 説明文8';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">
説明文8';inu.filters['DXImageTransform.Microsoft.GradientWipe'].play();">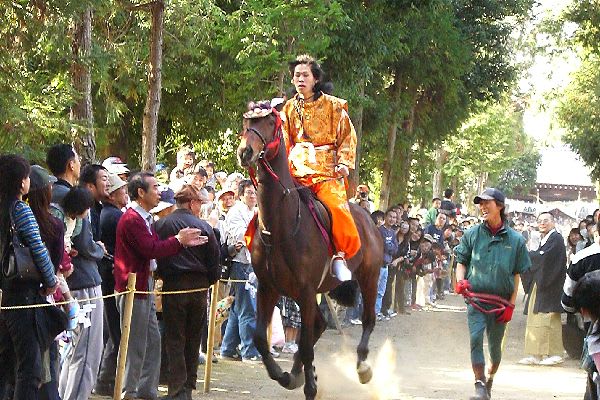

 >
>