8強の壁に跳ね返されたところで、一時的な俄かサポータのサッカーW杯が終わった。
戦前から今回のジャパンは史上最強と報じられ、予選リーグでドイツ・スペインを破ったこともあって「新しい景色(ベスト8以上)」が見られるのかと期待したが、やはり欧州・南米には及ばなかったようである。
以前には組織力の欧州、個人技の南米・アフリカと云われて信じてきたが、ダイジェスト版の予選各試合を観ると得点を挙げた選手には個人技に長けたビッグネームが名を連ねているとはいえ、彼らに球を持たせるには中盤の組織力が必要であり、勝利には組織力と個人技の両方が必要であることが分かった。
これまでのW杯は、新聞で報じられる試合結果しか観なかったが、今回はネット情報を併せて見ることにした。ネット記事の大半は往年の名選手・監督経験者ではない熱狂的ファンからのもので、対コスタリカ敗戦時には「監督の采配非難」と「選手の戦犯探し」に溢れ、スペイン戦勝利後は一転して監督・選手の賞賛一辺倒となり、ネット記事を世論と観れば「手のひら返し」は当然かとも思うものの、矢面に立つ監督・選手には同情を禁じ得ないものである。
かって、プロ野球の名監督が「監督の采配で勝敗が決するのは年間130試合のうち多くて2・3試合」と述べられたことを記憶している。また、オーケストラ指揮者は、いかに名手と雖もステージ上での一発勝負では満足な結果は出せず、成否のカギは事前の練習・音作りにあるとも聞いている。
今回W杯の勝敗の分かれ目は、故「野村克也氏」が好んで引用し、本ブログでも使用している松浦静山(江戸時代期の平戸藩主、剣術の達人)の名言「勝ちに不思議な勝ちあり、負けに不思議な負けなし」が端的に表しているとするならば、ベスト8以上に到達できるヒントはコスタリカ戦とクロアチア戦に隠されているのかもしれない。
多くのヒーローを産む傍らで、個人攻撃を浴びた選手も生まれたW杯。
しかしながら、強豪国がひしめく「死のE組」を突破したことは、八咫烏ブルーにとっては誇れるものと思う。
願わくば、今回の代表選手の将来が輝かしいものであり、次回W杯(何処であるかも知らない)に向けて研鑽に努めて欲しいと願うところである。
俄かフアンに夢と些かの睡眠不足を与えてくれた森保監督と選手に、感謝と同時に、長友佑都選手の口調で「ブラボー!!」を捧げて。















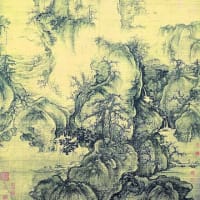




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます