アルピニストの野口健氏が、病院船の保有に関して国会で論議することを提言しているコラムを読んだ。
東日本大震災では、病院船とまでは呼べないものの相当な医療設備を持つ揚陸艦を配備したにもかかわらず、総合的な運用に関しては「トモダチ作戦」に参加した米海兵隊から《日本の水・陸両用能力が脆弱》と指摘されたように、病院船とそれを支援(利用)する陸海空の総合・統合運用力は不足していると思っている。
統合運用については、陸海空自衛隊を一元的に指揮する常設組織「統合作戦司令部」が3月に編成されることから、水陸空両用能力も改善されると期待しているが、病院船に関しては大規模災害の度に話題とはなるものの、喉元過ぎれば語られることも少ない。
病院船の保有に関する要望が一過性となるのは、偏にコストがかかり過ぎることであるように思う。
病院船については、米海軍病院船”マーシー”が東京に寄港した際に紹介したが、再度勉強してみた。
実は、病院船の厳密・正確な定義は無い様である。
病院船の国際的な法定義は、1949年の「海上における傷病者の病気の改善に関する条約」であるらしいが、それとても、非武装、船体の白色塗装、船体・装備の全てに赤十字の着標、配備の10日前に紛争の当事者に名称提示が義務付けられているだけであるらしい。
現在病院船として広く認知されているのは、アメリカのマーシー級2隻、中国の兵員輸送艦を改装した1隻、ロシア海軍の3隻のみとされている。インドネシア海軍も1隻運用しているが船体塗装・武装などから国際的な病院船とはされていないようである。
その他にも、
〇河川や湖沼に住む地元住民に医療支援を提供する小型船(ボリビア、ブラジル、チリ、ペルー、タイ)
〇 小規模医療支援船(インド、インドネシア、メキシコ)
〇人道支援・避難輸送船(ドイツ、英国)
〇民間病院の船舶(スペイン、各NGO)
等が挙げられている。
病院性の有効性について考える前に米海軍マーシー運用を観てみると、年間の内、半年は造船所等でのメンテナンス(通常の艦船整備+医療機器の更新等)に費やされており、残りの半分で人道支援・災害救援などの平和維持活動に当っているが、湾岸戦争以後は大きな戦地出動はないようである。通常は少数の保守要員だけが乗船しており、出動時には残余の乗員と、予め指定されている民間人を含む医療スタッフが乗船することになっており、緊急出動に要する時間は5日間とされている。
有効性についてであるが、先ずコストを考えれば、建造費は艦船よりは安いが、維持費は艦船と同等であるように思える。カンボディアPKO時の経験であるが、搭載した医薬品の賞味期限は概ね3か月であり、診療実績の無い病院船では年に4回全医薬品を更新しなければならない。医療機器についても、随時更新する必要があるだろうと思える。
活用についても、病院船は大規模災害が無ければ1年間全く無診療・非活動である公算が高く、更には内陸部での災害に対しては無力である。そのような運用実績の病院船であれば、乗組員もマーシーと同様の体制とならざるを得ないように思う。
このような活動では、非活動嫌いの会計検査院の格好の餌であろうし、最大のネックは緊急時に召集する人的資源がないことである。運行するための自衛官乗員については、他艦船が7~80%の定員で運用されている現実では抽出もままならないだろうことは明白である。更に、民間医療スタッフの活用体制については法整備されていない実情にある。フォークランド紛争で出動した英軍には、病院船クイーンエリザベスが随伴したが、客船の徴用については平時からの取り決めによって、医療従事者については現役・予備役・後備役に加えて民間人の招集・応召に依ったとされる。それらのどれ一つとして、日本では取り組みや制度がないのではないだろうか。
野口氏の提言は、真に的を射たものと思うが、前提として平時における盛大な無駄を容認することと船舶の徴用や民間人の招集についての法整備が為されなければならないように思える。さらに重要なのは、国民が”百俵の米”に堪える気持ちであるように思う。















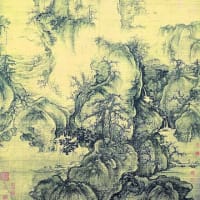




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます