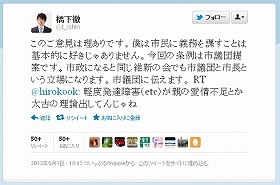可能な限りワンストップで手続きなどが行えるよう、海老名市は7日、総合窓口を始めた。手続きに来る市民の9割が1カ所の窓口で済む見込み。市によると、同様の窓口は県内にもあるが、福祉関係を一括にしたものはないという。
連休中に1階フロアを改修。新窓口を住民異動や戸籍関係の「市民総合窓口」と福祉関係の「福祉総合窓口」に分け、複数の課にわたる手続きの場合、市民は座ったままで、担当課員が入れ替わる形で対応する。
市民総合では、住民票や戸籍証明などの発行のほか、転入・転出など住民異動、出生、婚姻など戸籍関係、転入時の学校指定などを扱う。福祉総合は国民健康保険(国保)、国民年金、保育園・幼稚園、障害者手帳、介護保険などの手続きを行う。
窓口利用の効率化が図られ、転入、学校関係、国保の手続きで計1時間にもなった待ち時間が半分ほどになるという。それぞれの窓口に案内係(コンシェルジュ)を置き、キッズスペースや授乳室なども配置した。
この日行われた開設式で、内野優市長は「市役所は縦割りと言われるが、総合窓口は横の連携が必要になる。市役所全体に波及して、市民のための市役所にしたい」とあいさつした。
住民票を取りに来た男性(34)は「格段によくなった。案内係がいて、分かりやすくなった」と変更を歓迎していた。
市は今後も総合窓口に加えられる手続き業務などを探す方針。内野市長は「将来的にはすべてを1人の職員が対応できるよう、その意識を持たせたい」と話している。

スタートした市民総合窓口。奥は福祉総合窓口=海老名市役所
カナロコ(神奈川新聞) -2012年5月7日
連休中に1階フロアを改修。新窓口を住民異動や戸籍関係の「市民総合窓口」と福祉関係の「福祉総合窓口」に分け、複数の課にわたる手続きの場合、市民は座ったままで、担当課員が入れ替わる形で対応する。
市民総合では、住民票や戸籍証明などの発行のほか、転入・転出など住民異動、出生、婚姻など戸籍関係、転入時の学校指定などを扱う。福祉総合は国民健康保険(国保)、国民年金、保育園・幼稚園、障害者手帳、介護保険などの手続きを行う。
窓口利用の効率化が図られ、転入、学校関係、国保の手続きで計1時間にもなった待ち時間が半分ほどになるという。それぞれの窓口に案内係(コンシェルジュ)を置き、キッズスペースや授乳室なども配置した。
この日行われた開設式で、内野優市長は「市役所は縦割りと言われるが、総合窓口は横の連携が必要になる。市役所全体に波及して、市民のための市役所にしたい」とあいさつした。
住民票を取りに来た男性(34)は「格段によくなった。案内係がいて、分かりやすくなった」と変更を歓迎していた。
市は今後も総合窓口に加えられる手続き業務などを探す方針。内野市長は「将来的にはすべてを1人の職員が対応できるよう、その意識を持たせたい」と話している。

スタートした市民総合窓口。奥は福祉総合窓口=海老名市役所
カナロコ(神奈川新聞) -2012年5月7日