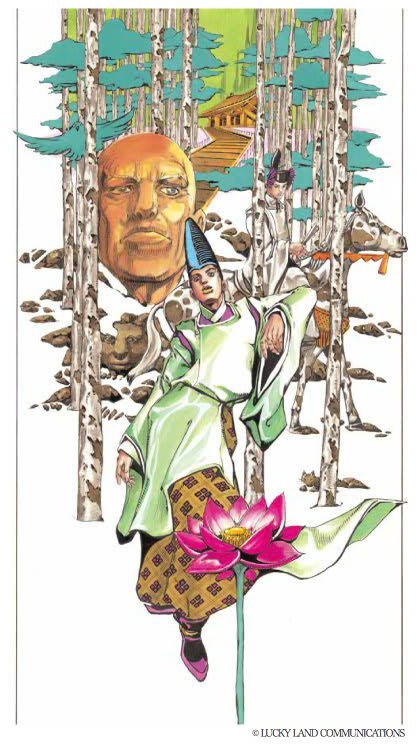「まだ踏み出せない」「あの笑顔が…」。事件発生から間もなく2カ月。犠牲者の家族、津久井やまゆり園の職員らは、癒やされることのない悲しみと無念の思いの一方で、何とか前へ踏み出そうとしている。
◆このままでは…
「(犠牲者の名前や顔写真が出ない状況が)このままじゃいけないのは分かっている」
関係者によると、都内住む犠牲者の家族は、こう話しているという。
県警は事件をめぐり、障害者への配慮などを理由に被害者の実名公表を拒んだ。障害者団体は「逆に障害者への差別になっていないか」と批判、メディアの専門家からも疑問が出された。
この家族は「過去、障害者が家族の中にいるということで白い目で見られたこともあり、社会は変わってきているといえネット上にも心ない書き込みが実際にある。まだ一歩踏み出す勇気がない」とも語っているといい、深い葛藤がうかがえる。
一部の家族はできる限りメディアの取材に応じ、こうした声を代弁しようとするかのように訴え続けている。
腹部などを刺されて一時意識不明となった入居者、尾野一矢さん(43)の母、尾野チキ子さん(75)は、今月11日にやまゆり園で開かれた家族会で、ある遺族から声を掛けられた。
「いつも(報道を)見てるよ。これからも家族の声を発信し続けてほしい」
チキ子さんは「涙が出るほどうれしかった。これからも家族の思いを訴えていければ」と必死で前を向く。
◆バラバラに
同園に約2年間勤める男性職員(28)は毎日、園と約40人の入居者らが移った厚木市内の施設を往復している。男性が担当するホームでは、入居者3人が犠牲となった。
「事件後は(職員、入居者とも)皆ばらばらになってしまった。やっと入居者と打ち解けてきたところだったのに」と憤る。
「今は事件を特に意識しないようにしている」と話すが、「一緒に洗濯物をたたんだり食事をしたり、何気ない当たり前のことがもうできないんだと思うとつらい」と語る表情からは深い悲しみがにじむ。
園に約36年間勤めた元職員、太田顕さん(73)は事件当日早朝、テレビで事件を知って駆け付け、体育館で入居者の食事の世話などを手伝った。職員時代に一緒に過ごした入居者数人と再会。ほっとしたが、「いつもいる人がいない」ことにも気付いた。
ある男性犠牲者の元には、家族が月1回面会に訪れていたという。
「食事をしたり散歩をするときは満面の笑顔を見せていた。あの表情が忘れられない。二度と彼の笑顔を見ることができないのかと思うとつらい」
2016.9.22 産経ニュース