今年1月に宮城県の女性が起こした初の国賠訴訟後、全国で同様の提訴が相次いでいるが、札幌地裁の取り組みは初めて。多様な障害に対応する法廷の在り方について、専門家は「画期的だ。他の全裁判所にも波及が期待できる」と評価する。
きっかけとなったのは、今年1月以降に全国で提訴が相次ぐ一連の裁判の中で、初めて実名で名乗り出た札幌市の小島喜久夫さん(77)の訴訟。被害者の「顔」が見える裁判となったことで大きな注目が集まり、5月の提訴では多くの障害者たちも支援に訪れた。
このため、弁護団や障害者団体「DPI北海道ブロック会議」が、札幌地裁に障害者の傍聴への配慮を要望。地裁は要望項目をほぼ受け入れ、文書で回答した。
文書によると、法廷内の全80席のうち約50席が身体、知的、聴覚、視覚各障害者、介助者、その他の配慮の必要な人向けに拡充。通訳対応や入退室などきめ細かい配慮にまで踏み込んでいる。
車いすを使う障害者らは通常の2人程度(傍聴席4席分)から10人程度(20席分)に拡大。聴覚障害者は最前列に10席で、これまで着席が必要だった手話通訳者は立って通訳できるようにした。同伴の介助者も傍聴の定員数に含めず、障害者の傍らの席を用意する。
医療機器が必要な障害者はこれまで、人工呼吸器の稼働音やアラーム音などで傍聴が困難だった。しかし、これらの音を容認した上で、たんの吸引や廊下への出入りも認めた。知的障害者用も10席を配置し、近くのモニターには法律の専門用語を使わず分かりやすい表現で映す。
障害者問題に詳しい全盲の大胡田(おおごだ)誠弁護士は「旧法を問う訴訟がすべての障害者に重要であることを裁判所が認めたことになる」と評価。熊本地裁の原告団長を務める、熊本学園大社会福祉学部教授の東俊裕弁護士も「札幌地裁は明確に文書で回答しており、全国の裁判所に影響するだろう」と期待する。
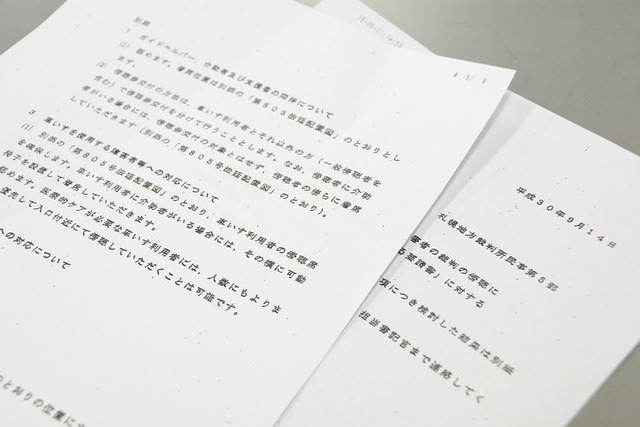

毎日新聞 2018年9月25日










