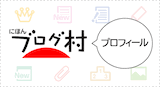正月松の内直後の三連休も今日まで。明日よりは、いよいよ2012=平成24年の日常が本格始動する。今日は、改正祝日法により、1月第2月曜に規定変えとなった「成人の日」。先の震災後初のこの日となり、特に東日本の震災被災各地にては、特別な1日となる事だろう。沖縄県など一部では、一頃社会問題化した荒れ模様の所もある様だが、多くは大人となる事の節目を謙虚に受け止め、社会人としての自覚を新たにする日である事が認識されている様だ。今日々中も、当地名古屋市内にても、式典に向かう晴れ着姿や礼装の若者達を多く見かけた。まずは、彼らの前途のつつがなきを祈りたい所です。
さて、式典と来れば、宴会に出る食材がつきものだが、曲がり角が指摘される我国の「食」の問題につき、昨日の地元紙 C新聞に記事が出ていたので、以下に引用しながらこの事を考えてみたく思う。
「食品1割ゴミに~野菜って 形なの?」
昨年末、名古屋市熱田区の市中央卸売市場は、迎春用の商品を運ぶフォーク・リフトが忙しく行き来していた。その間をすり抜けて国立K大学農学部4年、M(22歳男性、敬称略)は店舗裏へ向かう。目当ては、廃棄食材入りの段ボールだ。
「廃棄」と言っても、食べ残しと言う意味ではない。色褪せた白菜やキャベツ、熟れ過ぎたトマト・・。「傷んでいる所は取り除けば良いし、形の悪さと味は関係ない」名古屋で手に入れた野菜は宮城に持ち込み、大晦日は塩釜市、元日は名取市の集会所で若鶏の煮込みやカレー・ライスなどを振る舞った。料理は好評で、仮設(住居)に持ち帰る被災者もあった。
Mが「食」に関心を持ったのは、自宅にあった絵本「世界がもし100人の村だったら」を何気なく手にした時、高校2年生だった。(100人中の)20人は栄養が十分でなく、1人は死にそうな程です。でも15人は太り過ぎです・・。限られた食糧を、一部の裕福な国が独占し、貧しい国は飢えている。日本は裕福な部類に入るが、ニュースにては食糧自給率が40%前後まで落ちていると報じられている。必要な食糧を自分達で作り、余った分は足りない所に譲る「当たり前の社会」を創る必要がある。漠然とそう感じたMは、大学に進むと、農家で野菜栽培を学んだ。所が農家でも「当たり前」ではない実態があった。心を込めて作ったはずの作物が、ただ色形の悪さや値崩れへの心配から、捨てられていた。
「(先の震災)3.11」が起きた。避難所では食糧が不足し、特に野菜が決定的に足りなかった。ところが5月、Mがボランティアで仙台市内の市場へ行くと、ここでも廃棄食材の段ボールが「ゴミ扱い」で積まれていた。
未曾有の衝撃を受けても、日本はまだ「裕福」と言う意識から抜け出せていない。愕然とした。
食べられるのに捨てられる食糧を「食品ロス」と言う。日本では毎年、500万~900万tのロスが出る。これは、食用となる農林水産物の総量のほぼ1割になる。国際連合世界食糧計画WFPが途上国に行う1年間の援助量を上回る程の量だ。ロスを減らせば、自給率を高めるのと同じ効果がある。「すぐには変わらないが、10年後、20年後には、このおかしな社会を変えたい」と思う。
Mは昨年、知人が住み、人脈もある名古屋市にて、廃棄(予定の)食材を使ったカフェを2回開いた。地元の大学生が調理や接客を担当。店は1800人以上が訪れる盛況だった。売上は、義援金に充てた。嬉しかったのは、延べ60人のスタッフの意識が変化し始めた事だ。最初の頃は余った分を捨てようとしたが、カフェで働くにつれ「まだ、全然食べられるじゃん」と言う声があちこちで聞かれる様になった。
こう言う言葉が増えて行けば、自分が高校時代に絵本を読んだ時に感じた、世界の偏りが少しずつ取り除かれる。Mは、少しだけ形のおかしい野菜を眺めながら、そう感じている。
この記事と、若いMさんの取組みを、皆様はどうお感じになりますか?先の震災は、福島県下の原子力発電所事故と共に、東日本の多くの地域より、良質な多くの農業生産とその雇用を奪った。その再生には、最低でも10年を超えるスパンの月日が必要と言われる。更に、我々の暮らす当地東海や西日本、首都圏周辺も将来は震災の不安が付き纏う。最早これまでの、食糧の安易な廃棄は許されまい。夏場などで安全が懸念される一部の場合を除き、食せる物は活用する厳しい姿勢が生産、販売、消費の各方面に求められている様に感じるのである。その事は、我国防にも資する、食糧安全保障の鍵をも握る程の大きな意味を持つ。大きな事は申せないが、新成人の中よりも、Mさんの様に「食」の健全化に真っ向から取り組む方々が多く現れる事を、強く望みたいと思います。