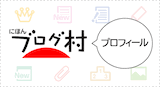さて今月の拙特集日記の東海道新幹線、貴女の地元大阪を縦横無尽に駆け巡る優秀な私鉄各線、そして拙地元の名古屋鉄道と、新幹線を別格としても相当な高速にて走行している訳ですが、その陰で地道な安全確保への取組みが行われているのは、あるいはご存じでしょう。
考えたくはないけれど、安全を語る上で、我々は決して忘れてはならない惨劇の記憶がありますね。
そう、2005=平成17年4月、兵庫尼崎のJR福知山線にての、100名を超える犠牲と、550名を超える負傷者を生じた大列車事故であります。
まだ通勤通学の混雑も収まらない9am過ぎ、尼崎へ向かっていた上り列車が大幅な速度超過の為正常な曲線通過をする事なく脱線、沿線の建物に激突して多くの死傷を生ずる結果となりました。一時は列車妨害の可能性も囁かれましたが、結局は速度違反による事が明らかとなりました。
現在の鉄道は、運転者が明白な信号無視などをした場合は数秒で自動ブレーキをかけて列車を停止させ、危険を避ける仕組みになっています。
所謂ATS=自動列車停止装置であります。但し事故当時の福知山線の装置は旧世代のもので、事故原因となった大幅な速度違反に対応したものではなかった様です。
そこで改良された自動列車停止装置では、信号が守られていても速度が著しく高い場合はやはり同様に安全確保の為に動作する仕組みの様です。
この様に安全への取り組みは、言わば「事故との闘い」でもある訳ですね。こうしたシステムは勿論東海道新幹線でも標準的に取り入れられている訳ですが、在来の一般路線であっても、この様な深刻な問題が起これば直ちに改良が加えられて来ている様です。
過日も申した様に、この6月末、私は前述の事故現場へ弔意を表しに行って参りました。場所は福知山線の尼崎とすぐ次の塚本のほぼ中間、塚本駅より徒歩で20分強の所で到着時刻は7pm頃。夏至と言えど暗くなるギリギリのタイミングでありました。件の建物には今も残る衝突痕が車窓からもはっきりと認められ、当時の凄惨さを今に留めておりました。
雨天ではありましたが、現場には今も保安の為に関係各位が詰めていらし、この方々に一礼の後現場に向かい焼香をして参った次第。
許可を得て映像も1枚収めましたので、近く拙写真帖にてお目にかけたく思います。
とに角強く感じたのは、高速化や利便性の向上は良いが、乗客乗員の生命に関わる安全が疎かにされる事があっては断じてならないと言う事でしょう。
聞いた話では、事故現場を守るJRの関係各位には、線路の品質と安全を守る保線の技術を担う方々も多くいらす様です。鉄道の礎とも言える線路の守り手として、この出来事を誰よりも重く受け止めていらっしゃる事でしょう。又、是非そうあって欲しい所です。*(新幹線)*