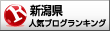村の墓場の入り口に何故か一つだけ向きの違う、村の方を向いて立つ小さなお墓がある。
きぜんばか ( 喜左ェ門墓 ) と呼ばれている。字は違うかもしれないが。

言い伝えによれば何百年か前、旅の お坊さん ? 山伏 ? タンヨ様 (宮司)だかよくわからないが喜左ェ門と言う男がこの村にたどり着き住み着いた。
村の人は田を与え、一緒に耕し、食い米だけはとれるようにしてこの男を受け入れたそうな。
実際、60代後半の人は 喜左ェ門田っぽ を耕した経験を語る。
そのころ村は6軒しか無かったが 徳衛門 の次男 長兵衛が分家に出て村は7件になった。
7軒になったので鎮守様がほしい と言うことになったそうな。
長兵衛 は屈強な男で 喜左ェ門 を道案内に頼み京都へ向かった。京都で修業を積み松尾神社から分院を許された。
この村の鎮守様地は 松尾神社。 京都の松尾神社はお酒の神様なのだそうな。
なのでこの村はみんな飲ん兵ェなのだとか。
松尾神社を建てた後はその功績が認められたのか長兵衛はあちこちから声がかかり活躍したそうな。
今も苗場山山頂近くに 「 長兵衛これを建てる 」 と掘り込んだ石碑があるそうだが、、、、
このたび道が広くなり、肩が踏まれてかわいそうなのでお墓を移動することになった。

何百年か経ってようやく村人の墓と同じ向きになった。
そのことが良いことなのか悪いことなのか??よくわからないが、粗末に扱わぬようにとお坊さんに開眼の供養をしてもらった。
とりあえず、、、何もわからない、言い伝えなんてものは又聞きの又聞き、語り継がれて何百年。
正確に伝わるなんてことは無理な話。
宗派 ? 神事なのか ???? とりあえず我々が気が済むことが大事。すがって気が済むこと、それが宗教ってものではないだろうか。

お斎の膳って訳では無くて、この時期恒例の焼肉パーティー。

村の衆だけではなくて従業員からバイト君。花の若い衆も加わって大人数だ。

途中から記憶が無いが、写真を見るとまだ明るいうちにお客さん ( 手前の酒の強い女性と奥の大男 ) は明るいうちに帰ってしまったようだ。
こちらは時差ぼけのなごりもあって早々につぶれたらしいが朝は布団の中だったので一安心。

二日酔いで、、、、今日も暑かった、でも球根植え作業は順調に進んでいる。

雨は降ったものの役に立たない水量。明日も暑そうだ。

クリックすると花農家仲間がたくさん。