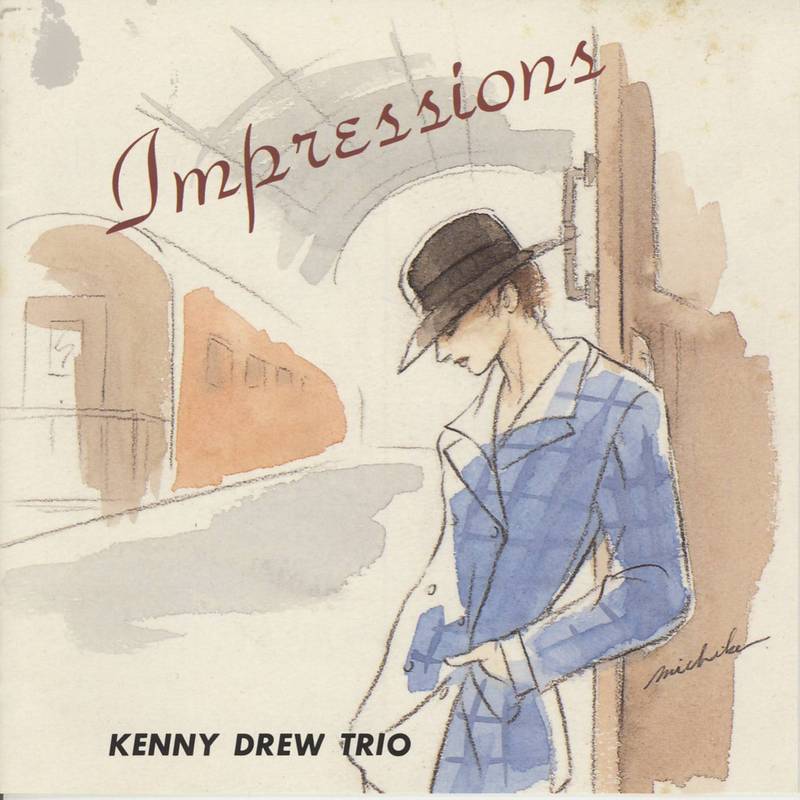●今日の一枚 11●
Stan Getz = Kenny Barron
People Time
 晩年のスタン・ゲッツをどう評価するかは、意見の分かれるところであろう。一定の評価はしつつも、ゲッツの本領は若い頃の流れるようなアドリブ演奏にあるとするのが一般的な批評家の傾向であろうか。若いゲッツのプレイにはスムーズで輝くような天才的なフレージングがあった。癌と戦いながら音楽を続けた晩年のゲッツの演奏は、もちろんすばらしいものであるが、音楽以前に、人生の物語がまとわりつき、音楽が「みえにくい」ということがあるのだろう。たとえば、村上春樹の近著『意味がなければスウィングはない』(文芸春秋)のつぎのようなことば、
晩年のスタン・ゲッツをどう評価するかは、意見の分かれるところであろう。一定の評価はしつつも、ゲッツの本領は若い頃の流れるようなアドリブ演奏にあるとするのが一般的な批評家の傾向であろうか。若いゲッツのプレイにはスムーズで輝くような天才的なフレージングがあった。癌と戦いながら音楽を続けた晩年のゲッツの演奏は、もちろんすばらしいものであるが、音楽以前に、人生の物語がまとわりつき、音楽が「みえにくい」ということがあるのだろう。たとえば、村上春樹の近著『意味がなければスウィングはない』(文芸春秋)のつぎのようなことば、
もっとも僕としては、晩年のスタン・ゲッツの演奏を聴くのは、正直なところいささかつらい。そこに滲み出てくる諦観的な響きの中に、ある種の息苦しさを感じないわけにはいかないからだ。音楽は美しく、深い。とくに最後のケニー・バロン(ピアノ)とのデュオの緊張感には、一種鬼気迫るものがある。音楽としては素晴らしい達成であると思う。彼はしっかりと地面に足をつけて、その音楽を作り出している。しかし、なんといえばいいのだろう、その音楽はあまりに多くのことを語ろうとしているように、僕には感じられる。その文体はあまりにフルであり、そのヴォイスはあまりに緊密である。あるいはいつか、そのようなゲッツの晩年の音楽を、自分の音楽として愛好するようになるかもしれない。でも今のところはまだだめだ。それは僕の耳にはあまりに生々しく響く。そこにはもう、かつてのあのイノセントな桃源郷の風景はない。そこではスタン・ゲッツという一人の人間の精神が、自らの創り出す音楽世界に限りなく肉薄している。
まったく、その通りだ。しかし、だからこそ、晩年のスタン・ゲッツは、私をひきつけて放さないのだ。その演奏はまさに、天からの啓示のように、わたしの前に現れた。それは、カーラジオだったかも知れないし、友人の部屋のレコードだったかも知れない。しかしとにかく、その全身から搾り出すような緊密で深い響きは、私の身体をしめつけて離さなかった。何だこの音は……、誰なんだこの演奏は……、といった感じだった。金縛りとは、こういう現象をいうのだろうか。
すべての演奏が素晴らしい。だが、なんといっても、DISK2の① first song が傑出している。その全身全霊をこめて創りだされたような音楽の響きに圧倒される。文字通り、命を削って創りだされた音楽のように感じられる。まさに、先の村上春樹氏の言のとおり、「あまりに生々しい」演奏である。実際、私自身この素晴らしい演奏を気軽に毎日聞く気にはなれない。けれども、ときどき身体が求めるのだ。砂漠の民がオアシスの潤いを求めるように、乾いた心が晩年のスタン・ゲッツの音楽を欲するのだ。
晩年のスタン・ゲッツ語るとき、ケニー・バロンというピアニストの存在は欠かせない。癌に犯されながらもステージに立ち続けたスタン・ゲッツを支えたのは、まさしくこのピアニストであり、彼の美しいピアノがあったからこそ、あの濃密な演奏は生まれたといってもいい。このアルバムは、そのケニー・バロンとスタン・ゲッツのデュオアルバムである。二人の緊密なかけあいが手に取るように感じられ、また身を削りながら「魂の演奏」を展開するゲッツの傍らに寄り添い、それをサポートするケニーの姿が目に浮かぶような作品である。このすばらしい作品について、ケニー・バロンは次のように語っている。
このレコーディングに収められた音楽が格別のものに思えるのは、これがスタン・ゲッツの演奏を刻んだ最後のレコーディングであるという以外に、その音楽が・・・・・ガンのもたらす苦痛にもかかわらず、あるいはそれゆえになお一層・・・・・リアルで誠実で、ピュアでビューティフルな音になっているからである。
スタン・ゲッツが死んだのは、1991年6月6日だった。