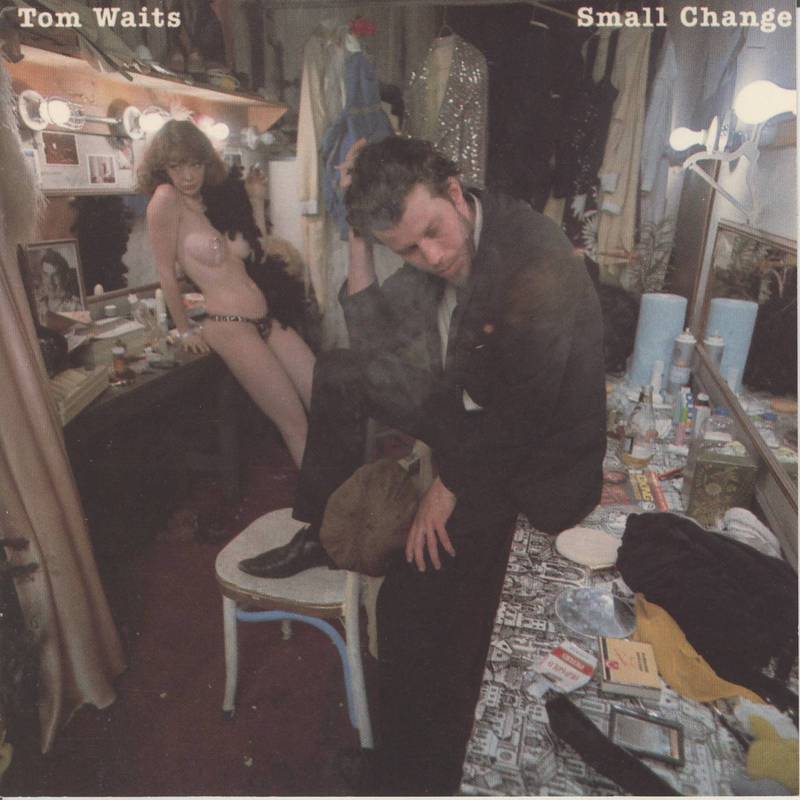●今日の一枚 159●
Sonny Rollins
Saxophone Colossus
 ソニー・ロリンズ畢生の名演にして誰もが最高傑作と疑わない1956年録音盤『サキソフォン・コロッサス』。
ソニー・ロリンズ畢生の名演にして誰もが最高傑作と疑わない1956年録音盤『サキソフォン・コロッサス』。
信じられないことだが、私はこの大名盤を所有していなかった。ジャズをおぼえたての頃、何十回と繰り返し聴き、その後も折に触れて聴いてきたのだが、LPもCDも所有していなかったのだ。貧しい学生時代、貸しレコード屋(レンタルCDショップではない)で借りたLPをカセットテープ(TDKのADだ)に録音したものをずっと聴き続けてきたのだ。後藤雅洋『新ジャズの名演・名盤』(講談社現代新書)にはこの「サキソフォン・コロッサス」について次のような話が載っている。
「……しかし、これだけその存在が喧伝されてしまうと、"通"を気取るマニアはかえって手を出しかねて、何千枚ものコレクションを誇りながら、いまだにこの一枚を買いそびれているというウソのような話もある。確かにジャズファンにとっての「サキコロ」は、いい年をしたオジサンが漱石の『坊ちゃん』を買うような気恥ずかしさがついてまわる。」
私もこのうちのひとりなのだろうか。"通"を気取っているつもりはないのだが、ブログにジャズの話題など書いているのだから、そう思われても仕方ない。ただ、実際には限られた資金でLPやCDを買うのだから、まだ聴いたことのないものを買いたかったというのが、本当のところだと思う。実は私にはそのようなアルバムが他にもいくつかあり、今回、ユニバーサル・クラシックス&ジャズからジャズ・ザ・ベスト超限定¥1,100 がでたということで、HMVのポイントも有効に使って、10枚ほど購入してみた。
さて、CDで聴くしばらくぶりの『サキソフォン・コロッサス』。マックス・ローチのドラムの音が鮮度が良い。あれっ、マックス・ローチの存在はこんなにおおきかったっけ、と思わせるほどだ。そして酌めども尽きぬロリンズのアドリブ。昨日届いたばかりのCDなのだが、もう4回も通して聴いている。たまたま妻や子が実家に行っていることもあって、大音響だ。ジャズをおぼえたての学生時代のように、音の洪水に酔いしれる。音楽を聴くことの原初的な喜びが身体から溢れ出てきそうだ。友人と飲みにいくまでまだ1時間程ある。もう一回通して聴いてみようか。