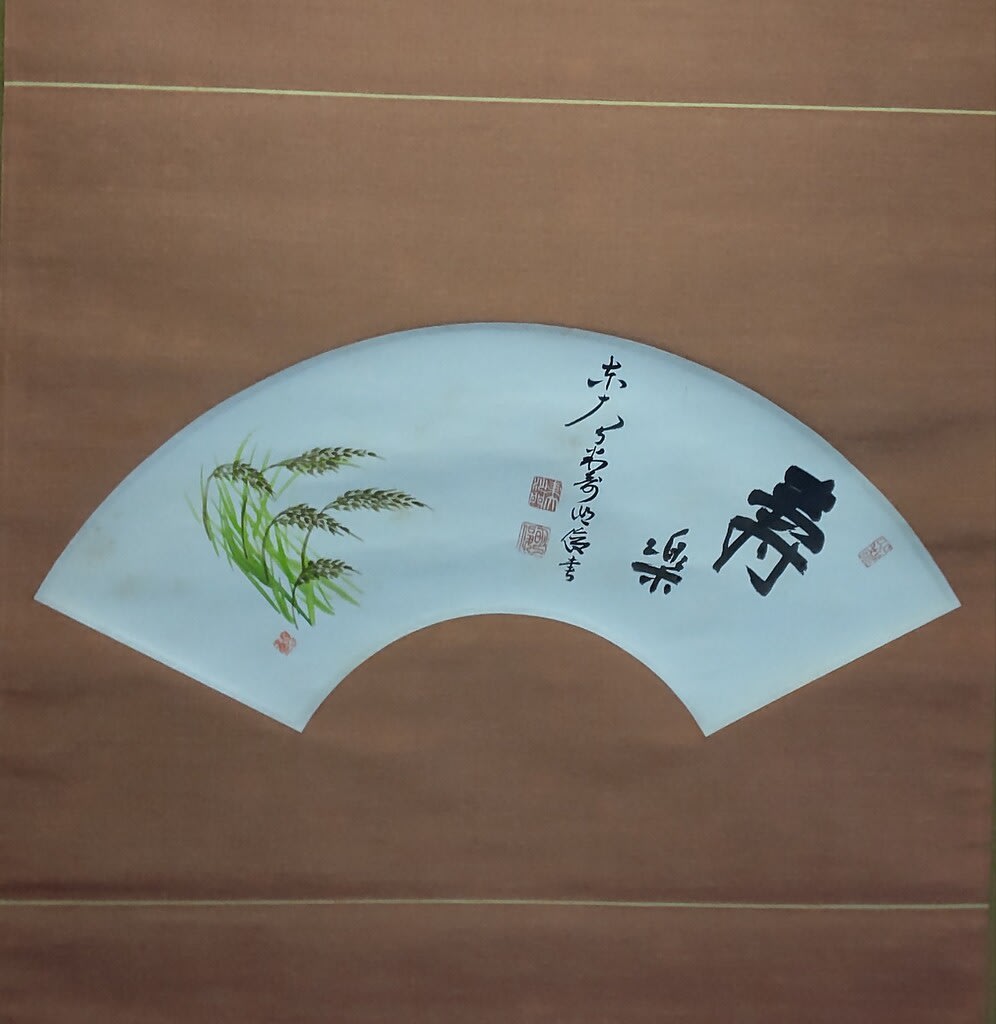七十二候「菜虫化蝶」なむしちょうとなる
青虫が紋白蝶になる頃
連綿と続き、1272回目の東大寺二月堂「修二会」も
12日はクライマックス
11人の練行衆が一回り大きな籠松明(60㎏)を伴い上堂され
 毎日新聞より
毎日新聞より深夜には閼伽井屋(若狭井)からのお水取り
お香水が十一面観音さんに奉納されましたね
奈良に春を呼ぶと言われる「修二会・お水取り」
15日に満行を迎えます
これから蝶が飛び交う季節のはずが・・・
奈良では桜が散る頃の陽気が続いていました
東京では今日14日午後二時に開花の発表が・・・
2020年と2021年に続き統計史上、最も早い記録に並び
地球温暖化による異常気象でしょうか?
さて先日のお稽古の主菓子は「糊こぼし」
日の丸盆に散らすと ウワ-ツと歓声が
日の丸盆に散らすと ウワ-ツと歓声が
ゆり根の白、安穏芋の黄色、食紅で染めた白餡
美味しくでき、喜んでいただきました


東大寺開山堂内に咲く糊こぼし椿(良弁椿)が由来とされ
南隣の四月堂の縁側にそっと水盤に浮かんでいるはず?
玄関では、いただいた煤のついた修二会の糊こぼし
ご本尊・十一面観音さんの周りを飾ざる造花の糊こぼし
せっせと練行衆が試別火でつくられたもの

清水公照 童子の扇面も

お水取り、お雛様のお稽古場も
そろそろおしまい
稽古場を華やかにしてくれたお雛様も
昨日片付けを
さて今週末には彼岸の入り、さらに利休忌と続きますね
「牡丹餅」「菜の花金団」を
作りたいと考えてますが
さて・・・
稽古場でのお楽しみに
このように季節は刻刻過ぎて
お菓子も季節で顔が変わっていきます
和菓子の成書を見ながら考えるのも愉しい
そうなんです
日本の主菓子は同じ素材でありながら
季節でどんどん変化し、又その季節になると
お目にかかります。そこが和菓子の醍醐味ですね
春の陽が降り注ぐ小庭では「金魚葉椿」が咲き出しました

遅咲きの「天津乙女椿」「源氏車椿」も蕾が膨らんでおり
待ち望んだ春、駆け足でやってきているようですね



























 2/28
2/28 平城京跡より
平城京跡より 多聞城跡より
多聞城跡より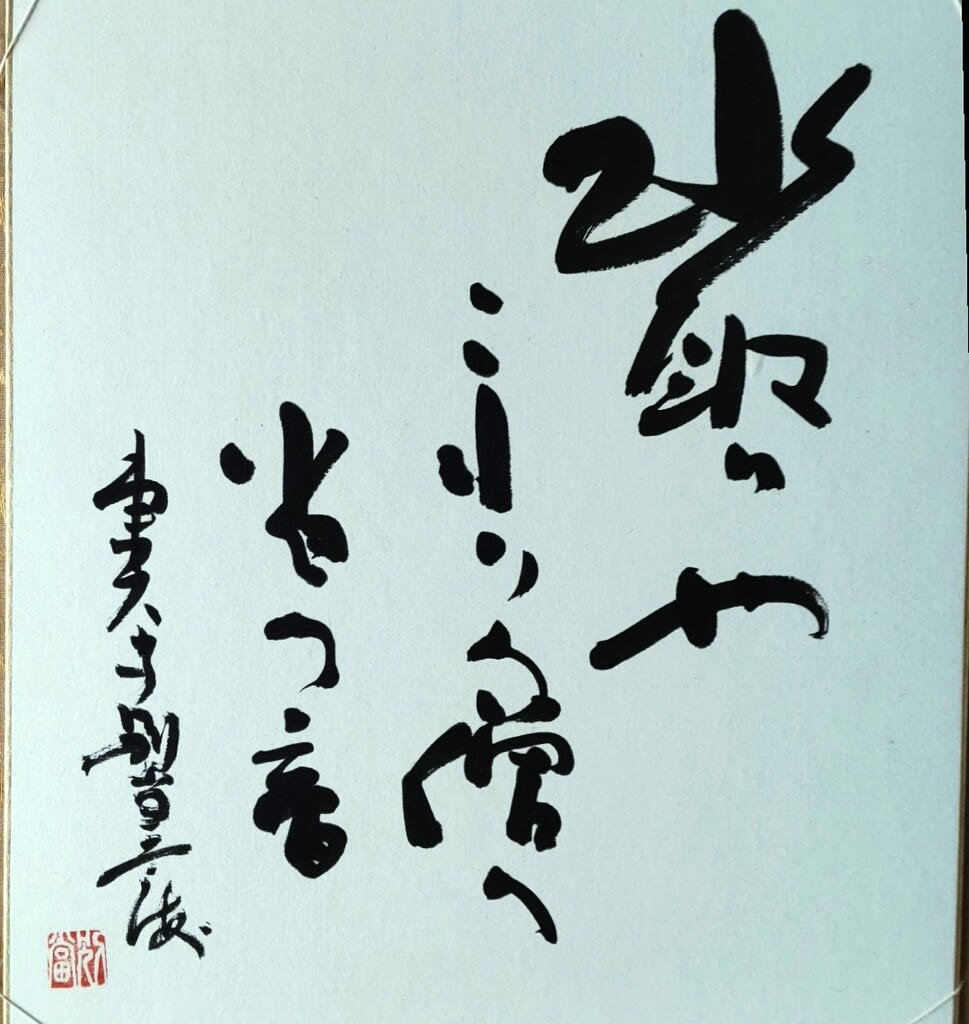
 清水公照筆
清水公照筆




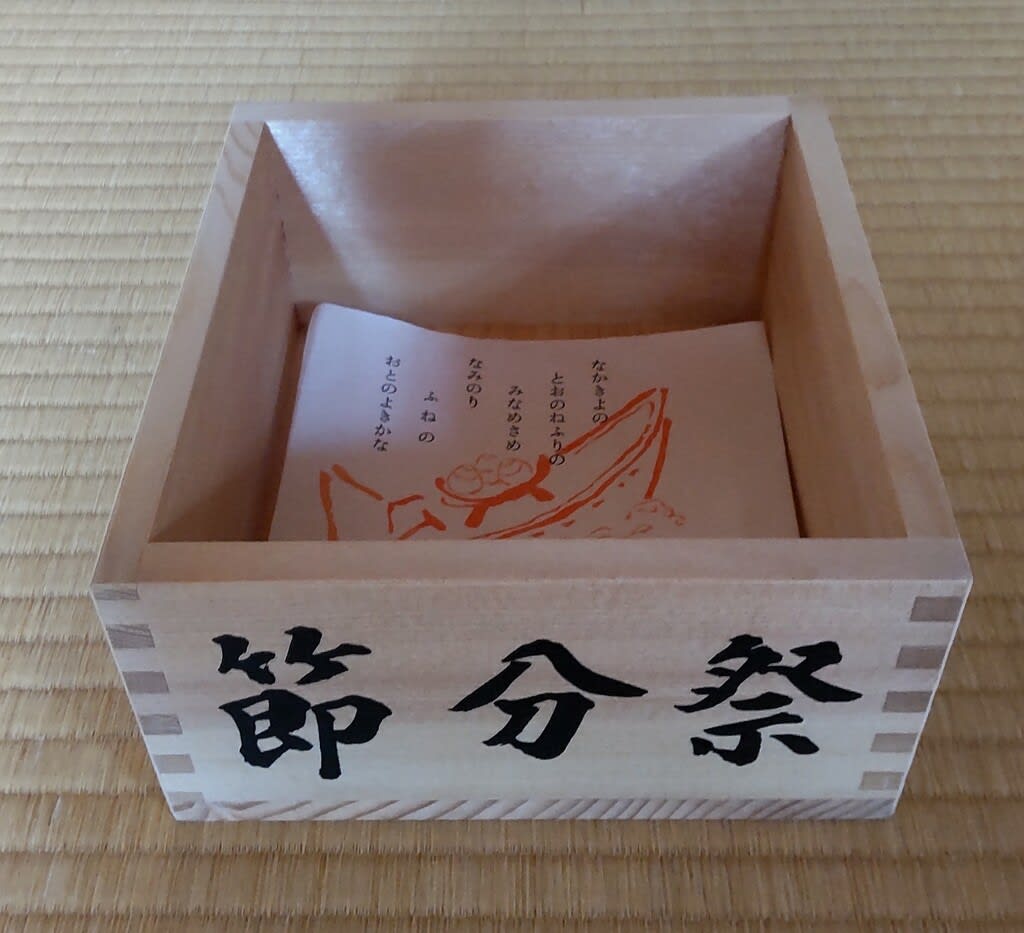





 午前11時
午前11時













 1/8
1/8 1/15
1/15









 1.1.2023
1.1.2023


















 小餅
小餅

 礼拝堂の正月堂内
礼拝堂の正月堂内 行在所跡の歌碑
行在所跡の歌碑