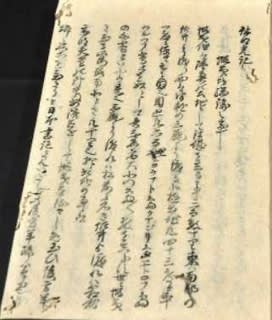VOGUE2022年4月8日
伝統的なラインタトゥーを顔に施し、先住民族のレプリゼンテーションとしてファッション業界で活躍するクアナ・チェイシングホース。北極圏の大自然と人々が直面する過酷な実態を世界に力強く発信する。
BY MASAMI YOKOYAMA


ARTURO HOLMES / MG21 / GETTY IMAGES
「私は北極圏で国立野生生物保護区の原生地域指定獲得のため尽力する国際グウィッチン青年協議会およびグウィッチン運営委員会のメンバーです。永久凍土は生命がはじまる神聖な場所。カリブー(シカ科の動物)はこの地に依存して子孫を繋ぎ、私たちの暮らしも彼らに支えられています。しかし、北極圏の氷は従来の2倍の速度で解け、異常事態に直面しています。その大きな理由が化石燃料の採掘です」
環境活動団体「The Oxgen Project」の取材に対し、こう語るモデルのクアナ・チェイシングホースは、2002年、アメリカ・アリゾナ州ナバホ族保留地ナバホ・ネイションに生まれた。サウスダコタ州のオグララ・ラコタ族と、アラスカのヘン・グウィッチン族をルーツに持ち、モデルになることを夢見た少女は、大手モデルエージェンシー・IMGと契約直後に、カルバン クライン(CALVIN KLEIN)のキャンペーンでデビューした。昨年はメキシコ版『VOGUE』のカバーを飾り、先住民族のレプリゼンテーションとして注目を集めている。
MAHSI’CHOO😭✨🙏🏽to @imgmodels @corian4 @blackberrylizz @mimiyapor for making this happen for me and for being so supportive and uplifting. This is HUGE for me as a little native girl straight out the Alaskan Bush and to see some representation of indigenous peoples. I am so honored and grateful to have been able to work with Fotografía: @inezandvinoodh
Realización: @georgecortina
Peinado: @jamespecis @_antonalexander
Maquillaje: @fulviafarolfi
Casting: @legainsbourg
Producción: @michael.gleeson / @valecollado
Earrings: Melissa Charlie @melissacharlie1254
🥰✨💛🌞
そんな彼女が、環境活動家として頭角を表したのは17歳の時。先住民族の文化を継承するアラスカ州・フェアバンクスのエフィ・コクリーン・チャーター・スクール在学中にアラスカ先住民連盟大会での講演だった。そこで気候変動対策指導者タスクフォースの復活を要求し、北極圏国立野生生物保護区を石油開発から永久に保護するため「Wilderness Designation(原生地域保護区指定)」にすることを訴えた。
永久凍土と伝統を継承するために。
2021年11月、ハリウッド・ブールバードで行われたグッチ(GUCCI)のランウェイを闊歩するモデルのクアナ・チェイシングホース。Photo: Taylor Hill / WireImage
「現在の気候変動の議論には、先住民の声、経験、そして視点が十分に含まれていません。先住民の生活は、代々受け継がれるその土地や生き物に依存しています。ですから私たちは、地球に対して深い精神的なつながりと尊敬の念を抱いています。同時に、次の世代のために伝統や生活様式を維持できるよう、責任も感じています」
そして、北極圏の環境を守るために立ち上がった経緯をこう続けた。
「私たち先住民族は何世代にもわたって、世界の不公平というトラウマに悩まされてきました。私は成長するにつれ、世界のある一部の人のエゴのしわ寄せが、私たちの動物、土地、水、そして生活様式に及んでいることを知りました。社会の仕組みを学べば学ぶほど、先住民族が経験させられる不条理に傷つき、怒りがこみ上げてきました。昨今の気候変動は、その不公平をより顕著にしています。だからこそ、私は北極圏の人のために戦おうと決心したのです。この大地は、私のアイデンティティの一部ですから」
そんな彼女は、主にアメリカにおける気候変動対策が、全く足りていないと強調する。
「環境問題は存在しない、と主張する気候変動否定論者も依然多いのも事実です。だから、気候変動の影響を軽減、もしくは逆転させる政策を成立させるよう、政治権力者にもっと働きかけなければなりません。そして、化石燃料によるエネルギーから脱却し、クリーンで持続可能なエネルギーに早急に移行する必要があります。今こそ、私たち先住民族の声を受け入れる時です」
北極圏を脅かす危険な兆候。
2022年2月、NYファッションウィーク開催期間中に行われた「No Waste」ディナーパーティーに出席した。Photo: Roy Rochlin / Getty Images for NYFW: The Shows
クアナが現在最も危惧しているのが、北極圏の急激な気温上昇だ。アメリカ海洋大気庁(NOAA)が北極圏の気象・環境を分析した「北極圏レポートカード」2021年版によると、4月の北極海の海氷量が、2010年の記録開始以来最少を記録した。また、グリーンランドでは、8月に史上初めて氷床の標高1万500フィート(約3200m)の山頂で降雨が観測されたほか、比較的長期安定していた氷床がほぼ毎年減少傾向にあることもわかった。さらに、秋季(10~12月)も記録的な暖かさとなり、北極圏の気温上昇は地球の他の地域の2倍以上の速さで進行している。加えて、流氷が減少した事で海運商業活動が盛んになり、海洋ゴミも増加。これによって、海洋哺乳類の生存が脅かされている。海洋酸性化のペースも世界で最も速いことも明らかとなり、このまま推移すれば、21世紀半ばまでに夏の北極海から氷が消える、との試算もある。
一方で、北極圏の気温上昇は、先住民の暮らしにも大きな影を落としている。北極圏の分厚い氷が薄くなったことで、海底油田の掘削が可能になり、採掘権を巡る抗争など治安悪化が問題となっているのだ。こうした現状を前に、クアナはこう訴える。
「私たち先住民は以前から気候変動の影響について危惧しており、その影響を受け続けています。以前より改革を推進する人が増えたとは思いますが、それでもまだ不十分です。気候変動は世界的な問題です。これ以上無視することはできません。私はこれからも、この地球のレガシーである北極の大地と動物、そして未来の世代を守るために戦い続けます」
Text: Masami Yokoyama Editor: Mina Oba
https://www.vogue.co.jp/change/article/models-in-challenge-quanna-chasinghorse