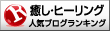東洋医学に関わっての質問した。質問とは如何にあるべきか?と改めて考えた。
昨日、東洋医学の担当教員に、「外因と内因の病の深まりの過程は違うのか?(東洋医学では違うと考えるのか?)」、「東洋医学では、病の深まりの一般的な像というものはあるのか?」と問うた。
それに対して、外因による病、それが病となっていくには内因がある。と縷縷説明いただいた。また、病の深まりとして、太陽病→少陽病→陽明病→太陰病→少陰病→厥陰病という過程があるとの説明いただいた。
それ以外にも、気血→臓腑という病の深まりや、病を気血、臓腑という観点から捉えることと陰陽として捉えることとはどう違うのか?等々、質問に対して答えていただき、それに対して、再度、質問し答えていただく。という事に凡そ1時間程もお付き合いいただいた。
にもかかわらず、かつ、後から振り返ると、質問にしっかりと答えていただいているにもかかわらず、自身のアタマの中は、スッキリと整理されたものとならず、感情的には、釈然としない思いが残った。
これはには、二重性があると思う。一つは、当初のからの自身の中での答えがあって、そこに合致しないからの釈然としない思い。であり、もう一つは、そもそもが問いたいことの像が明確でなかったから。では無いかと思う。
質問とは、この場合では、物事に関わっての自身の像が明確に描けないからの、その像を明確に描くための、相手の像との相互浸透である。
それだけに、如何に詳細に答えもらっても、当初の自身の像との一致はありえない。のだと思う。
また、そもそもが明確な像では無くても、最低限、その像を質問という形に収斂させること、明確化することを抜きにしては、例えば、分かっている部分と分からない部分くらいは明確に分けておくことをしないで質問するのでは、昨日の自身の質問の如くに、本当は何を聞きたかったのか分からない。ということになってしまい、質問する側も質問される側も、何の為の質問だったのか????となってしまう。のだと思う。
とはいえこれらのことは、質問することで明確化して来たものである。から、当初は、無茶苦茶レベルでも質問し続けることが必要である。
そうすることが、弁証術のソクラテス的な段階の始まりなのだ。と思う。
昨日、東洋医学の担当教員に、「外因と内因の病の深まりの過程は違うのか?(東洋医学では違うと考えるのか?)」、「東洋医学では、病の深まりの一般的な像というものはあるのか?」と問うた。
それに対して、外因による病、それが病となっていくには内因がある。と縷縷説明いただいた。また、病の深まりとして、太陽病→少陽病→陽明病→太陰病→少陰病→厥陰病という過程があるとの説明いただいた。
それ以外にも、気血→臓腑という病の深まりや、病を気血、臓腑という観点から捉えることと陰陽として捉えることとはどう違うのか?等々、質問に対して答えていただき、それに対して、再度、質問し答えていただく。という事に凡そ1時間程もお付き合いいただいた。
にもかかわらず、かつ、後から振り返ると、質問にしっかりと答えていただいているにもかかわらず、自身のアタマの中は、スッキリと整理されたものとならず、感情的には、釈然としない思いが残った。
これはには、二重性があると思う。一つは、当初のからの自身の中での答えがあって、そこに合致しないからの釈然としない思い。であり、もう一つは、そもそもが問いたいことの像が明確でなかったから。では無いかと思う。
質問とは、この場合では、物事に関わっての自身の像が明確に描けないからの、その像を明確に描くための、相手の像との相互浸透である。
それだけに、如何に詳細に答えもらっても、当初の自身の像との一致はありえない。のだと思う。
また、そもそもが明確な像では無くても、最低限、その像を質問という形に収斂させること、明確化することを抜きにしては、例えば、分かっている部分と分からない部分くらいは明確に分けておくことをしないで質問するのでは、昨日の自身の質問の如くに、本当は何を聞きたかったのか分からない。ということになってしまい、質問する側も質問される側も、何の為の質問だったのか????となってしまう。のだと思う。
とはいえこれらのことは、質問することで明確化して来たものである。から、当初は、無茶苦茶レベルでも質問し続けることが必要である。
そうすることが、弁証術のソクラテス的な段階の始まりなのだ。と思う。