私たちはこの広い宇宙で唯一の存在なのか?
近年観測体制が飛躍的に向上して、今まで観測できなかった太陽系外の惑星の存在が分かるようになってきた。1995年以降系外惑星が次々と発見され2014年現在で1800個を超えている。それにしても初めて確認されたのが1995年と言うと私が40歳のころ。学生時代の知識は全く役に立たない訳です。
太陽系でも火星、そして木星の衛星であるエウロバ、ガニメデ、土星の衛星タイタンとエンケラドスには、生命に必要な3条件である液体の水、有機物、熱源が揃っているものもある。高度に進化した知的生命体はあり得ないにしても、地球の生命体とは全く違った生命体の存在の可能性は否定できない。
縣さんは国立天文台勤務の天文学者。
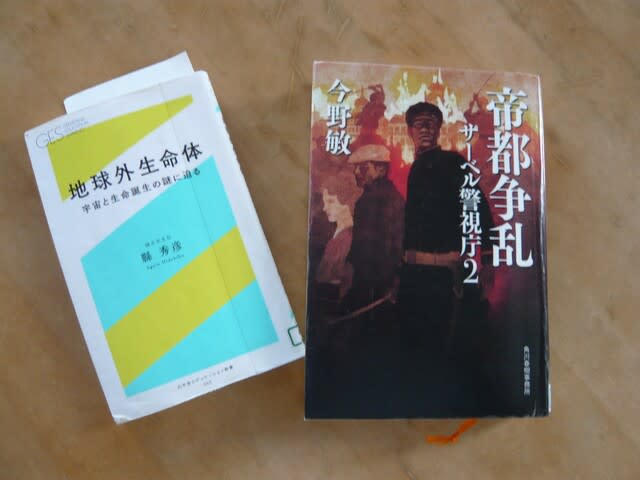
ビックバンによる宇宙誕生以来138億年、天の川銀河は120億年前に出来、太陽系が出来て46億年、地球に生命が誕生して以来38~40億年、まさに天文学的数字が並びますが、私たち人類が誕生して以来の年数は、宇宙的に見ればほんの一瞬。ましてや人類が星の外部と交信できるような知性を持ったのはほんのここ100年ちょっと。あと何年人類が繫栄しているか分からないですが、人類が何時の日にか滅びるまでの時間は宇宙の時間と比べればほんの瞬きする間でしかないだろう。同じ時代に知的生命体と出会う確率はほとんどないかも。
それでも系外惑星が次々と見つかっていくと、いわゆる生命を宿しえるハピタブルゾーンに存在する惑星はそんなにまれな存在ではないとわかってきた。天の川銀河だけで一千億個を超える恒星があり、少なからない恒星に惑星が存在し、中には太陽との距離が地球のように生命存在に丁度良くて(ハピタブルゾーンに含まれている)、大きさも地球と同じ程度の岩石惑星も一定の確率で存在するのだろう。
そこからどうやって生命が誕生したかは、偶然の賜物かこれまた奇跡的な確率の結果なのだろうが、地球だけが奇跡の星とは言い難いのではと思える。生命のもととなる有機物は多分地球だけで生成されたわけでなく小惑星なり彗星の中で出来たものが地球に降り注いでもたらされたかも。生命さえも宇宙から来たのではという説もあるのですが、これは今のところ単なる仮説の域を出ず証明されていない。しかし地球が誕生して5~6億年で、原始地球の過酷な環境下で有機物ができ、そこから生命が誕生したと言うのは時間的に短すぎると言われると、宇宙飛来説にも一定の説得力を感じてしまう。
時間軸の問題で我々が知的生命体と実際にコンタクトを取るのは難しいかもしれないが、何らかの地球外生命体を見つけるかもしれないのは大いにあり得るみたいです。
地球外生命を探すために今ではいろいろなプロジェクトが動き出していて、惑星探査も進んでいる。ハヤブサもその一翼を担っています。
宇宙の成り立ちから最新の研究までが分かりやすく書いてあり、知的好奇心を満足させる本でした。
あまり面白いので似たような新書をもう1冊。
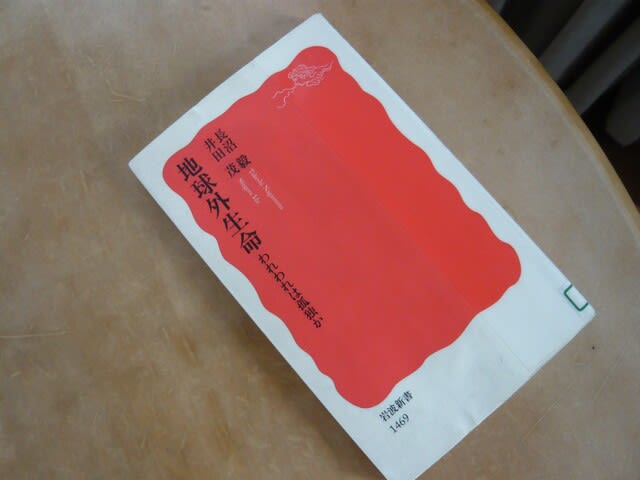
この本は生物学者それも極限生物とか微生物が専門の長沼毅と天文学者で惑星形成論が専門の井戸茂の共著。内容としては被るところが多いのですが、微妙に観点とか論点とかが異なっていて、縣さんの本がいい意味での予備知識となって興味持って読むことができました。
ちなみに天文学者は条件さえそろえば生命は発生すると考え、確率から考えると地球外生命は存在すると信じがちで、生物学者は生命の発生と進化は奇跡の連続で地球外生命に懐疑的とか。
確かに約6千万年前に小惑星が地球に衝突しなければ、恐竜が絶滅することはなく哺乳類にとってかわられることもなかったかも。そうなると恐竜はどういう形に進化していったのだろう…知的に進化した恐竜が出てくるのだろうか?今の人類が誕生した進化の道筋は天変地異による大きな環境変動などの偶然に左右されたことの結果とすると、やっぱり我々人類は唯一無二の存在なのか。
我々はこの宇宙で孤独な存在なのか、興味は尽きません。
一緒に写っているのは今野敏のサーベル警視庁シリーズの「帝都争乱」。シリーズ2冊目ですが、今回は日露戦争終結時の講和条約に対する不満からの日比谷焼き討ち事件が舞台。日露戦争で我慢を強いられた民衆の不満が爆発した事件ですが、その裏には桂首相と山形有朋、伊藤博文の暗闘と玄洋社と黒龍会が絡んだという筋立て。警視庁の鳥居部長以下警官たちが振り回され何とか乗り切っていくのだが、裏主人公は女学校の用務員こと新鮮組だった斎藤一。確か浅田次郎の「一刀齊夢録」でも主人公でしたが、戊辰戦争後警視庁に勤め西南戦争にも従軍し、明治半ばまで存命だったのは事実だったみたいですが、想像力が膨らむ存在です。
近年観測体制が飛躍的に向上して、今まで観測できなかった太陽系外の惑星の存在が分かるようになってきた。1995年以降系外惑星が次々と発見され2014年現在で1800個を超えている。それにしても初めて確認されたのが1995年と言うと私が40歳のころ。学生時代の知識は全く役に立たない訳です。
太陽系でも火星、そして木星の衛星であるエウロバ、ガニメデ、土星の衛星タイタンとエンケラドスには、生命に必要な3条件である液体の水、有機物、熱源が揃っているものもある。高度に進化した知的生命体はあり得ないにしても、地球の生命体とは全く違った生命体の存在の可能性は否定できない。
縣さんは国立天文台勤務の天文学者。
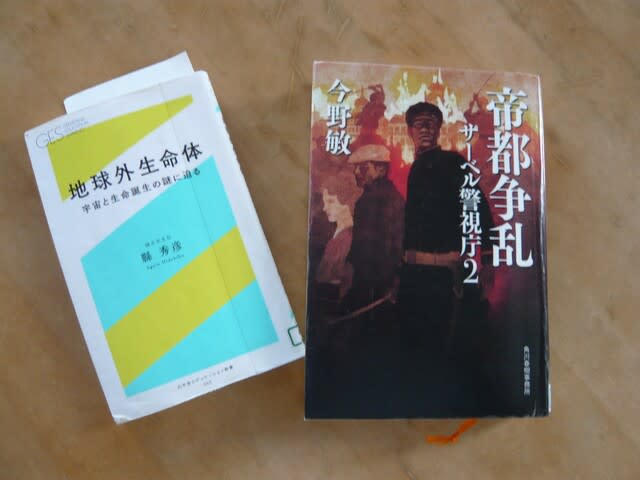
ビックバンによる宇宙誕生以来138億年、天の川銀河は120億年前に出来、太陽系が出来て46億年、地球に生命が誕生して以来38~40億年、まさに天文学的数字が並びますが、私たち人類が誕生して以来の年数は、宇宙的に見ればほんの一瞬。ましてや人類が星の外部と交信できるような知性を持ったのはほんのここ100年ちょっと。あと何年人類が繫栄しているか分からないですが、人類が何時の日にか滅びるまでの時間は宇宙の時間と比べればほんの瞬きする間でしかないだろう。同じ時代に知的生命体と出会う確率はほとんどないかも。
それでも系外惑星が次々と見つかっていくと、いわゆる生命を宿しえるハピタブルゾーンに存在する惑星はそんなにまれな存在ではないとわかってきた。天の川銀河だけで一千億個を超える恒星があり、少なからない恒星に惑星が存在し、中には太陽との距離が地球のように生命存在に丁度良くて(ハピタブルゾーンに含まれている)、大きさも地球と同じ程度の岩石惑星も一定の確率で存在するのだろう。
そこからどうやって生命が誕生したかは、偶然の賜物かこれまた奇跡的な確率の結果なのだろうが、地球だけが奇跡の星とは言い難いのではと思える。生命のもととなる有機物は多分地球だけで生成されたわけでなく小惑星なり彗星の中で出来たものが地球に降り注いでもたらされたかも。生命さえも宇宙から来たのではという説もあるのですが、これは今のところ単なる仮説の域を出ず証明されていない。しかし地球が誕生して5~6億年で、原始地球の過酷な環境下で有機物ができ、そこから生命が誕生したと言うのは時間的に短すぎると言われると、宇宙飛来説にも一定の説得力を感じてしまう。
時間軸の問題で我々が知的生命体と実際にコンタクトを取るのは難しいかもしれないが、何らかの地球外生命体を見つけるかもしれないのは大いにあり得るみたいです。
地球外生命を探すために今ではいろいろなプロジェクトが動き出していて、惑星探査も進んでいる。ハヤブサもその一翼を担っています。
宇宙の成り立ちから最新の研究までが分かりやすく書いてあり、知的好奇心を満足させる本でした。
あまり面白いので似たような新書をもう1冊。
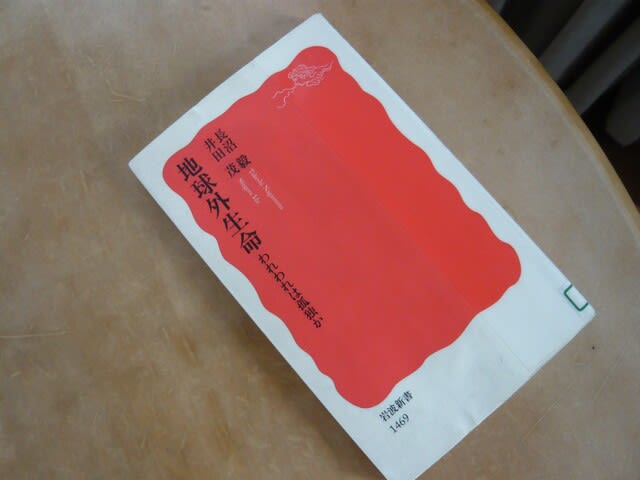
この本は生物学者それも極限生物とか微生物が専門の長沼毅と天文学者で惑星形成論が専門の井戸茂の共著。内容としては被るところが多いのですが、微妙に観点とか論点とかが異なっていて、縣さんの本がいい意味での予備知識となって興味持って読むことができました。
ちなみに天文学者は条件さえそろえば生命は発生すると考え、確率から考えると地球外生命は存在すると信じがちで、生物学者は生命の発生と進化は奇跡の連続で地球外生命に懐疑的とか。
確かに約6千万年前に小惑星が地球に衝突しなければ、恐竜が絶滅することはなく哺乳類にとってかわられることもなかったかも。そうなると恐竜はどういう形に進化していったのだろう…知的に進化した恐竜が出てくるのだろうか?今の人類が誕生した進化の道筋は天変地異による大きな環境変動などの偶然に左右されたことの結果とすると、やっぱり我々人類は唯一無二の存在なのか。
我々はこの宇宙で孤独な存在なのか、興味は尽きません。
一緒に写っているのは今野敏のサーベル警視庁シリーズの「帝都争乱」。シリーズ2冊目ですが、今回は日露戦争終結時の講和条約に対する不満からの日比谷焼き討ち事件が舞台。日露戦争で我慢を強いられた民衆の不満が爆発した事件ですが、その裏には桂首相と山形有朋、伊藤博文の暗闘と玄洋社と黒龍会が絡んだという筋立て。警視庁の鳥居部長以下警官たちが振り回され何とか乗り切っていくのだが、裏主人公は女学校の用務員こと新鮮組だった斎藤一。確か浅田次郎の「一刀齊夢録」でも主人公でしたが、戊辰戦争後警視庁に勤め西南戦争にも従軍し、明治半ばまで存命だったのは事実だったみたいですが、想像力が膨らむ存在です。


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます