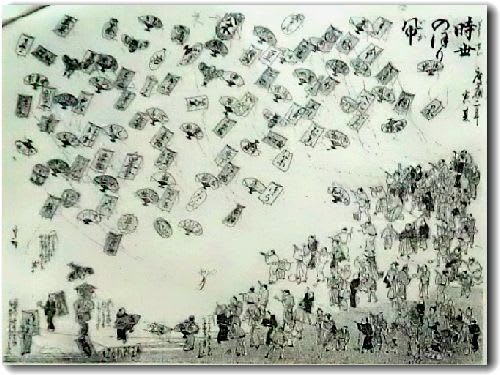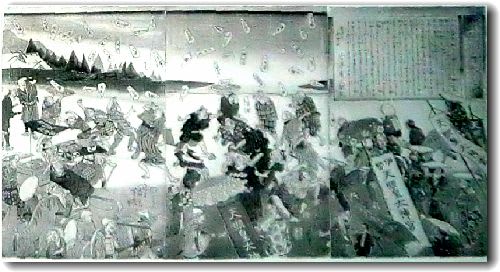しろあと歴史館秋季特別展 「幕末 京都をめぐる雄藩と高槻」 の
歴史ウォーク2回目 「幕末の京都を歩く」に参加してきました。
今日のコースは、大宮駅前にて13時に集合してから
蛤御門まで行ってきました。
大宮駅前→①京都高槻藩跡→六角獄舎跡 (平野国臣外三十数名終焉之址) →②武信稲荷神社→③若狭小浜藩邸跡→④京都東・西町奉行所跡→⑤二条城西門前→板倉重→・重宗屋敷跡→⑥二条城前→福井藩邸跡→京都守護職正門→⑨京都守護職屋敷跡 (京都府庁)→水戸藩邸跡→⑩蛤御門(○の数字は、しろあと歴史館の学芸員さんから説明があった場所の順番です。)

阪急京都線大宮駅前
ここで集合して13時にスタートしました。

少し北に向かって歩いていくと
京都高槻藩邸跡は洛中小学校になってました。
高槻から
この京都高槻藩邸までは8時間かけてきていたそうです。
高槻藩は
近隣の諸大名とともに御所や二条城を守る火消役を担当する藩士の詰め所として使用され、戊辰戦争時の在京藩士は400名あまりいたそうです。

六角獄舎跡
元々六角通りにあった獄舎が宝永5年(1708)に当地へ移りました。
『ここは、幕末の平野国臣(ひらのくにおみ)が処刑された殉難の地でもあり、「六角獄舎」があったところで、安政の大獄以後は多くの政治犯が収容されたので会所ともいった。
国臣は、もと福岡藩士で尊王攘夷運動に参加して脱藩し、生野の乱に挙兵して捕らえられ、元治元年(1864)1月17日ここに収容された。
ところが同年7月19日長州藩兵の入京に端を発した「禁門の変 (蛤御門の変)」によって、京都市中の大半が兵火に見舞われ、その翌日火勢が「六角獄舎」に迫るや、爆死は獄中の尊皇攘夷派の志士たちを斬った。
この時斬られた一人が国臣である。
この難にあったものは国臣のほか三十数名にのぼった。
なお、当地は、宝暦4年(1754)に医師「山脇東洋」がわが国で初めて死体解剖を行った所とも言われ、付近には記念碑も建っている。 京都市より』

ここは 武信稲荷神社 です。
平安時代初期の貞観元年(859)、藤原良相(ふじわらのよしみ)によって創建されました。
その後、藤原武信という人が厚く信仰したことから 「武信稲荷」 と称されたそうです。

境内には、大きな一本のエノキが立っていました。
幕府に追われていた坂本龍馬は「京都で生きている」という証にエノキに「龍」の一文字を彫ったという、龍馬と妻おりょうの逸話が伝わっているそうです。(^^♪
~~~~~~~ 今日の誕生花 日比谷花壇より ~~~~~~~
花名 : ルクリア 花言葉 : 優雅な人
紅茶の産地として知られるアッサム地方原産の常緑低木です。その甘く上品な香りから日本では、ニオイザクラ、カオリザクラと呼ばれています。
歴史ウォーク2回目 「幕末の京都を歩く」に参加してきました。
今日のコースは、大宮駅前にて13時に集合してから
蛤御門まで行ってきました。
大宮駅前→①京都高槻藩跡→六角獄舎跡 (平野国臣外三十数名終焉之址) →②武信稲荷神社→③若狭小浜藩邸跡→④京都東・西町奉行所跡→⑤二条城西門前→板倉重→・重宗屋敷跡→⑥二条城前→福井藩邸跡→京都守護職正門→⑨京都守護職屋敷跡 (京都府庁)→水戸藩邸跡→⑩蛤御門(○の数字は、しろあと歴史館の学芸員さんから説明があった場所の順番です。)

阪急京都線大宮駅前
ここで集合して13時にスタートしました。

少し北に向かって歩いていくと
京都高槻藩邸跡は洛中小学校になってました。
高槻から
この京都高槻藩邸までは8時間かけてきていたそうです。
高槻藩は
近隣の諸大名とともに御所や二条城を守る火消役を担当する藩士の詰め所として使用され、戊辰戦争時の在京藩士は400名あまりいたそうです。

六角獄舎跡
元々六角通りにあった獄舎が宝永5年(1708)に当地へ移りました。
『ここは、幕末の平野国臣(ひらのくにおみ)が処刑された殉難の地でもあり、「六角獄舎」があったところで、安政の大獄以後は多くの政治犯が収容されたので会所ともいった。
国臣は、もと福岡藩士で尊王攘夷運動に参加して脱藩し、生野の乱に挙兵して捕らえられ、元治元年(1864)1月17日ここに収容された。
ところが同年7月19日長州藩兵の入京に端を発した「禁門の変 (蛤御門の変)」によって、京都市中の大半が兵火に見舞われ、その翌日火勢が「六角獄舎」に迫るや、爆死は獄中の尊皇攘夷派の志士たちを斬った。
この時斬られた一人が国臣である。
この難にあったものは国臣のほか三十数名にのぼった。
なお、当地は、宝暦4年(1754)に医師「山脇東洋」がわが国で初めて死体解剖を行った所とも言われ、付近には記念碑も建っている。 京都市より』

ここは 武信稲荷神社 です。
平安時代初期の貞観元年(859)、藤原良相(ふじわらのよしみ)によって創建されました。
その後、藤原武信という人が厚く信仰したことから 「武信稲荷」 と称されたそうです。

境内には、大きな一本のエノキが立っていました。
幕府に追われていた坂本龍馬は「京都で生きている」という証にエノキに「龍」の一文字を彫ったという、龍馬と妻おりょうの逸話が伝わっているそうです。(^^♪
~~~~~~~ 今日の誕生花 日比谷花壇より ~~~~~~~
花名 : ルクリア 花言葉 : 優雅な人
紅茶の産地として知られるアッサム地方原産の常緑低木です。その甘く上品な香りから日本では、ニオイザクラ、カオリザクラと呼ばれています。