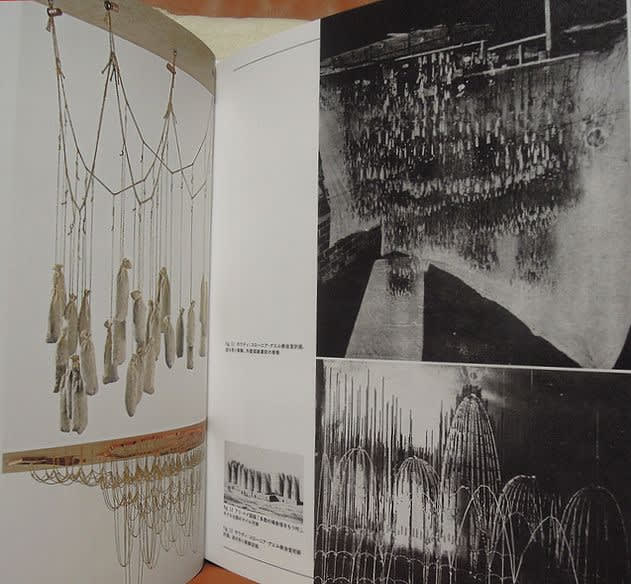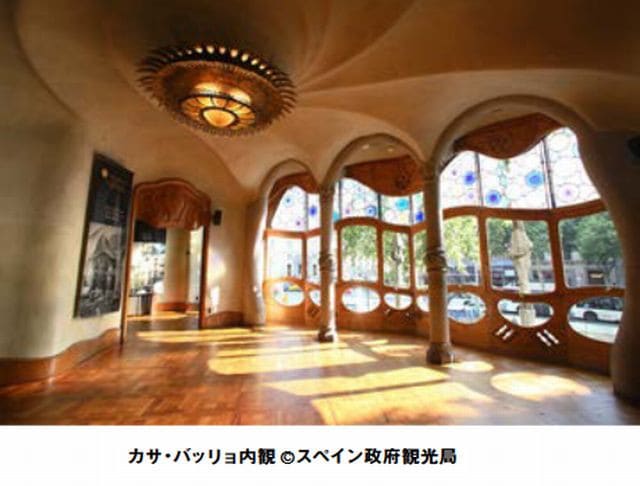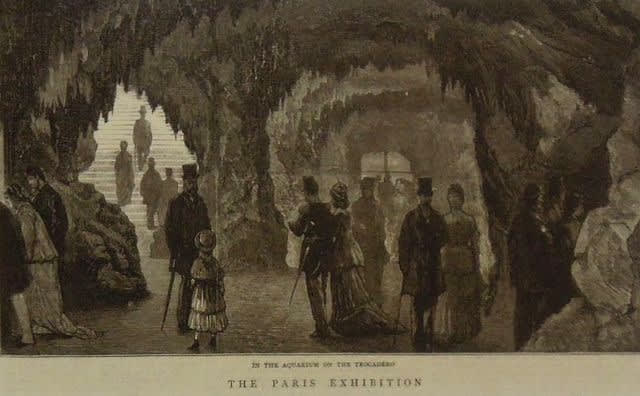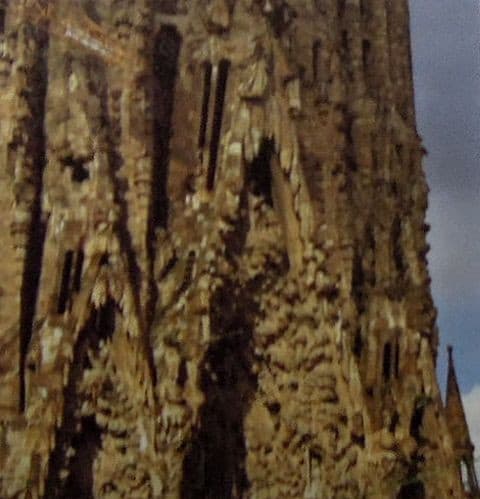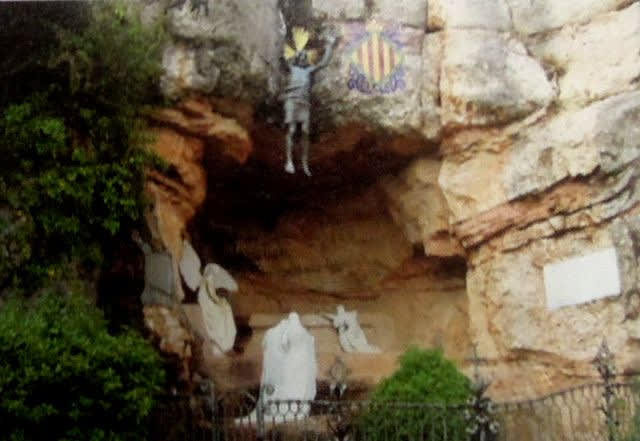昨日の記事から移行して再投稿します。
今年は、ブログ訪問で紅葉を楽しませて頂きましたが
家近くに気付かずにいた紅葉がありました・・・それは

ご近所の塀にへばりついて伸びているのは
「ヘンリーヅタ」の蔓(つる)だと思います。
今まで、家の壁をよじ登って蔓を伸ばしているのは見ていましたが、紅葉しているのを見るのは初めてです。
科・属名:ブドウ科・ツタ属
原産地:中国

遠くから見ていても、きれいに紅葉していたので
近くまでいって撮らせて頂きました。(^^ゞ

ヘンリーヅタは
春に赤色の葉になると、赤紫色から深い緑色へと変わり
秋に低温にあうと、赤く紅葉するそうです。
~~~~~~~~~~~~~~
追記

蔦で思い出すのは「甲子園の蔦」ですが
気になったので調べると・・・
甲子園の蔦の種類は2つでした。
メインは「ナツヅタ」と呼ばれるブドウ科の蔦で
秋には赤く色づき、冬は葉を落とします。
日当たりの良くない場所には
日陰に強いウコギ科の「キヅタ」が使われていました。
今年は、ブログ訪問で紅葉を楽しませて頂きましたが
家近くに気付かずにいた紅葉がありました・・・それは

ご近所の塀にへばりついて伸びているのは
「ヘンリーヅタ」の蔓(つる)だと思います。
今まで、家の壁をよじ登って蔓を伸ばしているのは見ていましたが、紅葉しているのを見るのは初めてです。
科・属名:ブドウ科・ツタ属
原産地:中国

遠くから見ていても、きれいに紅葉していたので
近くまでいって撮らせて頂きました。(^^ゞ

ヘンリーヅタは
春に赤色の葉になると、赤紫色から深い緑色へと変わり
秋に低温にあうと、赤く紅葉するそうです。
~~~~~~~~~~~~~~
追記

蔦で思い出すのは「甲子園の蔦」ですが
気になったので調べると・・・
甲子園の蔦の種類は2つでした。
メインは「ナツヅタ」と呼ばれるブドウ科の蔦で
秋には赤く色づき、冬は葉を落とします。
日当たりの良くない場所には
日陰に強いウコギ科の「キヅタ」が使われていました。