先日2月4日は、立春。
愛媛県内の中学2年生は、少年式を行った。
全国的には、そんな行事はしていない学校もあるだろうし、
立志式という名前で行っているところもある。(親友のいる鹿児島県など)
お祝いに、全校生徒や教職員に紅白饅頭が配られた。
紅と白のシンプルな饅頭に「祝」という文字が焼き印されている。

今年、異動してきた隣の同僚がひとくち食べて、
「おいしー」と大絶賛。
甘すぎず、もたれない、なつかしい味とのこと。
私もパクッ。
この饅頭のおいしさが、ふるさと二名津にある田村菓子舗のものであることは、すぐにわかった。
すぐにわかるほど昔と変わらない味だから。
「未来に残したいふるさとの味」
食べながら、疑問に思ったことがある。
「お祝いごとに、なぜ紅白饅頭なんだろう?」
すぐに調べてみた。
すると「気になるジョ」というブログからおもしろい事実がわかった。
『まんじゅうを漢字で書くと、「饅頭!」
なんで頭が付くの?
この理由というのに、驚愕の事実が!!(;゜ロ゜ノ)ノ
饅頭の漢字の由来というのが、三国志と言われる時代にまで、さかのぼります。
天下の名軍師、諸葛孔明が南蛮を平定し、成都へ帰るおりに瀘水という河にさしかかると、
瀘水が荒れ狂っていて渡れない。
孔明がこの地方の人々になぜ河が荒れるのかと問うと、
「河の荒神と、戦いで死んだ将兵たちの祟りだ」という。
鎮めるには人身御供(ひとみごくう、身代わり)として、
7749人の首と黒い牛、白い羊を河の神に供えて祭をしなければならないと教えられる。
それを聞いた孔明は、人身御供の悪習を絶ち切ろうと考え、
料理番を呼び寄せ、小麦粉を練って人の頭の形に似せて作らせ、
その中に人肉の代わりに牛や羊の肉を詰めた饅頭を河の神に捧げ祭を行った。
すると翌朝、荒れ狂っていた河は鎮り返り渡ることができたという。
人間の頭に見せて作った?Σ(||゜Д゜)ヒィ~!!
だから、頭という漢字が・・・
こういうエピソードがあり、中国の饅頭がお供え物と、定着したようで。。。
実際に今でも中国では、桃饅頭という桃の形をした饅頭が、祝いの席では欠かせません!
また、日本では饅頭に入ってる『あん』の素となる小豆には、
•邪気を祓う力
•厄除けの力
が、備わってると言われてます。
日本では、中国から伝わったことと、小豆の厄除けがまじりあい、
饅頭じたいが縁起物の意味を、持っているのです!』
なるほど、そう言えば、我が家でも小豆を神様のお供え物としている。
実におもしろい。
では、次の疑問。
「お祝いごとの紅白の色は、どのような意味なのか?」
続く。
愛媛県内の中学2年生は、少年式を行った。
全国的には、そんな行事はしていない学校もあるだろうし、
立志式という名前で行っているところもある。(親友のいる鹿児島県など)
お祝いに、全校生徒や教職員に紅白饅頭が配られた。
紅と白のシンプルな饅頭に「祝」という文字が焼き印されている。

今年、異動してきた隣の同僚がひとくち食べて、
「おいしー」と大絶賛。
甘すぎず、もたれない、なつかしい味とのこと。
私もパクッ。
この饅頭のおいしさが、ふるさと二名津にある田村菓子舗のものであることは、すぐにわかった。
すぐにわかるほど昔と変わらない味だから。
「未来に残したいふるさとの味」
食べながら、疑問に思ったことがある。
「お祝いごとに、なぜ紅白饅頭なんだろう?」
すぐに調べてみた。
すると「気になるジョ」というブログからおもしろい事実がわかった。
『まんじゅうを漢字で書くと、「饅頭!」
なんで頭が付くの?
この理由というのに、驚愕の事実が!!(;゜ロ゜ノ)ノ
饅頭の漢字の由来というのが、三国志と言われる時代にまで、さかのぼります。
天下の名軍師、諸葛孔明が南蛮を平定し、成都へ帰るおりに瀘水という河にさしかかると、
瀘水が荒れ狂っていて渡れない。
孔明がこの地方の人々になぜ河が荒れるのかと問うと、
「河の荒神と、戦いで死んだ将兵たちの祟りだ」という。
鎮めるには人身御供(ひとみごくう、身代わり)として、
7749人の首と黒い牛、白い羊を河の神に供えて祭をしなければならないと教えられる。
それを聞いた孔明は、人身御供の悪習を絶ち切ろうと考え、
料理番を呼び寄せ、小麦粉を練って人の頭の形に似せて作らせ、
その中に人肉の代わりに牛や羊の肉を詰めた饅頭を河の神に捧げ祭を行った。
すると翌朝、荒れ狂っていた河は鎮り返り渡ることができたという。
人間の頭に見せて作った?Σ(||゜Д゜)ヒィ~!!
だから、頭という漢字が・・・
こういうエピソードがあり、中国の饅頭がお供え物と、定着したようで。。。
実際に今でも中国では、桃饅頭という桃の形をした饅頭が、祝いの席では欠かせません!
また、日本では饅頭に入ってる『あん』の素となる小豆には、
•邪気を祓う力
•厄除けの力
が、備わってると言われてます。
日本では、中国から伝わったことと、小豆の厄除けがまじりあい、
饅頭じたいが縁起物の意味を、持っているのです!』
なるほど、そう言えば、我が家でも小豆を神様のお供え物としている。
実におもしろい。
では、次の疑問。
「お祝いごとの紅白の色は、どのような意味なのか?」
続く。












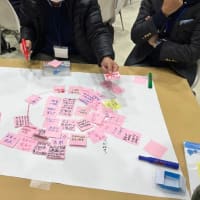








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます