昨夜 「チャコちゅうぶ」で縁(えにし)の話をしていて 戦前のわが家の縁側外交(笑)を思い出した
縁側は東南の両親の寝室からぐるりと南側にあった 縁側の幅は一間幅、部屋は障子で仕切り外側はガラス戸、そのうえ夜は雨戸を繰る。太陽のある昼間はガラス戸を締めると冬は温室
こういう縁側は正確には廊下というらしい
庭木戸をあけて人がそこに集まってくる 屋根にひさしがあるので大雨でない限り縁側に座っていても濡れない、植木屋さんが庭木の剪定が終わるとその縁側でお弁当を食べたり、お茶をする
母はその時庭の花や木の手入れをプロに教わる
富山の薬売りが来る
薬の効用を母は聞く
人糞を取りに農家の人が来る
母は野菜の知識をそこで教わる
輪島の漆屋さんが来る
母は諸国の様子や漆の手入れ法を聞く
魚屋さんが来て台所に行って刺身をつくったあと、縁側に来て茶をすすっている、
母は魚と海の話などを聞いている
母はそういう外商の人たちに対して、巻きずしを作ってもてなしたり、パウンドケーキを作って当時としては珍しい紅茶など出して喜ばれていた
その縁側で仕入れた情報を母は遊びに来た近くの人たちに伝えていた
またそこでは若いお母さんが、子育てでの疑問を周りの先輩たちに質問し、みんなで知恵を出し合っていた
先日建築家に聞いたけど いま建築法では縁側は作れないようになったという。みんなの「たまり場」が無くなった。玄関からの人の出入りは「よそ行き顔、他人行儀」家の作りから人とのコミニュケーションが広がらない世の中になったのだと、あらためて思う












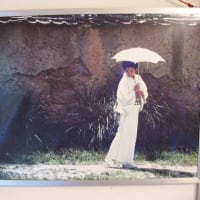












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます