
悉皆屋(しっかいや)この職業も激減した
どんな仕事をするのかと言えば
着物や襦袢、羽織り、帯など形あるものをほどく
端縫い(はぬい)解いた着物など元の反物に戻すことを目的として縫う(8枚のパーツがまた一反の布に変身)
水道の水を勢いよく流しながら布を浸し、洗濯板のようなお化けの板に布を置いて亀の子たわしでごしごし洗う(この場面を初めて見たとき、腰を抜かさんばかりに驚いた)
とにかく水で洗う(これで大体の汚れは取れる)
汚れがひどいときは固形石鹸を使い、せっけんで洗いそのあとたわしでさらに洗う、この場合は40度のお湯を使用
流れる水で洗う洗う(うんと昔は川の流れを利用していた、だから川のそばに悉皆屋はある)
ゆるく回る乾燥機で洗った布の水分を取る(うんと昔は手絞り)
伸子針を使って布を干す(うんと昔は天日干し、今は空気が汚れているので外は使わない。これは都会の場合)
布を張った後薄く伸ばしたフノリを刷毛で引いて完全に乾くのを待つ(フノリは海藻、仕上げの役を持つ)
伸子から布を外し検品し折り目正しくたたむ(アイロンの必要があればここで蒸気アイロンをつかう)
紬や小紋、無地などはほとんどこの作業、紋付ものに関して、また金銀の糸を使ったものに関しては、順序は一緒だけど、もう少し注意深く細かく微調整をしながら作業を進めていく
着物の洗濯は本来このように進めていた
何年間かエルメスの洋服しか着ない時があり(着物より安いし素材がいいと思った)エルメス用のクリーニング屋さんに洗濯をお願いしていた。とにかく丁寧で新品同様に仕上げてくれるので(そのおかげか30年も前の洋服を今も着ている、いまは新品は買っていない)着物もお願いできませんか?と聞いたら「着物はそのご専門のところにお出しください。私どもはその技術を持ち合わせていません」と断られた。やはり餅屋は餅屋
ついでに言えばその昔パリでデイオールの作業場を取材したとき仕上げは洋服をスターンに着せて、そこにアイロンを当てていた。日本のように洋服も平面におきアイロンをするという習慣はないらしかった。そのエルメス専門のクリーニング屋さんにその話をしたら、それに近い作業だと言っていた。和服と洋服違って当然とつくづく思う
そう悉皆屋さんのはなし、こういう手仕事の悉皆屋さんはお蕎麦屋さんと同じ数だけ各町内にあったのは昭和50年代までか。シーズンが終わるとバサッと預けて、当面の季節物を持ってきてくれる。なんと箪笥の役目をしていてくれたのだった。
いまも一軒の悉皆屋さんとお付き合いをしているが、後継者はいない。今のうちに多くのことを学んでおこうと思うこのごろ
#悉皆屋 #エルメスの洋服 #中谷比佐子 #チャ子ちゃん先生 #ふのり #後継者 #亀の子たわし #固形石鹸 #伸子張り












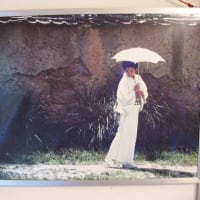












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます