
毎日着物を着続けることでわかったことは半襟にも四季があるということ
1月東雲 2月ふくれ織 3月明雲 4月平織り、一越ちりめん。綸子 5月楊柳 6月絽縮緬 7月段絽または麻 8月平絽か麻 9月絽麻、絽縮緬、段絽 楊柳
10月一越ちりめん。綸子 11月古代縮緬、ふくれ織 12月うづら縮緬 ふくれ織
塩瀬羽二重礼装用、夏の礼装は塩瀬絽
すごいことに半襟やさんはこの全ての品揃えができていた
私ごとだが私の母はいただきもののお返しには必ず半襟と決めていた
四季折々の半襟は半襟ダンスに収まっていた
そして町の半襟やさんによく半襟を購入に行っていた
着物に興味がなかったがその小間物屋さんは色んな色の下着や腰紐が店にあって
みているだけで楽しい。だから必ずついていく。
それに大人たちが楽しそうに着物の話をするのを聞いているのも面白かった
後に高校生になり街に出るとその店にクラスメートと立ち寄ってお茶をご馳走になり
ちょっと鼻たかだった
ともあれ半襟の種類の多さ
その他に色襟刺繍衿とある
白襟がよそ行きの半襟なので半襟をもらうことは嬉しかったに違いない
その母の習慣が私にも身にしみていて
おとなになってお返しには半衿と決めていた
呉服屋の前身が半襟やさんだったという店は多い
刺繍の半襟など今の値段だと10万円から20万円くらいのものはザラだったようだ
着物の色が地味な時代だったので半襟を派手にするのもおしゃれだったのであろう
時代時代に流行りがあり刺繍の半襟を買うのに行列したという話も聞いた
今でも「ゑり」とつく呉服屋さんは半襟やさんが前身という店が多いと思う
半襟は着物と同じ織り方ではなく半襟を織る機織り機が別にある
もともとは反物を切って半襟にしていたらしいけど
ジャガードが輸入されて半襟だけを織る機も開発された
半襟は真ん中が切れるようになっていて独特の織り方だ
10枚とか50枚とか一度に同じ種類のものが出来上がるので
だんだん素材の種類もすくなくなり
半襟を季節で楽しむことも今では無くなってしまった
あるとき
実家が半襟を織っていたという友人の家が仕事をやめるのでと大量に半襟が送られてきた
500枚はあったけど
いろんな素材のものがありあっという間にみんなの手に渡り喜んでもらえた
その時の「ふくれ織」の半襟がまだ手元にあるが本当に素晴らしい
その半襟をつけると胸元がふっくらとして
冬の寒さもこの半襟一枚が首の周りを暖かくする
半襟の種類が減ったことで着物の着方もまた変わったように思う
#半襟 #ジャガード #半襟の四季
1月東雲 2月ふくれ織 3月明雲 4月平織り、一越ちりめん。綸子 5月楊柳 6月絽縮緬 7月段絽または麻 8月平絽か麻 9月絽麻、絽縮緬、段絽 楊柳
10月一越ちりめん。綸子 11月古代縮緬、ふくれ織 12月うづら縮緬 ふくれ織
塩瀬羽二重礼装用、夏の礼装は塩瀬絽
すごいことに半襟やさんはこの全ての品揃えができていた
私ごとだが私の母はいただきもののお返しには必ず半襟と決めていた
四季折々の半襟は半襟ダンスに収まっていた
そして町の半襟やさんによく半襟を購入に行っていた
着物に興味がなかったがその小間物屋さんは色んな色の下着や腰紐が店にあって
みているだけで楽しい。だから必ずついていく。
それに大人たちが楽しそうに着物の話をするのを聞いているのも面白かった
後に高校生になり街に出るとその店にクラスメートと立ち寄ってお茶をご馳走になり
ちょっと鼻たかだった
ともあれ半襟の種類の多さ
その他に色襟刺繍衿とある
白襟がよそ行きの半襟なので半襟をもらうことは嬉しかったに違いない
その母の習慣が私にも身にしみていて
おとなになってお返しには半衿と決めていた
呉服屋の前身が半襟やさんだったという店は多い
刺繍の半襟など今の値段だと10万円から20万円くらいのものはザラだったようだ
着物の色が地味な時代だったので半襟を派手にするのもおしゃれだったのであろう
時代時代に流行りがあり刺繍の半襟を買うのに行列したという話も聞いた
今でも「ゑり」とつく呉服屋さんは半襟やさんが前身という店が多いと思う
半襟は着物と同じ織り方ではなく半襟を織る機織り機が別にある
もともとは反物を切って半襟にしていたらしいけど
ジャガードが輸入されて半襟だけを織る機も開発された
半襟は真ん中が切れるようになっていて独特の織り方だ
10枚とか50枚とか一度に同じ種類のものが出来上がるので
だんだん素材の種類もすくなくなり
半襟を季節で楽しむことも今では無くなってしまった
あるとき
実家が半襟を織っていたという友人の家が仕事をやめるのでと大量に半襟が送られてきた
500枚はあったけど
いろんな素材のものがありあっという間にみんなの手に渡り喜んでもらえた
その時の「ふくれ織」の半襟がまだ手元にあるが本当に素晴らしい
その半襟をつけると胸元がふっくらとして
冬の寒さもこの半襟一枚が首の周りを暖かくする
半襟の種類が減ったことで着物の着方もまた変わったように思う
#半襟 #ジャガード #半襟の四季












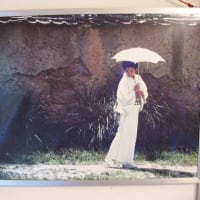












※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます