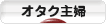『竹光侍 1』 画:松本大洋 原作:永福一成 小学館
ビックコミックスピリッツに連載中で、単行本は既に6巻まで出ています。
1巻目は2006年12月に発売。
やっと1巻読みました。思った通り面白い

松本大洋の単行本が書店に並ぶようになって、
大友克洋が好きな自分はずーっと気になってました。
中身も知らず大友の二番煎じかなと、読んでませんでした。
そのうち、結構平積み頻度が高いなとさらに気になり、
でも、読みたいモノが家に平積みになってる身。値段の高い単行本は
中身が自分の好みだとわかっていれば買えますが、それ以外はなかなか・・・
映画『ピンポン』を観て原作が松本大洋と知り、友人に借りて読みました。
大友とは違うじゃん
妙な迫力がいいなぁ、こんなのだったんだ。
もっと早くに読めばよかったと思ったものでした。
そして『鉄コン筋クリート』劇場版アニメ
話がながくなるので止めますが『アキラ』劇場版アニメ以来の衝撃でした。
『鉄コン』公開の頃に『竹光侍』の単行本が出たんですよ。
信濃から出てきて、江戸の長屋に住み着いた浪人、瀬能宗一郎。
剣の達人のようだが、どこか風変わりなこの男と
長屋の隣に住む子供、勘吉との珍妙な日々を描く時代劇です。
話はシュールで面白いし、瀬能のキャラにも惹かれますが、
松本独特の画にメチャメチャ惹かれます。
実にアーティスティック
画の省略の仕方、画面構成、コマの中のアップや引きのもっていき方、
上手いなぁ、惚れぼれする。
渋谷のBOOK・OFでやっと見つけた1巻。家の近所のBOOK・OFには影も形も無し。
2巻目以降はいつ見つかるかなぁ
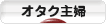
下の娘の長い長い夏休みもやっと終了。
誰もいない家をガガーッと掃除して、最後に子供部屋に着手しようとした途端
帰ってきました。
そうか始業式だけだから弁当食べたら帰ってくるのか・・・
ヤツ等の部屋はゴミ溜め状態のまま。
(てか、自分で掃除しろよ!)
こんな娘に育てたのは自分です。
学校が本格始動すると気になるのはやはりインフルエンザ。
毎朝検温とかマスク着用で登校とか
細かい指導プリントがそれぞれの学校から山と来てますが、
当の本人たちは屁の河童で登校してます。
(手はマメに洗えよ!)
これから文化祭シーズンに突入します。
通ってる学校以外の学校にたくさんの生徒が出入りします。
どうなることやら。
上の娘は喘息持ち。新型インフルになったら悪化するのかちょっと心配。
学校と予備校2つ行ってるので、あいつが一番感染率高いような・・・
そんなこと言って、あちこちフラフラ出歩いてる自分が一番ヤバイかもぉ。
だって、観たいモノがいっぱいあるんだもん。
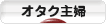
2回目観てきました。
本日は撮影用カメラが数台入ってました。
開演時間前から出演者がステージ上でウロウロするはずだと思い
早めに席に着きましたが、今日は時間が過ぎてもなかなか出て来ず、
最初に指揮者のティム・マーレーが、オドオドしながら遠慮がちに出てきて
上手のテーブル席に着いてました。(撮影してたからかな?)
初日は2階席、今回S席1階前方で観て感じたのは
この作品には会場が広すぎでは?です。
ロンドンでのリンバリー・シアター・スタジオは
どれ位のキャパかは知りませんが、小ホールだと聞いています。
先日、東京芸術劇場小ホールで野田秀樹の『ザ・ダイバー』を観たばかりなので
余計に感じるのかもしれません。狭い空間で濃密な世界感を共有する
というのが合っている気がしました。(1階後方はガラ空きでした )
)
前回は『危険な関係』以来のアダム・クーパーだったので
必死に彼と字幕を追ってましたが、
今日は落ち着いて演劇を観るぞの気分で行ってきました。
表情もよく見える席で、メイクがパンフに載ってる物より4人とも自然かな。
悪魔の最終形態メイクが歌舞伎っぽかった(目の周り隈取ってる!)
気がするのですがどうだったかな。
王女様はもう少しおてもやんでもよかったような。
あんまりバカっぽくなく綺麗でした。
カメラが入っていたのでこれもそのためかな?
たぶんアップも撮ってるはずですよね。
やはり、ゼナイダとマシューは動きもいいし、コミカル加減も絶品ですね。
クーパー&ゼナイダの組み合わせは映像で見ています。
ブラザーズ・クエイ監督、タケット振付の『デュエット』と
同じブラザーズ・クエイ監督の『サンドマン』です。
婚約者と兵士が踊るシーンはそれを思い出させるほど美しいです。
この舞台、キーパーソンはウィルかなぁ。
クーパーの優柔不断な情けない兵士も、
ゼナイダの高い技術の踊りに支えられた演技性も、マシューの怪演ぷりも
ウィルの声、動き、そして場に合った上手いストーリーテーリングで
全て引き立っているような気がしました。
クーパーの動きは初日よりは滑らかに身のこなしが軽くなったように感じました。
しかしです。あの婚約者と踊る美しいシーンもっとイケるだろう!
後ろに回した手に神経いってないぞぉ
それにしてもストラヴィンスキーは眠いです。
起伏のない単調な音を聴いていると、
ちょっと気を抜くと眠りそうになってる自分に気が付きます
次は東京千秋楽です。
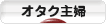
2009年9月11日(金) 開演19:30 新国立劇場 中劇場
自分はアダム・クーパーのファンであります。
御多分に洩れず、スワンとストレンジャーにヤラレタ口です。
でも、稼ぎと英語力が無いため、ロンドンまで彼の公演を観に行くことはできません。
その分彼の出ている数少ない映像をせっせと集め、
ひたすら日本に来るのを待ってる情けないヤツです。
そして久々の日本での公演。楽しみにしてました。
しかしです。イヤな予感が現実になったような・・・
2004年に彼がウィル・タケット演出・振付でやると知った時CD買いました。
「兵士の物語(英語版)」で、台詞もしっかり入っている物です。
指揮はニコラス・ウォード、ノーザン室内管弦楽団、1995年11月録音となってます。
聴いてみると眠い・・・ストラヴィンスキーは「春の祭典」ですら眠い自分です。
何が面白いんだかさっぱりだったし、内容知らなきゃダメだな、でした。
『兵士の物語』は日本でもいろんな方が舞台化してます。
観に行ったことはありませんが、以前NHKで放送した田中泯のを一度見ました。
暗い場面が延々と続き(前衛チックなのはダメだぁ)
その時も半分寝てしまって内容はよくわからないままでした。
今回、これじゃ楽しめないぞと絵本を買いました。
「兵士の物語」 中原佑介:文 山本容子:絵 評論社
山本容子の作品は以前から好きで小さな画集を何冊か持ってます。
副都心線新宿三丁目駅にあるパブリックアートの人です。
好きな版画家の絵で読めるなんて、こりゃいいやです。
元はロシアの民話だったんですね。
1918年にラミュの台本とストラヴィンスキーの作曲で音楽劇になったと。
絵本の最後に「幸せは一つだけで十分なのよね。」とあり、
これがこの話の教訓なんだなと理解して当日臨みました。
アダム・クーパーがバレエ界から離れてだいぶ経ちます。
彼は自分のやりたかった事を一生懸命やってるようでした。
でも、『オズの魔法使い』の画像を見た時は「ややっ!!なんかドンくさいぞ。」と思い、
来日直前までやってた『シャル・ウィ・ダンス?』のチャコットの評を読んでも
パッとしません。何より舞台の動画を見た時、
自分には輝きが感じられず「動いてこれか!」といささかショックでした。
まさかこのまま『兵士の物語』を持ってくるのか!?
練習してから来るはずだから、そんなことないよね。
初日を観て、さすがみなさんバレエ界出身。身のこなしがきれいです。
現役のゼナイダは出産して1年あまりとは思えません。
その中で一番生彩に欠けていたのがクーパーじゃないですか!
『オン・ユア・トゥズ』の時からみると声の上達ぶりは目を見張るものがあります。
せっせとミュージカルの舞台をこなしてきただけはあります。
舞台人の声の出し方になってると思いました。
しかし、動きは・・・あのキレは?艶っぽさは?どこ?
ウィルの方がいい感じだったぞ!!
会場は満席というわけにはいかず、1階後方は空席が目立ちました。
前方もちらほら空いてました。
公演終了後のロビーで、本日公演舞台写真付きのチケットを売ってました。
まだまだ席は残ってるということか。
今日はマチネ公演の後にダンマガのスペシャルイベントがありますね。
自分はあと2回行きます。
その間に観たいクーパーが観れるといいな。
〈キャスト〉
兵士:アダム・クーパー
ストーリーテラー:ウィル・ケンプ
悪魔:マシュー・ハート
王女:ゼナイダ・ヤノウスキー
指揮:ティム・マーレー
演奏:ソルジャーズ・アンサンブル・オーケストラ
演出・振付:ウィル・タケット
美術・衣装:レズ・ブラザーストン
照明:ニール・オースティン
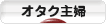
ええっ
これで終わりですか
原作ファンとしてはなんとも・・・
まあ、これだと誰でも見れるわかりやすい終わり方か。
10代の女の子が一度は経験する同性への憧れ。
世の中へ出て行く前の、女子校特有の守られてる中での擬似恋愛。
疑惑も嫉妬もあるけど本当の恋愛とは違う
どこか透明感のある同性との恋。
原作には無い、雪の夜中にあーちゃんとふみちゃんが通ってた
小学校を見に行くという展開であれれ!?終わりか?と思ってたら
スルッとまとめて終了・・・杉本先輩の留学騒動もうわさが飛び交って終わり。
原作4巻ではこの後ふみちゃんがあーちゃんに告って
次はどうなるんだぁ!ってとこです。
なんとも物足りない・・・
この話でドロドロの展開になるとは思わないし、それはいやだけど
でも、これで終わり?
コミックでの話が進んだら2期やってくださいよぉ。
ユリモノつながりで来期から始まる
『ささめきこと』
10/7(水) 深夜26:20~ テレビ東京
これはどうなんだろう。
原作本は4巻まで出ています。うち1、2巻持ってますが、まだ読んでません。
下の娘が読んでて、「どうよ」と聞いたら「ビミョー」との返事。
「青い花」の方が面白いと言ってました。
アニメが始まる前には読もうと思ってます。

2009年9月9日(水) 開演14:00 東京芸術劇場 小ホール
8月20日からやってる『ザ・ダイバー』本日の昼公演、並んで当日券取りました。
朝10時前に着いた時点で6人ぐらい並んでました。
12時半頃には70人ほど並んだそうで、会場のお姉さんが
「当日券は50枚でぇす。後ろの方はキャンセル待ちの整理券になりまぁす。」
と言ってました。その後も1時の発売まで列が延びてました。
芸劇の大ホールと中ホールは行ったことがありますが
小ホールは初めて入りました。地下にこんな空間があるんですねぇ。
可動式のホールで舞台によって形が変わるんですね。
広くない空間なので臨場感がいっぱいです。
出演の4人も達者な人たちで、若い俳優が野田の舞台に出て、
野田の要望に応えようと必死という感じが無くそれぞれが立ってました。
野田の舞台はなかなかチケットが取れないので久々でした。
(『パイパー』も取れなかったのでWOWOWで見ました)
夢の遊眠社から変わらない畳み掛けるセリフの応酬を堪能してきました。
個人的には、舞台の中で般若の絵を描いた袋をかぶるシーン。
あれは袋の上から面を着けて欲しかったかもです。
あの絵はちょっとププッと思ってしまった。
舞台の流れ上、一々面を着けるのは大変ですから無理なのかも・・・。
WOWOWで放送したロンドンバージョンは録画してあるので
今度ゆっくり見てみます。
〈作・演出〉 野田秀樹
〈出演〉 大竹しのぶ、渡辺いっけい、北村有起哉、野田秀樹
〈美術〉 堀尾幸男
〈照明〉 小川幾雄
〈作調〉 田中傅左衛門
〈音響〉 高都幸男
〈舞台監督〉 瀧原寿子
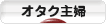

「敷居の住人1、2」 志村貴子 著 エンターブレイン
「青い花」のアニメ化で話題になってる志村貴子の
初連載作品の単行本の新装版です。
旧版の全7巻からサイズが大きくなり全6巻に変更です。
カバー画は新たに書き下ろしです。
「青い花」は女の子の話ですがこちらはミドリ頭の男の子が主人公。
髪をミドリに染めた中学生・本田千暁。
授業をさぼるタイプだが不良とも言い難い。
そんな彼がゲーセンで、つかめない美少女・キクチナナコと出会う。
男友達むーちゃん、彼とそっくりな顔の兼田先生登場と、
10代のウダウダモヤモヤな生活を描く。
2巻からは、登場人物に、メガネっ娘の中嶋くるみや
キツめの美少女・近藤ゆかもからんできて、
事態はますます混乱のストーリー。
けだるいけど、新鮮な10代の日常のお話。
(コミック・ビームHPより)
「青い花」とは画が全然違います。デザインチックというか、同人ぽいというか
これはこれで、完成度高いです。
ここから「青い花」に変わっていったんですから、
ある意味スゴイなと・・・どちらも好きです。
話の雰囲気は「青い花」を内包してますね。今一つこなれてませんが
それぞれ内にいろんなものを抱えながら、
先の見えない未来に向かって取りあえず生きてるぞといったところか。
2巻でやっと携帯が出てくるんですが、
12年前の中学生は普通、携帯持ってたりしませんもんね。
時代を感じてしまった。

「恋の話がしたい」 ヤマシタトモコ 著 東京漫画社
BLコーナーに平積みしてたBL本です。
う~ん、これ男女にしたら普通の恋愛マンガですよね。
自分がそっちの人間だと自覚してしまうと
ノンケには手を出せない、言ってもどうせ拒否られるとウダウダ・・・
思いもかけず受け入れられると、それはそれでグズグズ・・・
もどかしさ前面で・・・なんかどうよ。
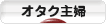
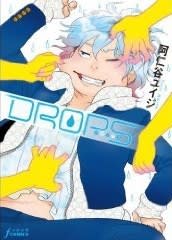
「DOROPS」 阿仁谷ユイジ 著 太田出版
朝日新聞で紹介してたので読んでみました。
「マンガ・エロティクス・エフ」に連載してただけに、ややHですが
話は両親のいない5人姉弟のそれぞれの恋愛模様ってとこですか。
5人が5人クセのある設定でなかなか読ませてくれます。
それにしても、上手くない画のおかげで、なんとも肉感的な感じが伝わります。

「やさぐれぱんだとうさぎとかめ」 山賊 著 小学館文庫
前回より面白かったです。
生瀬勝久も堺雅人も好きですが、
やはり「やさぐれぱんだ」はDVDよりコミックだなぁ。

「イルゲネス 03」 原作:桑原水菜×画:石据カチル マッグガーデン
今回は学園ドラマくささではなく、
軍学校にいながら反政府組織発足なんて、学園紛争モノかよ的な展開。
島裏への頻繁な潜入で実態を徐々に理解していくフォン。
次号ではフォンの秘密も明らかになるそうで、買っちゃうんだろうなぁ。

「娚の一生」 西炯子 著 小学館
西炯子作品は4、5年まえの作品あたりから少しだけ読んでました。
上手くなりましたねぇ、画も話も。
画は好みだけどちょっと読みにくいなぁと思ってたんですが
これはなかなかいい。主人公、魅力的です。
そして、おじさん好きにはたまらないかも。
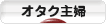
2009年9月5日(土) 14:30開演 東京芸術劇場大ホール
アンドレイ・アニハーノフ客演指揮者就任記念演奏会
スペイン奇想曲 op.34 リムスキー=コルサコフ
バレエ組曲「白鳥の湖」 op.20より(アニハーノフ編纂) チャイコフスキー
交響曲第2番 ホ短調 op.27 ラフマニノフ
アンコール 「くるみ割り人形」より 第2幕パ・ド・ドゥ チャイコフスキー
チャイコの「白鳥」を聴きに行ってきました。
東京ニューシティ管弦楽団といえば、レニ国のバレエオケで何度か聴いていますが、
バレエオケというのは最少人数のオケで、そしてたぶん
その楽団の2番手、3番手の方々が演奏していると思われ
(バレエがメインですからしょうがない・・・)
お前らプロか!と言いたくなる時が多々あります。
東京ニューシティ管弦楽団もまさにそれなんですが
客演指揮者を招いてのオケ公演ですから、
いくらなんでもキッチリやってくれるかと・・・やっぱりバレエオケでした。
バレエ公演で聴くよりはマトモでしたが
金管楽器がダメだぁ~肝心なところで音外す・・・
ハープはすいません下手です。
木管は頑張ってました。第1ヴァイオリンも聴かせてくれました。
珍しかったのが「白鳥の湖」の5曲目に演奏した第3幕No.19aパ・ド・ドゥです。
これはバレエ公演では何度か聴いていますが
持っている全曲CDには入っていません。
プログラムに載っていた解説に
“初演後、プリマのアンナ・ソペシチャンスカヤのためにチャイコフスキーが
新たに書き加えたもので、楽譜が長らく失われていましたが、
1953年にヴァイオリンのためのレペティトゥア(リハーサル用伴奏譜)と
第2ヴァリアシオンのパートが発見され、
そこからソ連の作曲家V・シェバーリンが復元した。”とありました。
なるほど~、それであまり聴いたこと無かったんですね。勉強になりました。
ラフマニノフはノーカットの全曲演奏、大曲でした。
ブラボーの声が飛んでました。
残念ながら空席が目立ちました。