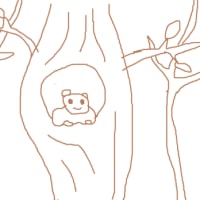日曜美術館で唐招提寺が取り上げられていました。でも、私は全く見ませんでした。奥さんは見ていたみたいで、特別な展示がある、という話でした。
毎年六月は、このお寺にとっては特別な時で、今年は5日、6日、7日の三日間だけ鑑真さんのお姿を公開したということでした。
私は、かなり昔、奈良国立博物館で見せていただいたことがありましたけど、お寺の中で見せてもらったことはなかったのかもしれません。
年に三日だけ、御影堂で鑑真さんにお会いすることができたんですね。そして、東山魁夷画伯の障壁画も見られたのかもしれません。襖絵そのものは、どこかの美術館で見せてもらいましたね。あれはどこだったかなあ。
1980年の4月に名古屋の栄で見ていました。これは第2期の作品群で、水墨画の作品群でした。それにしても、わざわざナゴヤで見ていたなんて、のん気なものでしたね。流石だなあ。

第1期の作品群は、得意の日本画で、青から紺の透明な世界と波とが描かれていました。それは1975年に完成したそうで、テスト監督に来られた古典の先生が新潮選書の東山画伯の『唐招提寺への道』を読んでおられて、そういう画家さんの本を読む、というのもあるのだと心開かれた気持ちでしたよね。画家の文章なんて、読むものではないと思ってたんでした。頭が固くて、文学的な人のものしか本として見られないところがあったんですから、私って……。

何となく、勢いで唐招提寺に来てしまいました。そんなに期待するところはありませんでした。とにかく、どこかへ行ってみたかったようです。
ブログでは2015年の2月に書いていますけど、あれ以来なんでしょうか。
いや、ブログには書いてないけど、それからも何度か来ているような気がしました。何度も何度も、来させてもらっていると思うんですが、奥さんを連れてとなると、今回も無理でしたね。なかなか難しいなあ。

金堂の横にハスの鉢をズラリと並べていました。そりぁ、もうすぐ開花ですから、一面に咲いたら、毘盧遮那仏さんも、薬師如来さんも、お客さんもうれしいでしょう。何しろ唐招提寺って、池もあるし、水も流れているんだけど、割とドライだから、こんなに飾ってくれたら、潤いがあります。
でも、管理は大変だろうな。水を絶やさないというだけでも、あちらこちらに鉢が置かれているし、これらをしおれさせるわけにはいかないですからね。

鼓楼(鎌倉時代・国宝)の前の手洗い巨大鉢、これはいつ頃置かれたのか、わからないですけど、小さい頃、奈良の絵ハガキを買ってもらった時に、ここを取り上げた1枚があって、残念だった記憶があるんですけど、小さい頃はベッタリとした真正面からの絵が欲しかったようです。
今なら、もう少し光が欲しいんだけど、今の安いカメラは、光をちゃんと表現できてないみたいで、残念な感じですけど、まあ、仕方がない。

一番奥の鑑真さんの御廟というところにもお参りさせてもらったんです。
苔の中の道を通り抜け、橋を渡ったら、鑑真さんをおまつりするお山が作られています。まわりに石造の囲いがあって、すべて漢字で書いてあって、誰なんだろうと、よく見てみたら、趙紫陽さんの名前が彫られてありました。
果たして、それはいつだったんだろう? 趙紫陽さんはこちらへ来られたの? わからないことが次から次と沸き起こったんです。