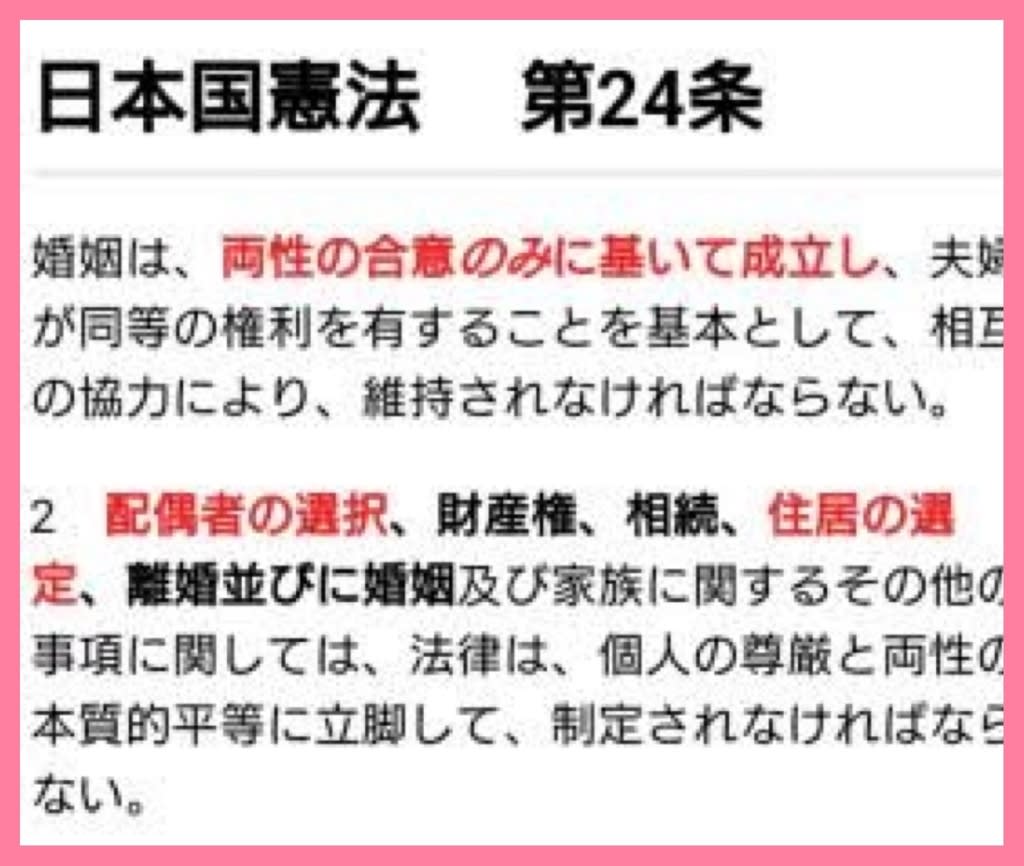新型コロナウイルス感染症は、爆発的な感染拡大の傾向を示しています。
おそらく、今後もスッキリと「収束」することは望めないのではないかと思ってしまいます。
新型コロナウイルス感染症のような動物から人へ感染が広がるリスクの発生は、人類による自然環境の破壊や過度な負荷をかけていることが原因だと言われています。
その意味では、このようなウイルスの発生はある程度予測できていたのかもしれません。
野生動物、天然資源の取りすぎ、経済優先の森林開発・農業推進、土壌の劣化、生態系の破壊をやめ、持続可能な世界・社会を創る時代を見据え、その大切さや地域で活動する人を育てなけらばならない。
これからの学校教育の役割の大切な側面になってくることでしょう。
それは今まで学校でやってきたような、たんなる「環境教育」ではありません。
持続可能な開発を行なっていくために、新しい時代にむかうための準備が学校現場で十分になされる必要があります。
十分な準備といえば、政府をあげて取り組んでいる学校のデジタル化についても、教師にたっぷりとした研修の機会を与え、環境整備を保障しなければなりません。
現場になかば押しつける形でデジタル化を進めていけば、被害を受けるのは次世代を担う子どもたちであるのです、