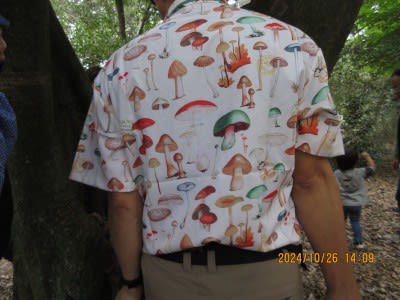・今年はあちこちでシンジュキノカワガの幼虫をよく見た。(再度写真)
成虫は見たことがない。見たいなあと思っていた。
・10月24日 室生ダムで観察会の時、メンバーのお1人が見つけてくださった見たことのない昆虫。
車にとまっていた。(再度写真)
深緑色に白っぽい縞模様。ステンレスのような金属光沢。連れ帰った。
帰って調べた結果、これが見たかったシンジュキノカワガの成虫とわかり大喜び。
虫嫌いの夫が「きれいな虫やな」というぐらいの美形。
翅を広げてほしいけれど一向に開く様子もない。
・そして今日。業を煮やして、翅を広げてみた。

黒とブルー・黄色・水玉模様・・なんというインパクト。
黄色い口吻が見える。
ちょっと強引に翅を広げ、弱らせてしまった。
毛むくじゃら。
その後、ベランダの葉の上にとまらせておいたら、横の支柱に移って・・
これぞ雲隠れの術。
その後、どこかへ行ったが、だいぶ弱らせてしまい、気の毒なことをした。