「1週間 時の流れに『、』を打つ 今日も早起き コラム記念日」
俵万智さんの「サラダ記念日」に出会ったのは、凡師が中学生の頃だっだろうか。国語の教科書に出てくる短歌とはまるで違う作品に、「こういう短歌もあるんだ」と坊主頭(凡師の出身中学は校則で全員坊主。ちなみに女子はおかっぱ頭)が集まって話していたのを思い出す。俵万智さんが高校の先生だったことを知ったのは、もっともっと後の事で、凡師が社会人になってから。凡師が俵さんの作品で最も好きなのは、「廊下にて 生徒と交わすあいさつが ちょっと照れてる今日新学期」。(俵万智著「サラダ記念日」より)
坊主頭の頃に出会った俵万智さんの作品と、凡師になってから触れる俵万智さんの作品とでは、また違った味わいがある。同じ作品でも、その作品に触れる時や場所、心によって新しい感じ方ができるのは、実に面白い。
猛暑が続く日本列島の中には、冒頭の凡師作品を読んで、止めどなく流れる涙をぬぐいきれない人もいるかもしれない。自分自身もそうだが、熱中症には気をつけたいものだ。
凡師の夏をうたった作品で今日はお別れ。
「熱中症 短パン・半袖・虫パッチ したたる汗に カレーとアイス」
 19年前、私の勤務する学校で、文化祭用の踊りがつくられた。それは、「南中ソーラン」と呼ばれるようになり、思春期真っ盛りの中学生の心を今も捉え続けている。練習を積み、切れのよい一生懸命な舞は観客の心を引き付けてやまない。踊りの輸は南中を超えて広がり続けている。市民ぐるみの子育て運動の街・稚内の共有財産となり、稚内発の新しい郷土芸能として根づいて欲しい。
19年前、私の勤務する学校で、文化祭用の踊りがつくられた。それは、「南中ソーラン」と呼ばれるようになり、思春期真っ盛りの中学生の心を今も捉え続けている。練習を積み、切れのよい一生懸命な舞は観客の心を引き付けてやまない。踊りの輸は南中を超えて広がり続けている。市民ぐるみの子育て運動の街・稚内の共有財産となり、稚内発の新しい郷土芸能として根づいて欲しい。
夏休みの今日も体育館からソーランの歌が聞こえる。中学生が高校生から踊りを習っているのだ。市内4申学校の21人が来月、地震で被災した宮城の中学校で踊る。「ソーランで元気を贈りたい」という中学生の声を稚内市が受け止めてくれたからだ、市内3校19人の高校生は、今月の全国高校PTA研究大会(札幌)で踊る。来年から市内全小中学校の共通教材になるので各校の先生たちも真剣に見ている。
稚内の中学生が、東北の中学生の困難を想像し、自分たちが学ぶ郷土芸能で交流したいという心がうれしい。この踊りの原点、最北端の海で働き苦難の中でふるさと稚内をつくり上げた先達に学ぶ精神に重なる。
国難といえる大震災は、子どもこそが確かな希望なのだと私たちに教えてくれた。教育とは子どもを人間にするための大人からの激励だが、子どもが大人を勇気づけるのも教育の可能性だと信じたい。【平成23年8月9日 北海道新聞「朝の食卓」】
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 今回のコラム、学校や稚内の宣伝にならないように注意した。踊りの起源を「学校再生」にしたがる誤りがずうっと気になっていた。昭和の荒れと、平成の踊りが一緒くたになるのは映画の世界だけだ。今回は本欄に、「教育」をストレートに書いてみた。
今回のコラム、学校や稚内の宣伝にならないように注意した。踊りの起源を「学校再生」にしたがる誤りがずうっと気になっていた。昭和の荒れと、平成の踊りが一緒くたになるのは映画の世界だけだ。今回は本欄に、「教育」をストレートに書いてみた。
大震災で、既婚者の8割以上が結婚相手を評価し、独身者の結婚願望が高まっている、と某生命保険会社の調査結果(8/7朝日)。関東圏1万人から、震災時の対応で「結婚相手を見直した(尊敬した)」既婚者が85.4%(男89.5%、女81.7%)。独身者の「いち早く結 婚したい」、「妥協して結婚する」が大幅増加の回答。何だか嬉しい。
婚したい」、「妥協して結婚する」が大幅増加の回答。何だか嬉しい。
立男は、ママヨさんを「水や空気のようなもの」と昔も今も思う。親友のママヨさんもそう思っているはず。大切なのは、互いにきれいな水や空気であり続けることだ。立男の場合、たとえ間違って汚染しても(しつこいが、何かの間違いの場合ダヨ)、濾過したら使ってもらえるぐらいのレベルにとどめるのが最低モラルだ。加齢臭ぐらいは許され…。
この国は3.11から、安心できない水や土や空気の国に変わった。専門家がいくら知恵をしぼっても安心できる手立てが見えないのだから「核と人は共存できない」のは誰が何と言おうと明白だ。では、未来は絶望なのか?そうではないだろう、人と人との「絆」がまだ信じられるからだ。ここに人の生き延びる可能性を信じたい。その単位が家族だ。結婚価値の高まりは未来に向かう吉報だと思う。あらゆる種類の生命は、こうやって生き延びてきたんだろう。人類が絶滅種になるかならないかは、現時点の人の知恵と勇気にある。 先週、誕生間もない赤ちゃんの訪問、命の不思議さと「希望」の形をママヨさんと実感。今週、若い人のお見合いに立ち会った。「うまくいきますように」と心から。
先週、誕生間もない赤ちゃんの訪問、命の不思議さと「希望」の形をママヨさんと実感。今週、若い人のお見合いに立ち会った。「うまくいきますように」と心から。
ある本に載っていた新聞記事。内容は、今から100年ほど前の子ども達が夢見た「未来の世界」。時速数100㎞で走る丸い胴体の乗り物等、今では技術が確立されているものばかりで、 100年もかからずに実現できたものもあった。「未来を思い描くこと」というのは尊いことで、技術の進歩には必要不可欠だということを改めて考えさせられた。
100年もかからずに実現できたものもあった。「未来を思い描くこと」というのは尊いことで、技術の進歩には必要不可欠だということを改めて考えさせられた。
奇しくも凡師が小学生の頃、美術の課題で描いた「未来の道具」は、ずばり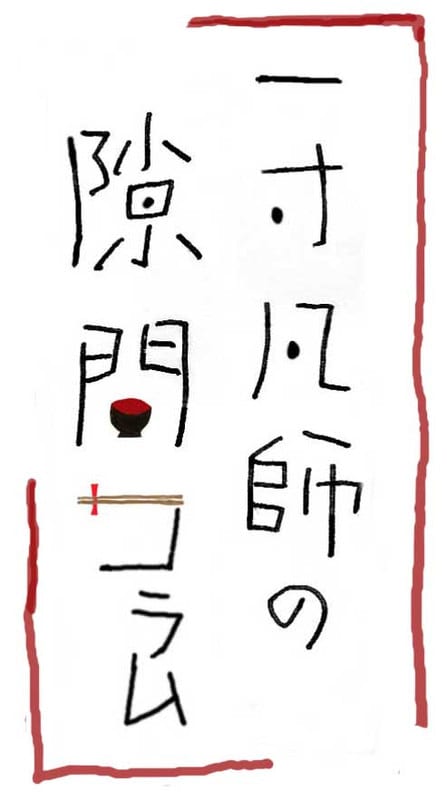 「未来の電話機」。コードレスの電話機にディスプレーが付いており、電話番号を教えてくれるというもの。今考えると、携帯電話そのものではないか。携帯電話の原型を今から30年も前に描いていた「少年凡師」。さすがである。もしかしたら凡師のポスターを見た技術者がインスピレーションを受け、開発につながったのかもしれない。そう考えると、「アチャー!」と思えるようなポスターや言葉も、何かのきっかけになる可能性は十分にあるのだ。
「未来の電話機」。コードレスの電話機にディスプレーが付いており、電話番号を教えてくれるというもの。今考えると、携帯電話そのものではないか。携帯電話の原型を今から30年も前に描いていた「少年凡師」。さすがである。もしかしたら凡師のポスターを見た技術者がインスピレーションを受け、開発につながったのかもしれない。そう考えると、「アチャー!」と思えるようなポスターや言葉も、何かのきっかけになる可能性は十分にあるのだ。
この駄文「隙間コラム」も、誰かの内に秘めたエネルギーのベクトルを決める「ひらめき」やエネルギーの吹き出し口に穴をあける「きっかけ」になっているとすれば、「青年凡師」もうれしい限りである。
さて、「少年凡師」が描いた「未来の電話」。コードレス、液晶ディスプレーは開発済。ただ、まだ一カ所だけ開発されていない部分がある。それは、電話機の上についた「タケコプター」。電話をかけたい時に、受話器が飛んでくるという発想。少年凡師、恐るべしである。
70年後の世界では、携帯電話が空を飛んでいるのだろうか、それとも人が空を飛んでいるのだろうか? 2080年の新聞記事が楽しみである。


















