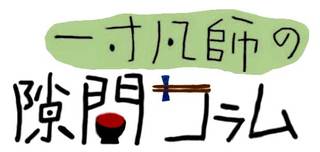愛される努力
愛される努力
ある日の腹ペコ家の朝食談義のこと。「大学は国の税金で運営しているのだから、国旗掲揚も国歌斉唱も当然だ」という言い方は、国旗と国歌の価値を低くしているという話になった。つまり、お金を出さないと大事にしてもらえないと言っているようなものじゃないか、ということだ。
・・・
この間の「愛国心」の問題は、人間関係に置き換えるとよくわかる。愛情や尊敬の気持ちは強制されて持つものではなく、自然と沸き起こってくるもの。好きな人に好きになってもらいたくて、あれこれ努力するのが普通だと思うのだけど、それを怠って「愛せよ」というのは、自信がないのかなんなのか。「いい国だと思ってもらう努力はしません」と宣言されているようにも思えて、脱力してしまう。「付き合ったあとだって愛され続ける努力をするのに、その最初の段階を怠るなんて!」とぷりぷりしながらの朝ごはんとなった。










 【藁】イネ・ムギの茎を干したもの。「溺れる者は-をもつかむ(=非常な苦境に立たされた者は、どんなに頼りになりそうもないものでも頼りにしたがるものだ)〈新明解 国語辞典〉。集団的自衛権の法的根拠にした砂川事件判決を、憲法学者の方々がバッサリ批判した時に使ったことわざ。戦争できる国の根拠に、よりによって【藁】を持ち出すお粗末さを笑ってる。いつまでたっても【藁】は【藁】でしかないですよ、は痛烈かつ痛快。
【藁】イネ・ムギの茎を干したもの。「溺れる者は-をもつかむ(=非常な苦境に立たされた者は、どんなに頼りになりそうもないものでも頼りにしたがるものだ)〈新明解 国語辞典〉。集団的自衛権の法的根拠にした砂川事件判決を、憲法学者の方々がバッサリ批判した時に使ったことわざ。戦争できる国の根拠に、よりによって【藁】を持ち出すお粗末さを笑ってる。いつまでたっても【藁】は【藁】でしかないですよ、は痛烈かつ痛快。 今日の話、裏ブログに書いていたのをこちらへ 。
今日の話、裏ブログに書いていたのをこちらへ 。 朝食の後だった。新聞を読んでいるとママヨが「…私って馬鹿だなあ」と言うのが聞こえてきた。中身をちゃんと聞きもせず反応した立男は「馬鹿な女は嫌いだ」と口にした。するとママヨの「では今日をもって分かれることにいたしましょう」の一言。個別的自衛権の発動、これで十分に効果はあるのだ…「すいません。許して下さい」。肉を切らせて骨を切る…アベシにも教えてやらなくちゃあ。
朝食の後だった。新聞を読んでいるとママヨが「…私って馬鹿だなあ」と言うのが聞こえてきた。中身をちゃんと聞きもせず反応した立男は「馬鹿な女は嫌いだ」と口にした。するとママヨの「では今日をもって分かれることにいたしましょう」の一言。個別的自衛権の発動、これで十分に効果はあるのだ…「すいません。許して下さい」。肉を切らせて骨を切る…アベシにも教えてやらなくちゃあ。