 今月3日終了の「イラスト展」の礼状を出した。3年連続の展覧会(「絵葉書」→「ポスター、チラシ」→今回の「イラスト(原画)」)だが、初めての礼状送信。展覧会に行って記帳してきたら次々と礼状をいただいたからだ。ここにきて世間の常識を知った。絵は、こういうつながりも作るのか。
今月3日終了の「イラスト展」の礼状を出した。3年連続の展覧会(「絵葉書」→「ポスター、チラシ」→今回の「イラスト(原画)」)だが、初めての礼状送信。展覧会に行って記帳してきたら次々と礼状をいただいたからだ。ここにきて世間の常識を知った。絵は、こういうつながりも作るのか。
・・・
『絵を描く心』をテーマに、ギャラリーオーナーに助言者になっていただき、車座の談話。昔、美術を教えていた時代の教え子もいて、忘れていた若き日の波風氏の破天荒な無茶ぶりに赤面した。楽しかった。こういうのが『文化』の味かもしれない。
・・・
参加していただいた方の中から抽選で、2017カレンダーをプレゼントすることになった。365日分の数字を手書きするのが面倒なので、「今年はやめようかな」と思っていたら、天が許さなかった(苦笑)。これから作成だが、年賀状が先にできた。展示の中で「あれが一番好き」と言う言葉を思い出して。天は、時々プレゼントもくれる。 公式裏ブログの方も更新しました。
公式裏ブログの方も更新しました。
 近頃話題の「学校スタンダード」について、講義で話し合った。議論の中心は、生徒指導の方向性について。大人が、場合によっては学校が、子どもを管理しやすくするための生徒指導の方針になっていないか。誰のための生徒指導なのかを見極めることが必要なんじゃないか、という結論にたどり着いたように思う。
近頃話題の「学校スタンダード」について、講義で話し合った。議論の中心は、生徒指導の方向性について。大人が、場合によっては学校が、子どもを管理しやすくするための生徒指導の方針になっていないか。誰のための生徒指導なのかを見極めることが必要なんじゃないか、という結論にたどり着いたように思う。
・・・
議論の中で参考にした、ある学校の生徒指導方針がとても素敵だった。この素敵さは、生徒と保護者との信頼関係の構築がベースとなっているからだろう。そして、信頼関係をつくるためにはどういった働きかけを心がけるべきか、そんなことが整理されていた。
・・・
やはり基本は信頼関係だと思いつつ、気づくと腹ペコも自分の思い通りに管理しようとしがちだ。これはだれしもついやってしまうものなのか。、あるいは腹ペコの性格なのか。だれのための指導なのか、そこを間違えないようにしたい。
【波風立男談】今日のイラストは、相方の夜寝ズさん作。まめた君の顔がビーンズ形で、『い~ん』の泣き声が味わい深いですね。
 昨日の「折々のことば」(朝日新聞1面のコラム、鷲田精一著)、あっと思った。2ヶ月ぐらい前のTV、詩人宇多田ヒカルの言葉。あの波風立男氏にも印象深かったようで、もう一つのブログに記録(9/24「宇多田ヒカル」)していた。
昨日の「折々のことば」(朝日新聞1面のコラム、鷲田精一著)、あっと思った。2ヶ月ぐらい前のTV、詩人宇多田ヒカルの言葉。あの波風立男氏にも印象深かったようで、もう一つのブログに記録(9/24「宇多田ヒカル」)していた。 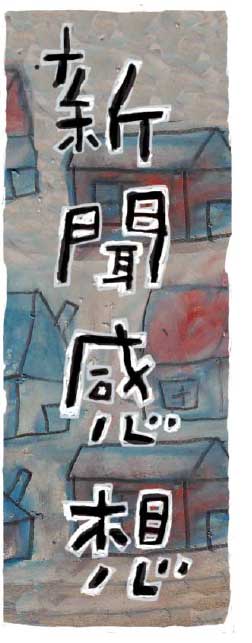
少し前まで、言葉の採集帳を作っていた。宴会の席で箸袋に記録したり、スーツのポケットや財布からくちゃくちゃになった走り書きのメモを取り出してそこに書き写したりした。新聞切り抜きと同じくらい大事な作業。言葉で心を落ち着かせ、背筋を伸ばし、文書作成の常備薬だった3冊の採取帳。
言葉の採集は、緊張感というか覚悟が必要で、定年退職以来休んでる。あいさつの機会が無くなったことが大きい。だが、言葉に対して緩んでしまうのは嫌だ。ブログに書き残そうかと思っても、読み返さないからなあ。だが、今回のように、書いていたから、反応できたのだしなあ。『記録が記憶の母』みたいな気もするし、ウーム、楽して実りを食べたい老人は悩むのだった。

(11/6 北海道新聞朝刊 書評欄から)
昨年(書評「学校の戦後史」)以来の今回(書評「崩壊するアメリカの公教育」)。「この著者は何を言いたいのか」、「どんな読む価値があるのか」、「自分の言いたいことは書いたのか」、今回も唸りながら700字の格闘。今回は前回と比べて「奥歯に何かが挟まった」、「歯がゆさ」の感じ無く、気持ちだけは楽だった。
書評の仕事は、担当記者が本を選び、依頼により始まる。書き手に本を選ぶ自由は無い。性格上、書評原稿はそのまま掲載される。本も著者も、今が旬の業界で話題の一冊。持ち上げるのも、文句をつけるのも自由だが、「的を得ているか」どうかの一点が書評の存在価値、だがこれが怖いことなのだ。書評とは、天下に読書力や批評性、文章力を評価される、晒される機会なのだ。川端康成著「水月」に出てくる『手鏡』なんかを思い出す。
同じ朝の全国紙に、この本の書評が出た。業界内で高名な学者の方。ほぼ同内容に安堵したが、字数の関係で削除したことがやっぱり大事だったなあ、と思った。
米国の大統領選、開票速報中。「どっちもどっち」感は、オバマ氏への失望と、こういう大統領選びで庶民が救われる気が全然しないからだ  公式裏ブログ更新、お題は「『タコ飯』万歳」。
公式裏ブログ更新、お題は「『タコ飯』万歳」。
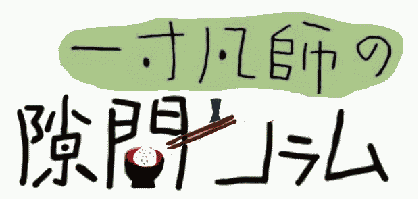 絵本セラピー
絵本セラピー
















