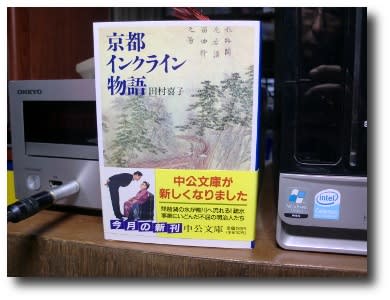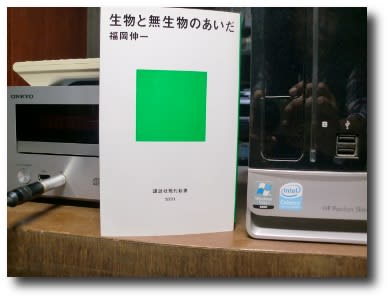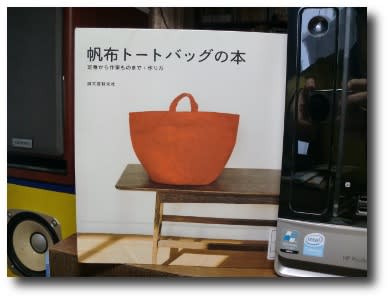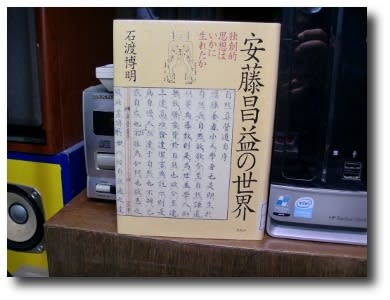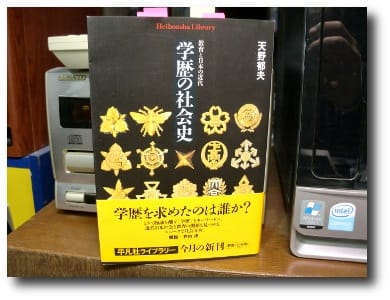河出文庫で、石井好子著『巴里の空の下オムレツのにおいは流れる』を読みました。1963年の春に暮しの手帖社から出た単行本を文庫化したものだそうで、高度経済成長期以前の1950年代、まだ日本全体が貧しかった時代に、憧れの巴里の街で生活をした頃の日常が描かれ、ちょっとハイカラな雰囲気とごく庶民ふうの視線が共感を集めたものと思われます。
そして、何よりも、登場する食べ物がほんとに美味しそうで、いたって簡単に作れるように思ってしまいます。たしかに、難しいことを言えばきりがないのですが、同じ材料を使って一定の順番で作れば、それなりに美味しく食べられることは単身赴任時代に実感しています。
玉ネギと間違えてスイセンの球根を食べさせあやうく人殺しをしそうになった話などは、ちょいと怖いエピソードですが、いくつかの料理は真似して作ってみたくなります。
○
思わず時代を感じてしまうところもいくつかありますが、その中でも、果樹農家の息子で現在は週末農業を営むワタクシらしい指摘を一つだけしておきましょう。
これは、1950年代末~1960年代初頭の品種を考えたとき、おそらくは缶詰用の白桃と生食用の黄桃とを比較しているのではないかと思います。缶詰は、後で甘く加工するわけだから、味よりも大きさが特徴的ですし、生食用の黄桃と比較したら、だんぜん味が劣ります。目的の違うものを同列に比較しても、しかたがないのです。

残念ながら氏はすでに2010年に亡くなられているようですが、現代の生食用の白桃、例えば「川中島白桃」を食べたとしたら、著者はどのような感想を持ったのでしょうか。たぶん「やっぱりちがうわね~。前言は撤回しますわ(^o^)」などと言ったにちがいないと想像しております。
そして、何よりも、登場する食べ物がほんとに美味しそうで、いたって簡単に作れるように思ってしまいます。たしかに、難しいことを言えばきりがないのですが、同じ材料を使って一定の順番で作れば、それなりに美味しく食べられることは単身赴任時代に実感しています。
玉ネギと間違えてスイセンの球根を食べさせあやうく人殺しをしそうになった話などは、ちょいと怖いエピソードですが、いくつかの料理は真似して作ってみたくなります。
○
思わず時代を感じてしまうところもいくつかありますが、その中でも、果樹農家の息子で現在は週末農業を営むワタクシらしい指摘を一つだけしておきましょう。
白桃だってそうだ。てのひら一杯にのるくらい大きく、皮をむくとつるつるの白いみの出てくる、きめのこまかい白桃は、おいしいにはおいしいが、なんだかこくがない。むしろ、小さくて黄色みをおびて、きずも少しついている、すっぱみも少しある安い桃のほうが味がよい。
果物もあまり改良されてしまうと、本来の味が消えて、まずくなるのではないかと心配だ。(p.134)
これは、1950年代末~1960年代初頭の品種を考えたとき、おそらくは缶詰用の白桃と生食用の黄桃とを比較しているのではないかと思います。缶詰は、後で甘く加工するわけだから、味よりも大きさが特徴的ですし、生食用の黄桃と比較したら、だんぜん味が劣ります。目的の違うものを同列に比較しても、しかたがないのです。

残念ながら氏はすでに2010年に亡くなられているようですが、現代の生食用の白桃、例えば「川中島白桃」を食べたとしたら、著者はどのような感想を持ったのでしょうか。たぶん「やっぱりちがうわね~。前言は撤回しますわ(^o^)」などと言ったにちがいないと想像しております。