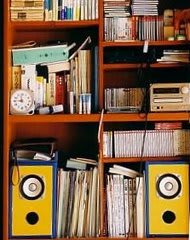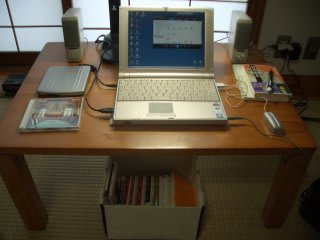昨日の土曜日、午後から老父が入院先の病院から一時帰宅、入浴して一休みし、さっぱりして、喜んで行きました。腸閉塞の手術の経過はまずまず順調なようで、食事も全がゆになりました。もう少し経過を見て、抗ガン剤の化学療法を再開する予定です。気力がおとろえていないのがなによりです。
そんなこんなで、山形弦楽四重奏団の第27回定期演奏会、アンサンブル・ピノによるプレ・コンサートには間に合わず。ヴァイオリンの中島光之さんのプレトークに、ようやく間に合いました。会場となる文翔館議場ホール、いつもは前列のほうに陣取るのですが、今回はおとなしく一番後ろのほうへ。ホールの特性でしょうか、中島さんの声がマイク無しでもよく聞こえます。内容は本日の曲目の解説ですが、特にフォーレについて詳しく説明してくれました。
ドイツ・ロマン派が行き着いたワーグナーなどのドイツ音楽に対し、フォーレはフランスの音楽を求めます。グレゴリオ聖歌などに遡り、新しい響きを追求。フォーレの「レクイエム」には「怒りの日」がないように、派手な表現を嫌い、内面的な作風が特徴。弦楽四重奏曲は最後の作品で、心の平安に向かって行くものです。響きは穏やかで、心に浸みて行く音楽、とのことです。
お客さんの入りはほぼ満席に近いくらい、かなり多かったのではないでしょうか。演奏は、まずハイドンの弦楽四重奏曲 ニ短調 作品76の2「五度」から。ステージ左から、第1ヴァイオリンを中島さん、第2ヴァイオリンが駒込綾さん、チェロが茂木さん、そしてヴィオラが倉田さんです。
第1楽章、アレグロ。短調のビッグベン。流れるようなハイドン、ふわっとやわらかいハイドンです。コントラストの強い場面でも、バランスを崩しません。こういうハイドン、好きですねぇ(^_^)/
第2楽章、アンダンテ・オ・ピウ・トスト・アレグレット。第1ヴァイオリンの主題に3人がピツィカートで。変奏が伸びやかで美しい。
第3楽章、メヌエット。アレグロ・マ・ノン・トロッポ。どことなくオリエンタルな、とても面白いメヌエットです。後半はカノン風の展開に。
第4楽章、フィナーレ。ヴィヴァーチェ・アッサイ。四人の奏者が全休止することで作られる間合いが印象的。静寂から再び第1ヴァイオリンで音楽が立ち上がって来ます。
個人的にハイドンの弦楽四重奏曲が大好き、特にこの作品76の六曲はお気に入りの作品が多く、嬉しい時間でした。
続いてベートーヴェンの弦楽四重奏曲第6番、変ロ長調、作品16の2です。第1ヴァイオリンが駒込さんに、第2ヴァイオリンが中島さんに交代します。
第1楽章、アレグロ・コン・ブリオ。小鳥の鳴くようなところもある、牧歌的な出だし。少し音程に不安なところもありましたが、全体に軽やかでリズミカルでいい感じです。
第2楽章、アダージョ・マ・ノン・トロッポ。第3楽章、スケルツォ。アンサンブルの緊密さが問われるところです。
第4楽章、La Malinconia (Adagio~Allegretto quasi Allegro) これ、メランコリックに、という意味なのかな。序奏部、第2ヴァイオリンとヴィオラとチェロが沈んだ響きを奏でる中で、第1ヴァイオリンも憂鬱な嘆きの曲想。チェロの音がしだいに高まる不安を表すのでしょうか。アレグレットも、軽やかですが晴れ晴れとはしていない。再びアダージョ、ことさらに深刻にしてはいないけれど、実は深刻な問題に直面しているようです。ベートーヴェンの演奏は、終楽章に近付くにつれて、ぐっとのってきたようです。
10分間の休憩の後、いよいよフォーレの弦楽四重奏曲が始まります。再び中島さんと駒込さんが交代し、第1楽章、アレグロ・モデラート。倉田さんのヴィオラから始まります。いい音です。全体に中低音域中心の中から、第1ヴァイオリンだけが高音と低音を行き来します。不思議なフォーレの響きです。
第2楽章、アンダンテ。静かで瞑想的な響き。4つの楽器が単独で聞こえるのではなくて、全体の響きの中に存在が見分けられる、といったあり方。絵の具が盛り上がったような絵画ではなくて、表面はつるっと平らなのに色調には陰影がある絵画のよう。
第3楽章、アレグロ。チェロから始まります。チェロのピツィカートの付点リズムがとても面白く印象的。ヴァイオリンやヴィオラも付点リズムを再現しますが、その間に他の楽器が響かせるゆらめくような旋律が繊細で美しい。
遺作となったフォーレの音楽は、意外にも、無調の音楽はすぐそこまで来ているのだな、と感じました。わかりやすい山場や見せ場といったものの少ない地味な曲を、見事にまとめた努力に拍手~です。
アンコールに演奏したハイドンの「皇帝」の第3楽章、メヌエットは、ぱっと窓が開いて外の景色が見えて来る感じ。やっぱりハイドンの弦楽四重奏曲はいいなぁ。
今回の定期演奏会、なかなか聴けないであろうフォーレの弦楽四重奏曲の実演に接することができたという点と、ハイドンの「五度」を楽しみ満足したことと、ベートーヴェンの初期の弦楽四重奏曲の意外な(?)難しさを認識したという点で、大きな収穫でした。山形弦楽四重奏団の皆さん、ありがとうございました。