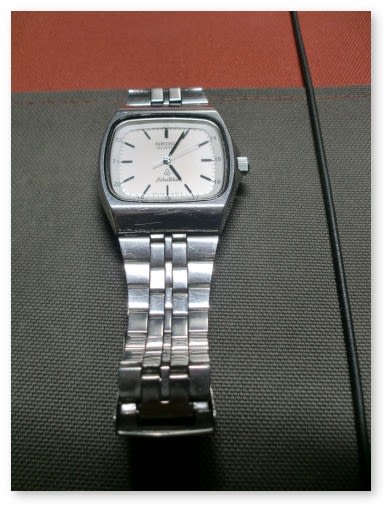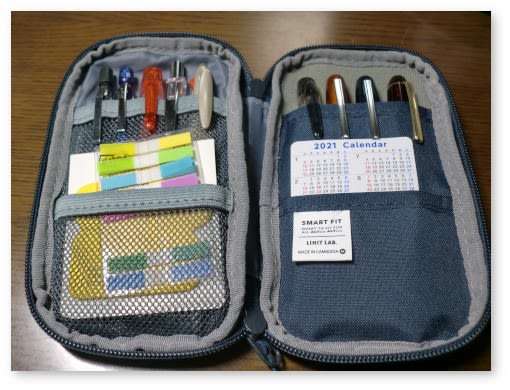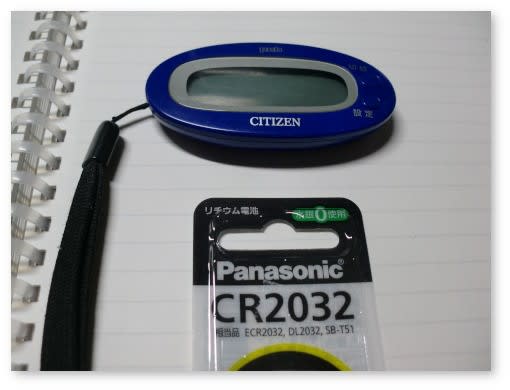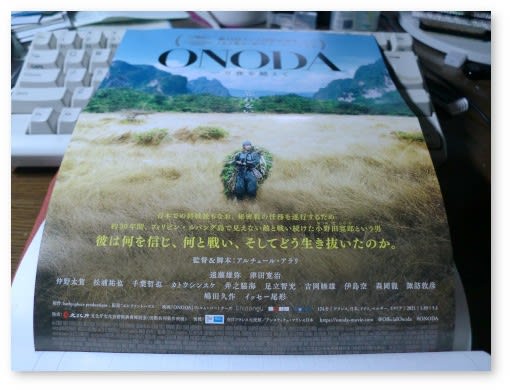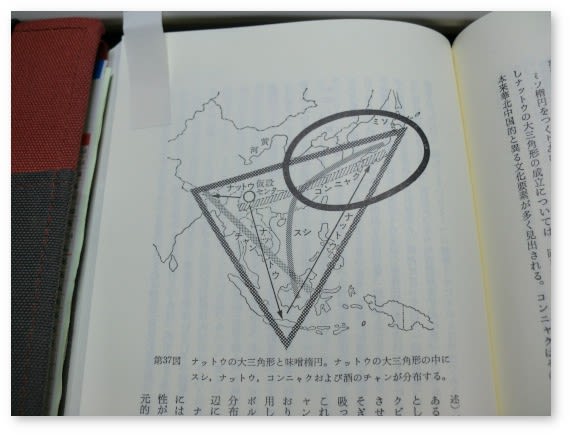季節はすっかり晩秋の装いで、田んぼは空っぽになっています。果樹園も落葉の時期に入ってきており、しだいに冬枯れの様相に近づいていくことでしょう。よその園地ですが、見事なラフランスの畑です。


久々によく晴れた週末、土曜日には自宅裏、日曜には少し離れた場所にあるもう一つの果樹園の草刈りとリンゴの落果処理をしました。草の生育速度はよほどゆっくりになりましたが、間隔が一ヶ月以上あきましたので、かなりびっしりと生えています。乗用草刈機で全体をきれいに草刈りし、クワで幹周りを耕し、リンゴの樹の下にたまっている落果を集めて穴に埋めました。昨年は野ネズミが付いたらしく一番端のリンゴの樹が一本枯れてしまいましたので、今年は落果を投げ込んだ穴の上から石灰窒素を撒き、土をかぶせるようにしました。今日から一週間、地区一斉の野鼠対策期間となります。我が家のアホ猫の心配もなくなりましたので、鼠穴に殺鼠剤を投入してみる予定。さて、効果のほどはどうでしょうか。
日差しがないと風が冷たく寒いのですが、日差しがあるとぽかぽか暖かく、気持ちが良いものです。今年一年の果樹園管理を思い浮かべ、来年はこうしようなどと考えながらぐるりと園地を見回りましたが、トンビが二羽、樹の上からこちらを見おろしていました。あれはたぶん、怪しいヤツが来たぞと警戒しているのでしょう。いや、こちらは人畜無害の前期高齢者、まったくあやしい者ではないのですが(^o^)/ こういうときに、ドリトル先生みたいに動物と話ができるといいのですけどね〜(^o^)/


久々によく晴れた週末、土曜日には自宅裏、日曜には少し離れた場所にあるもう一つの果樹園の草刈りとリンゴの落果処理をしました。草の生育速度はよほどゆっくりになりましたが、間隔が一ヶ月以上あきましたので、かなりびっしりと生えています。乗用草刈機で全体をきれいに草刈りし、クワで幹周りを耕し、リンゴの樹の下にたまっている落果を集めて穴に埋めました。昨年は野ネズミが付いたらしく一番端のリンゴの樹が一本枯れてしまいましたので、今年は落果を投げ込んだ穴の上から石灰窒素を撒き、土をかぶせるようにしました。今日から一週間、地区一斉の野鼠対策期間となります。我が家のアホ猫の心配もなくなりましたので、鼠穴に殺鼠剤を投入してみる予定。さて、効果のほどはどうでしょうか。
日差しがないと風が冷たく寒いのですが、日差しがあるとぽかぽか暖かく、気持ちが良いものです。今年一年の果樹園管理を思い浮かべ、来年はこうしようなどと考えながらぐるりと園地を見回りましたが、トンビが二羽、樹の上からこちらを見おろしていました。あれはたぶん、怪しいヤツが来たぞと警戒しているのでしょう。いや、こちらは人畜無害の前期高齢者、まったくあやしい者ではないのですが(^o^)/ こういうときに、ドリトル先生みたいに動物と話ができるといいのですけどね〜(^o^)/