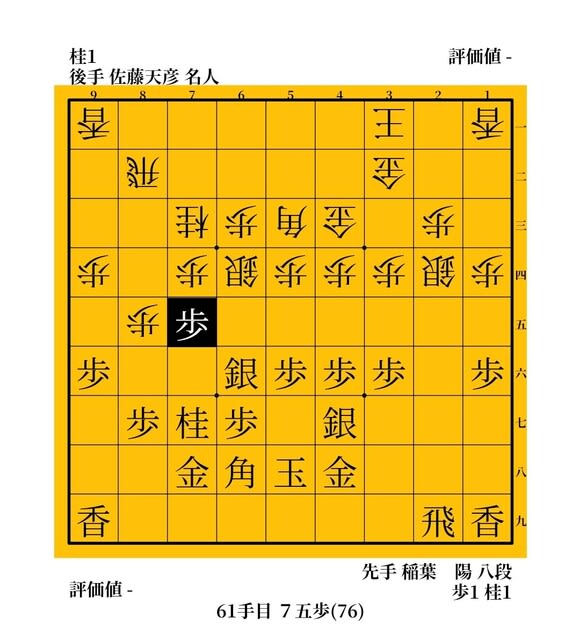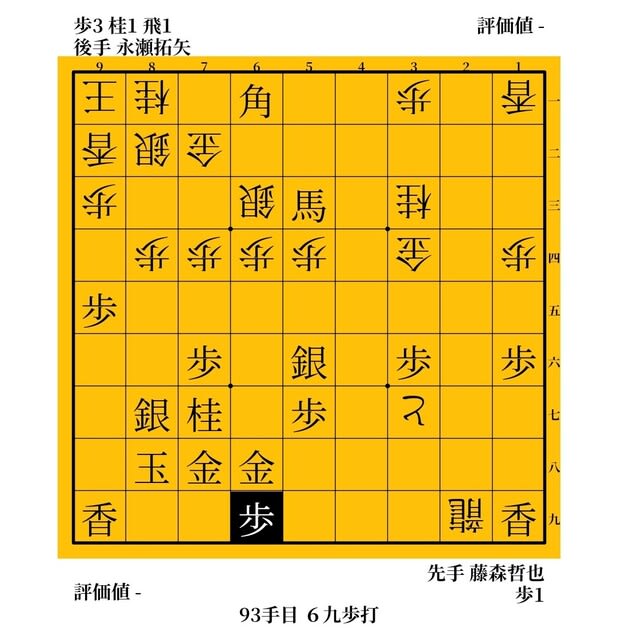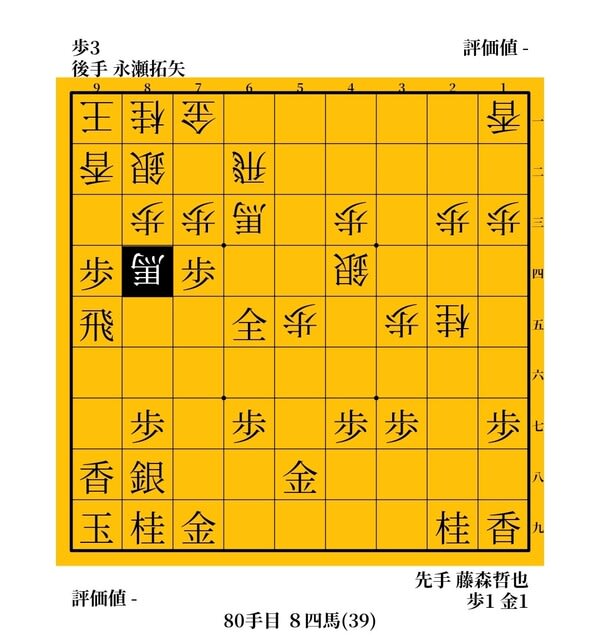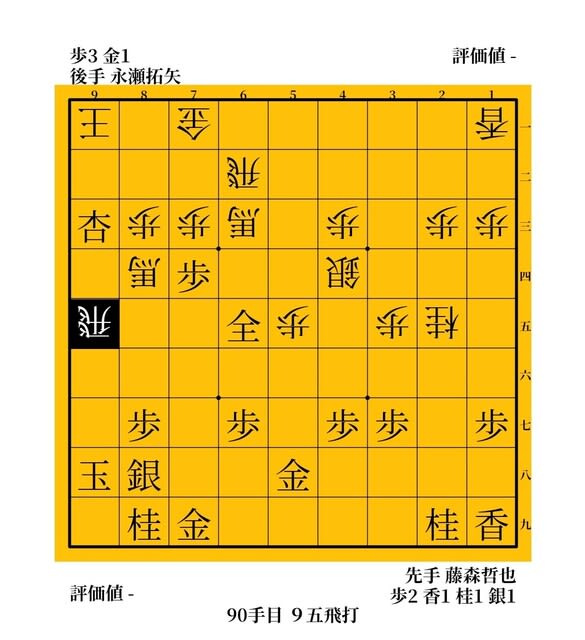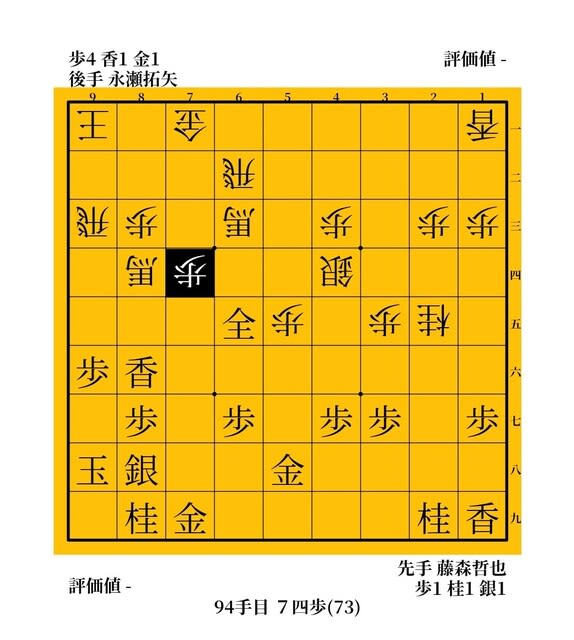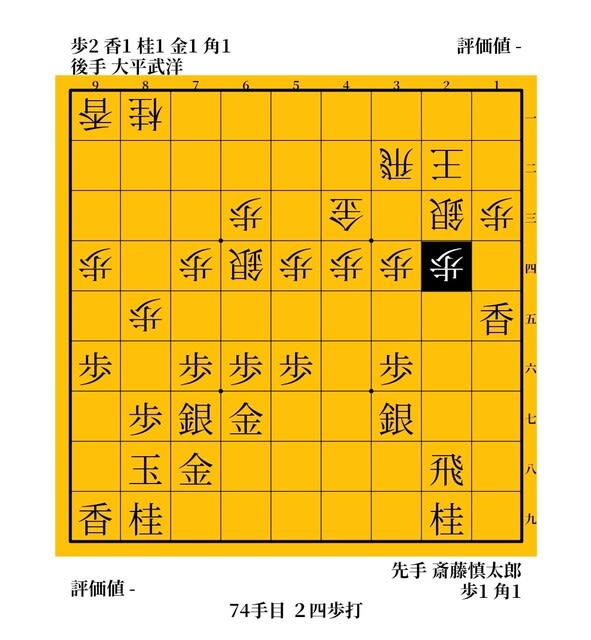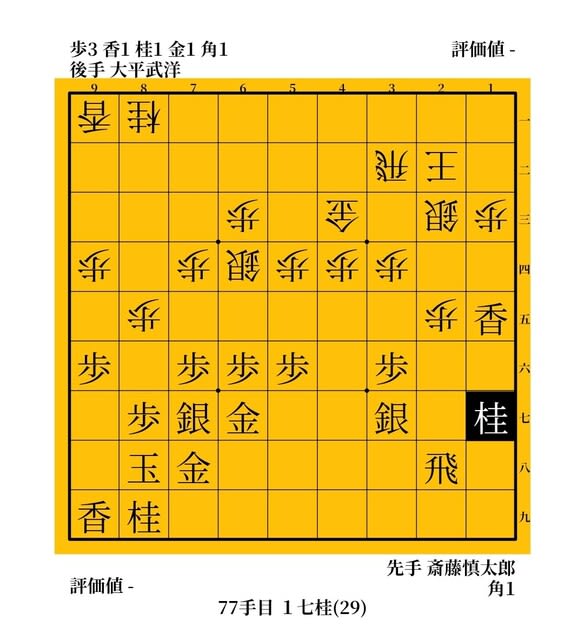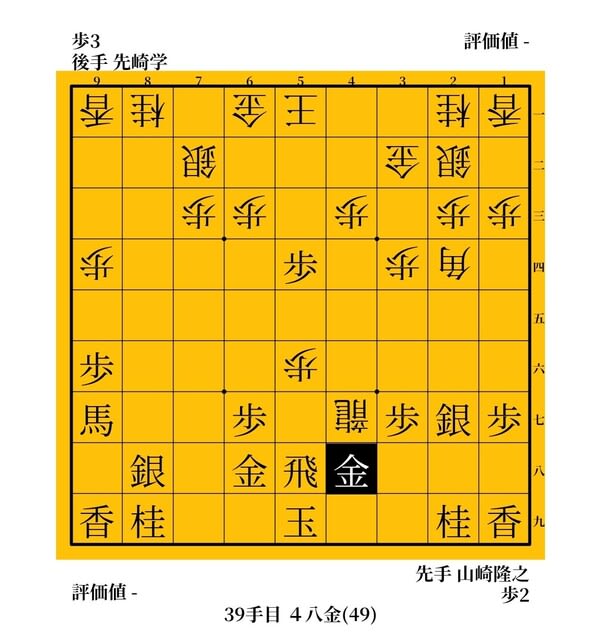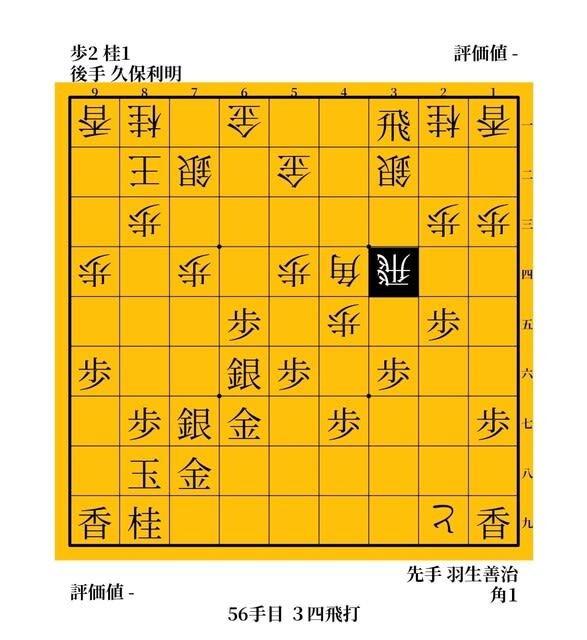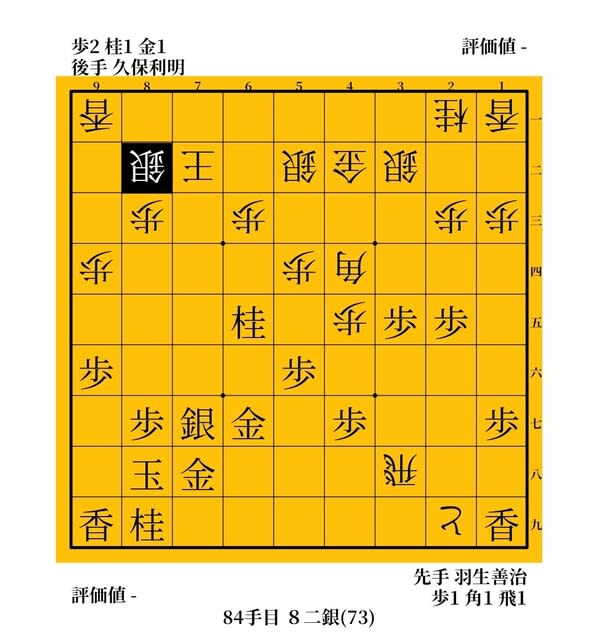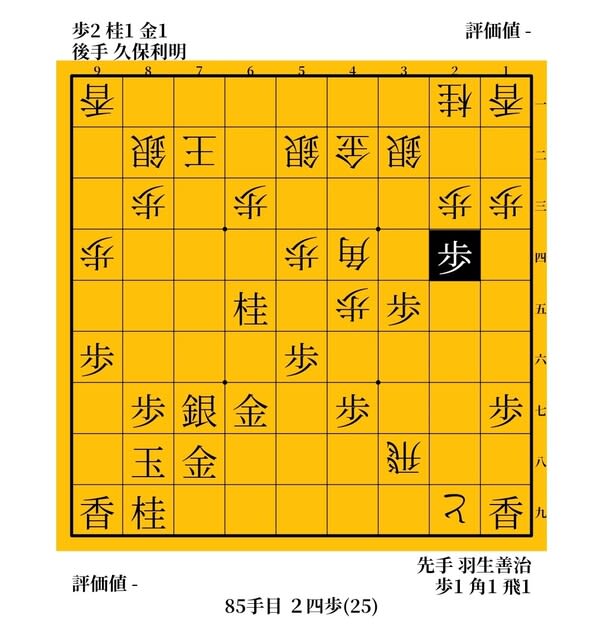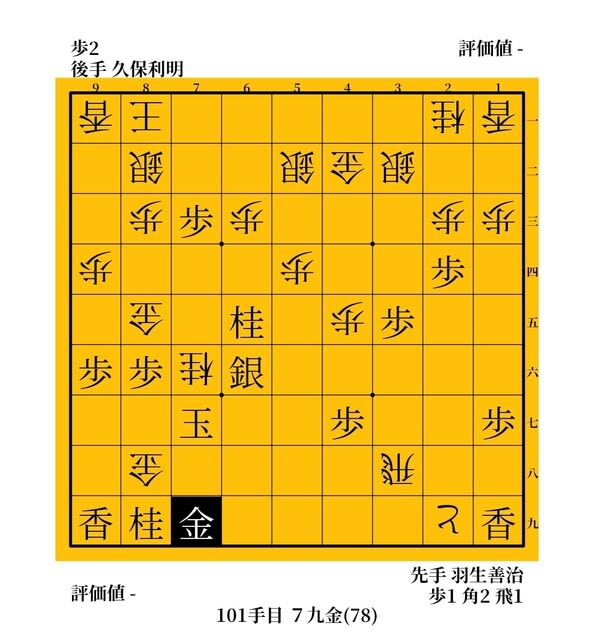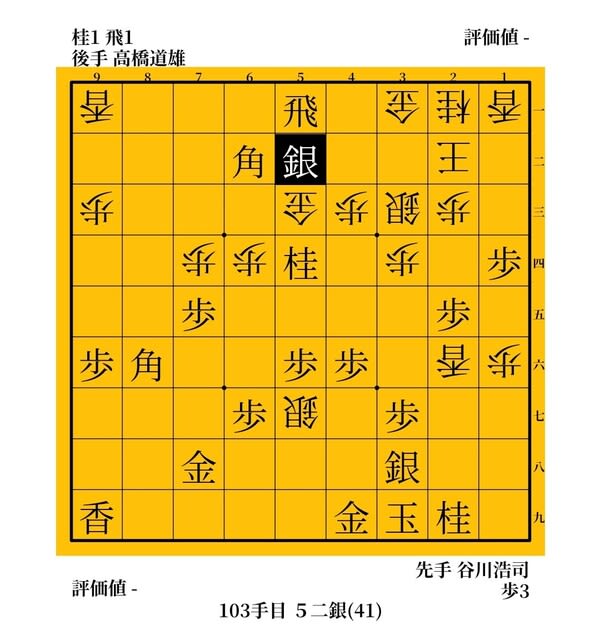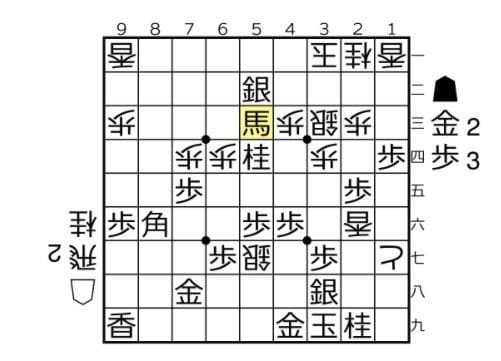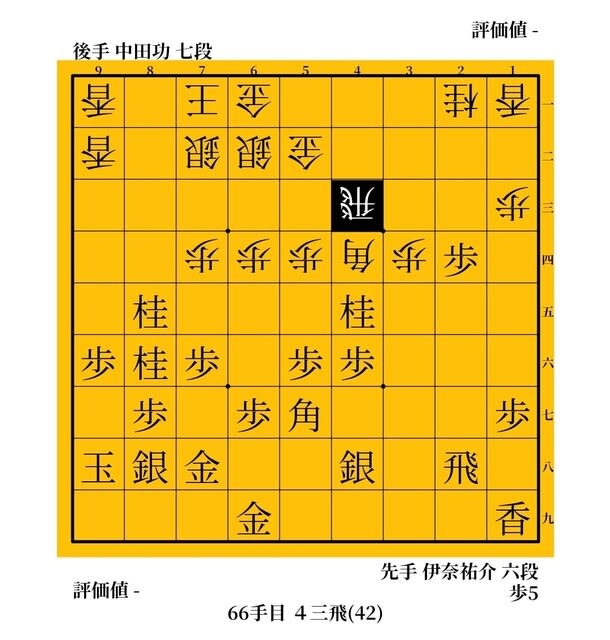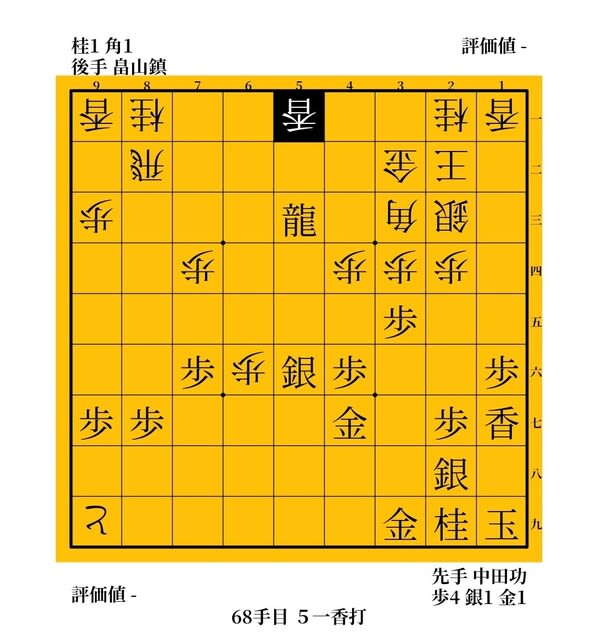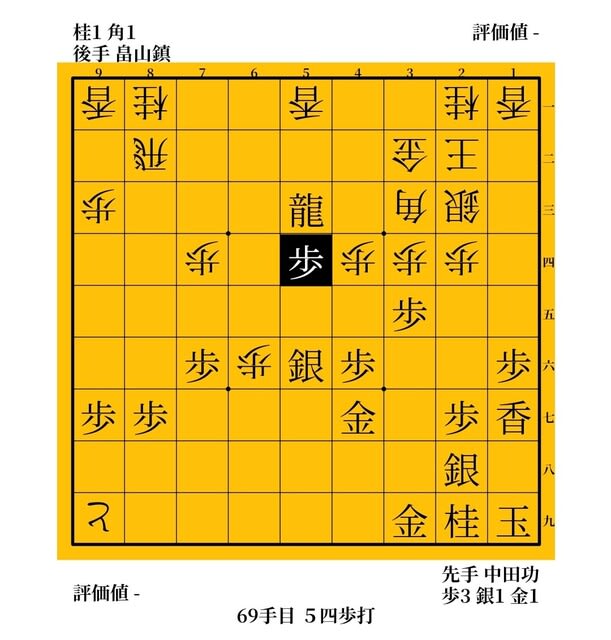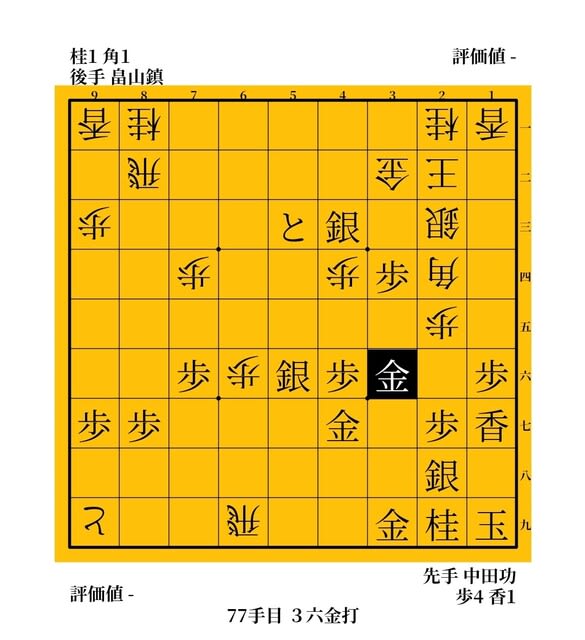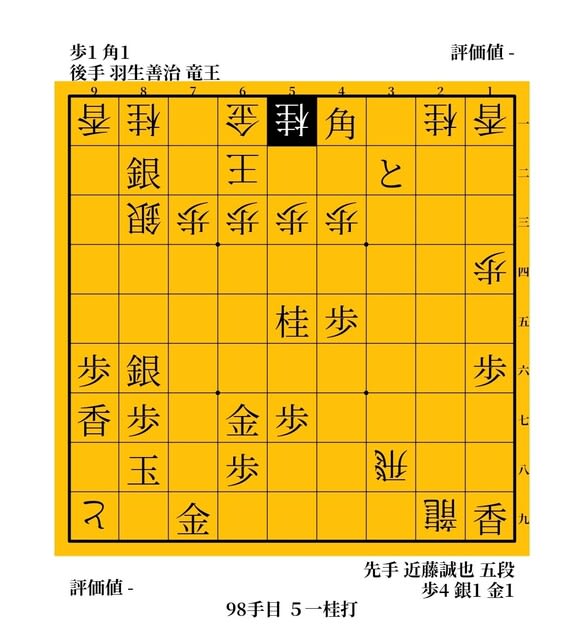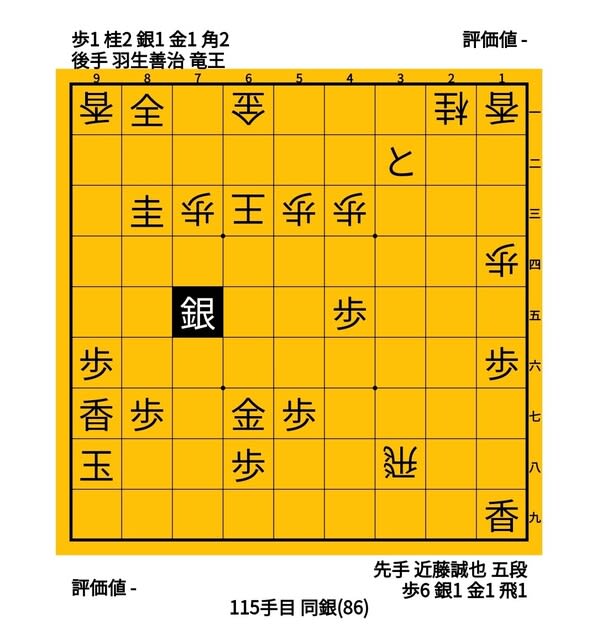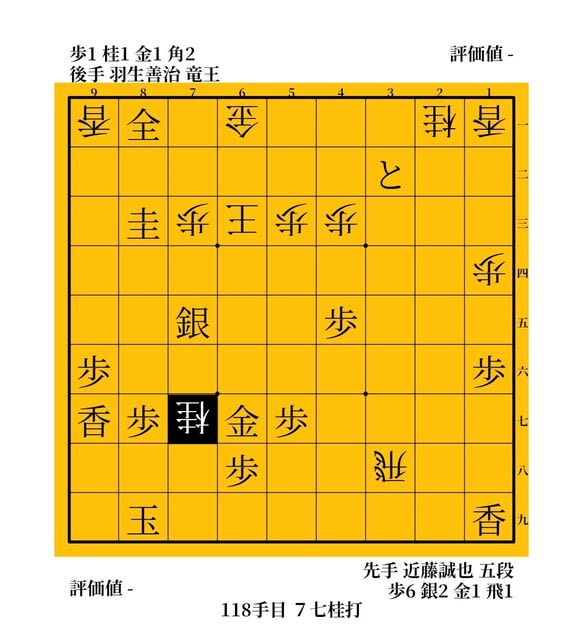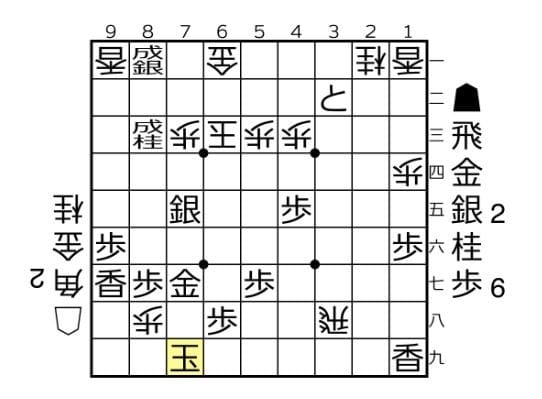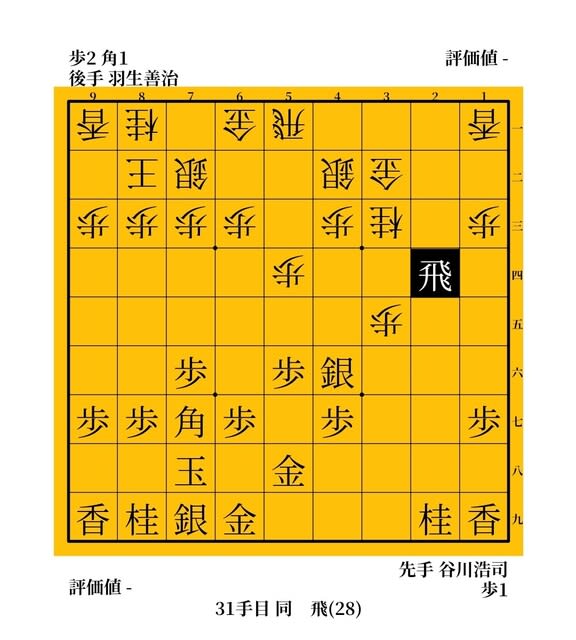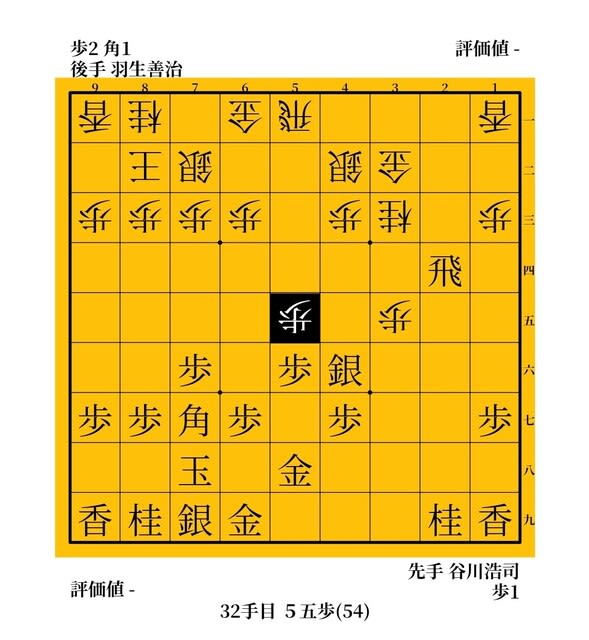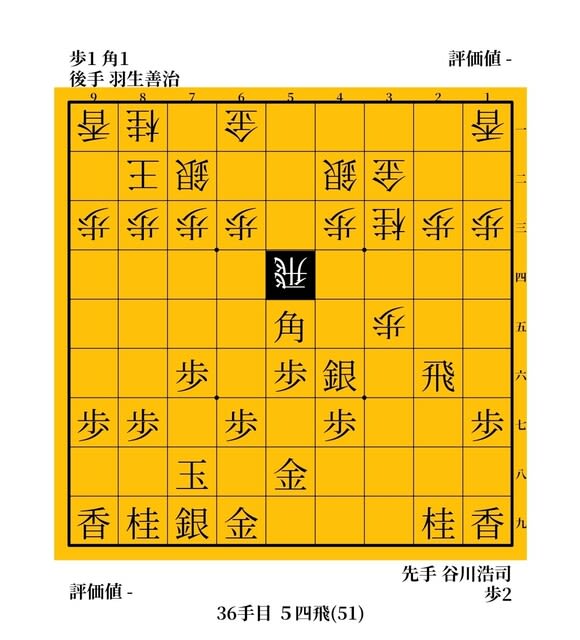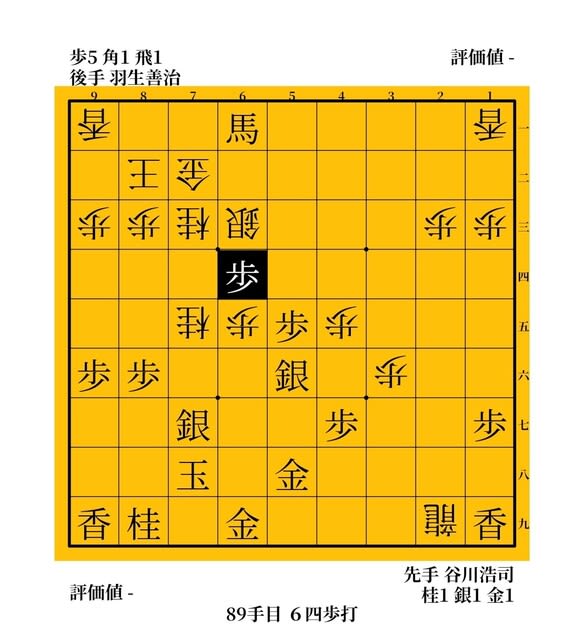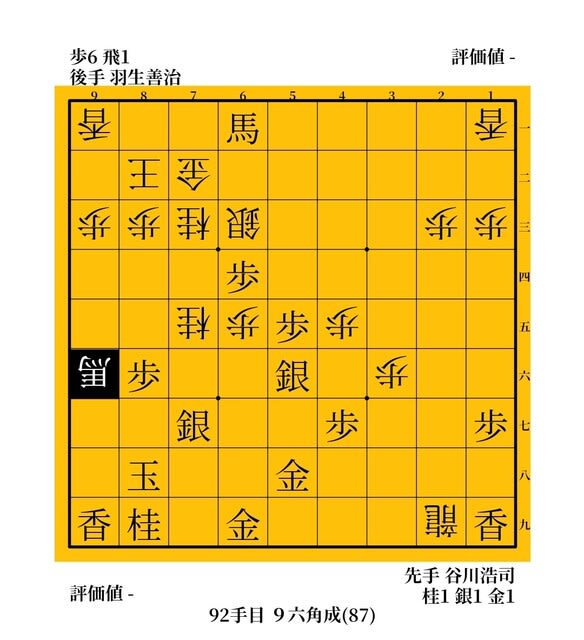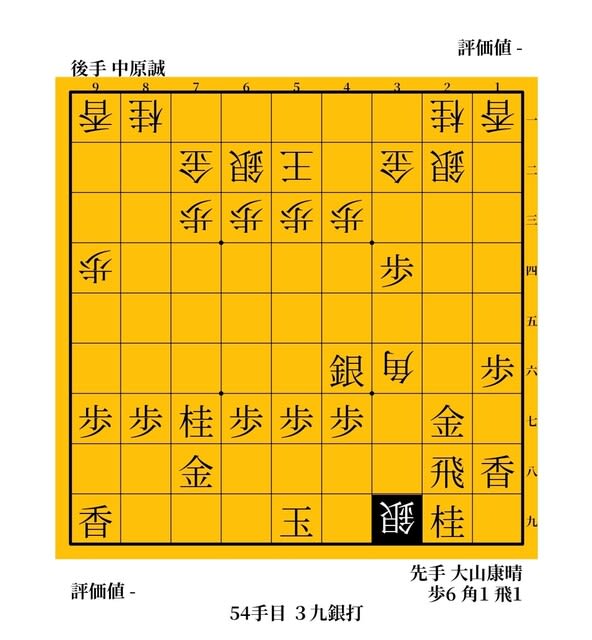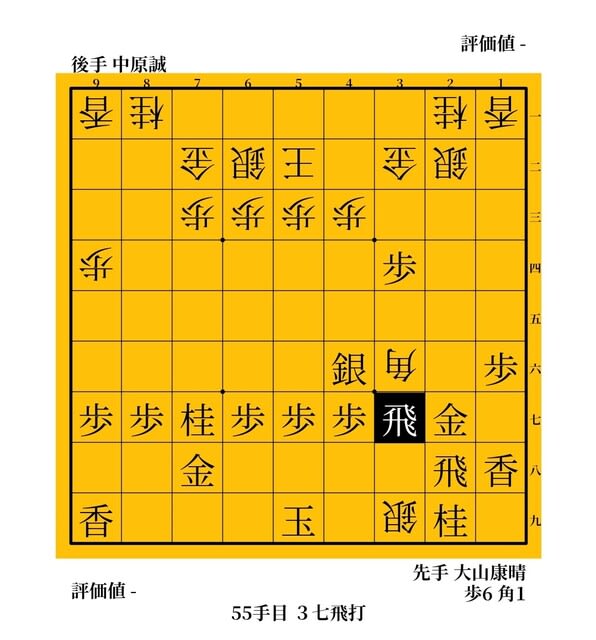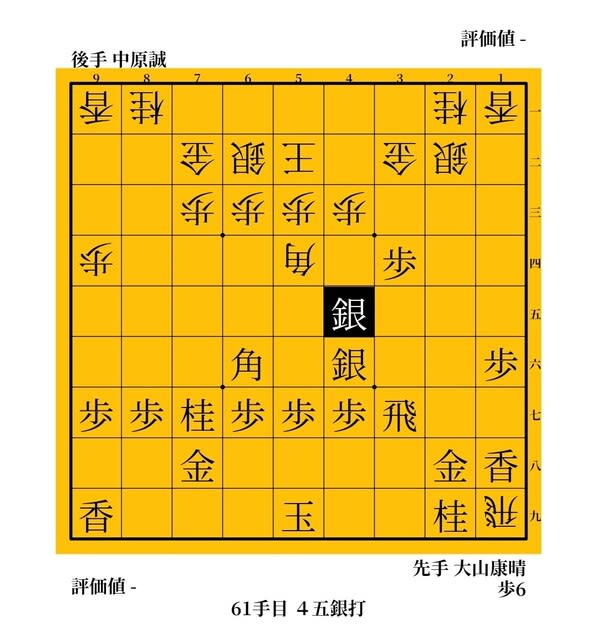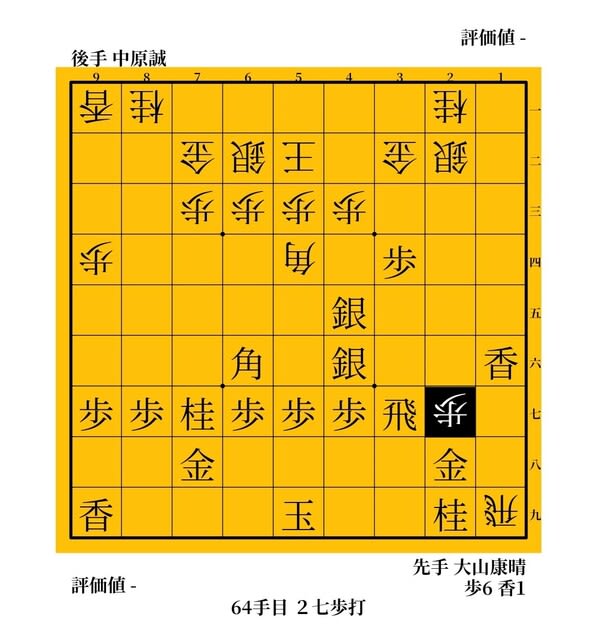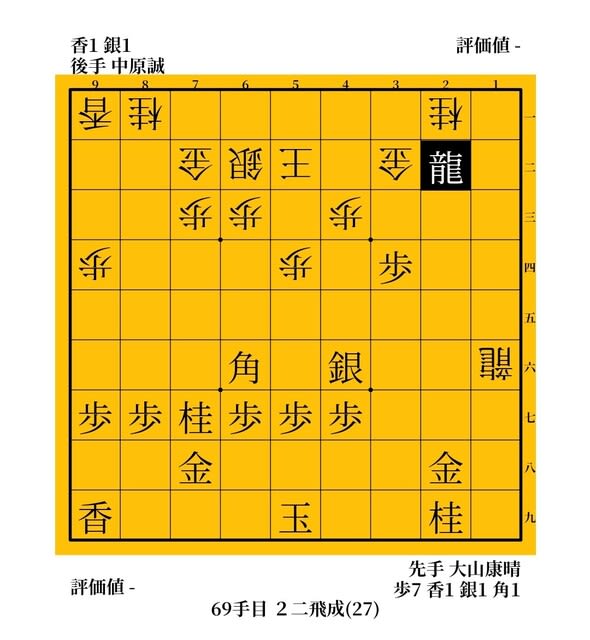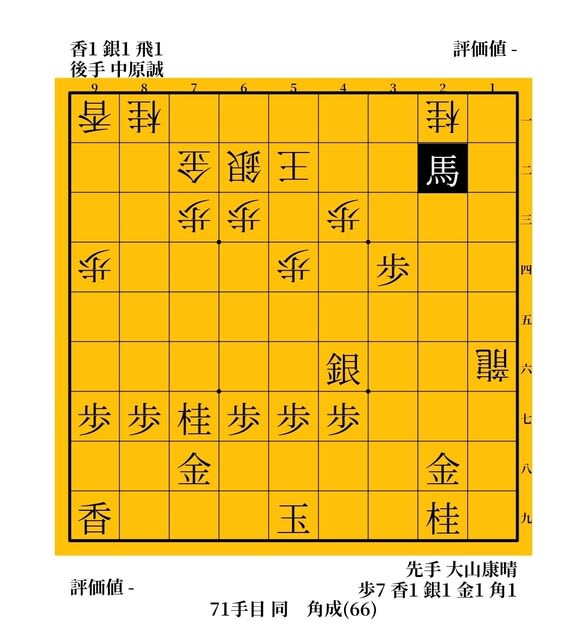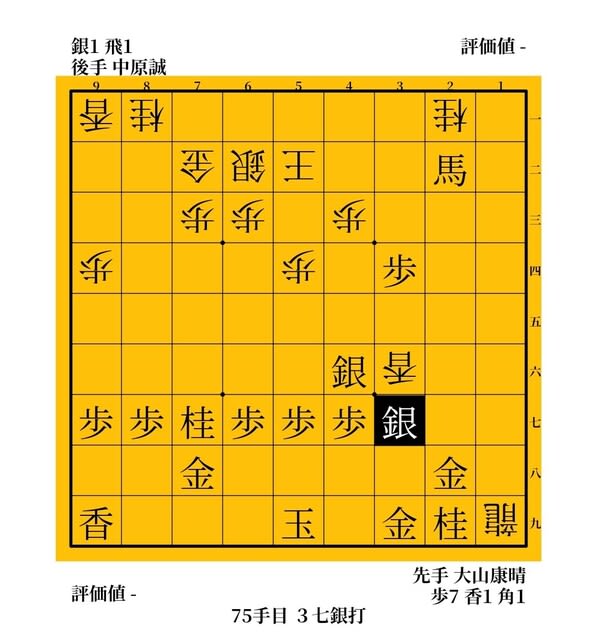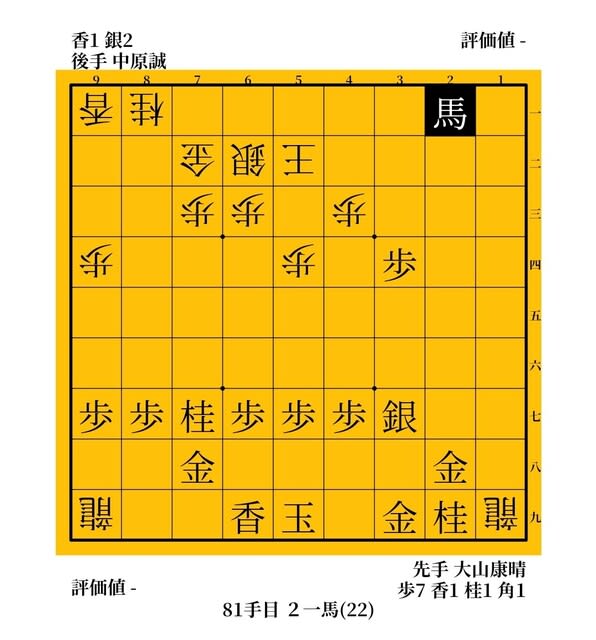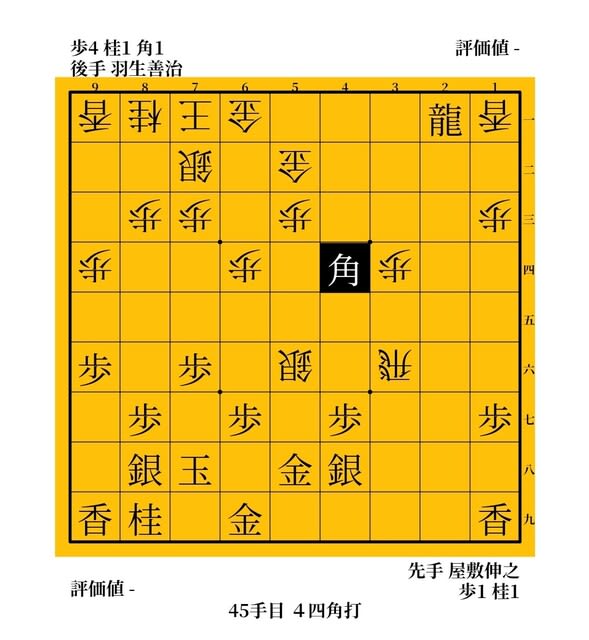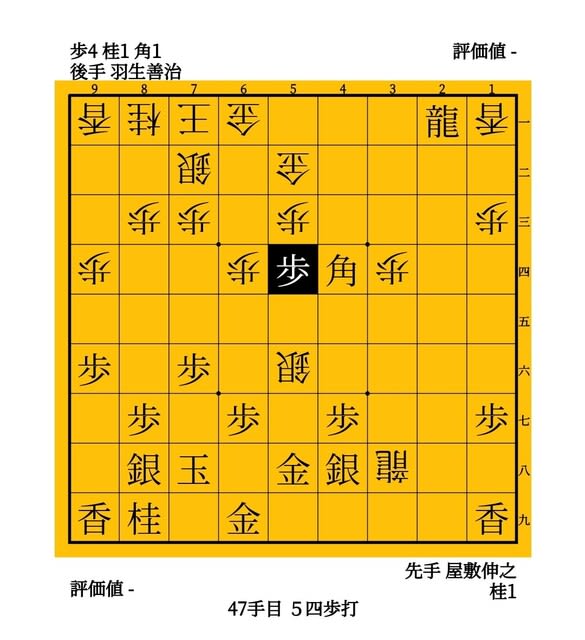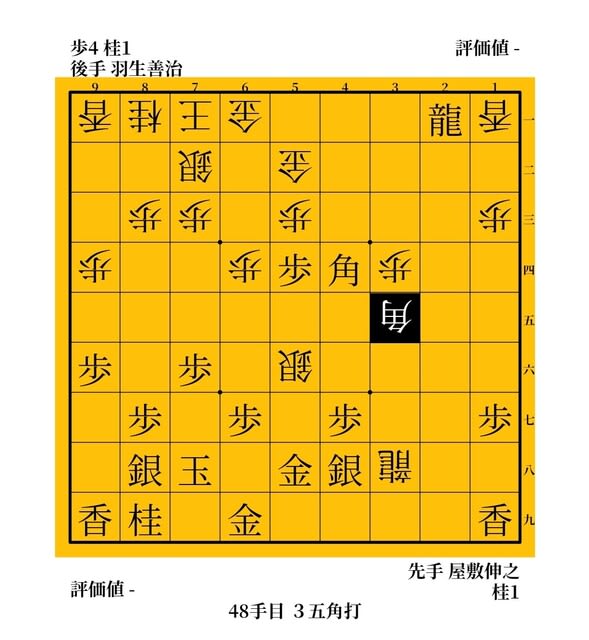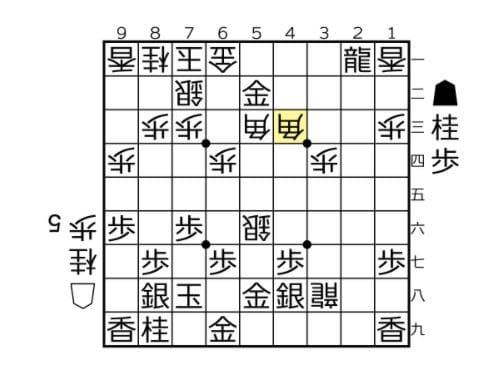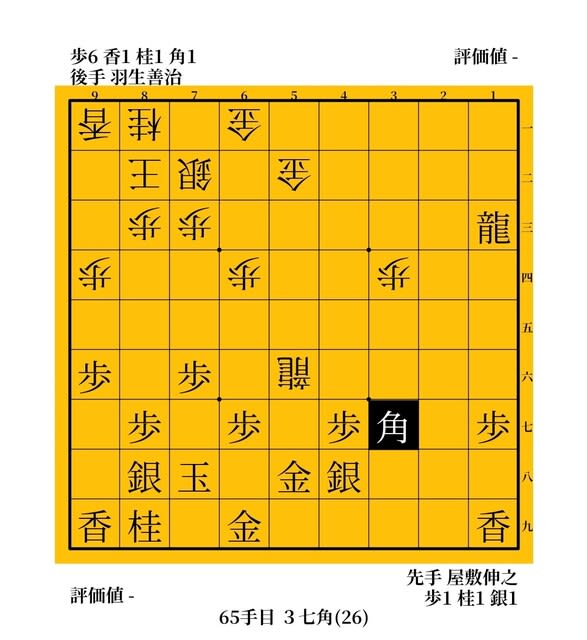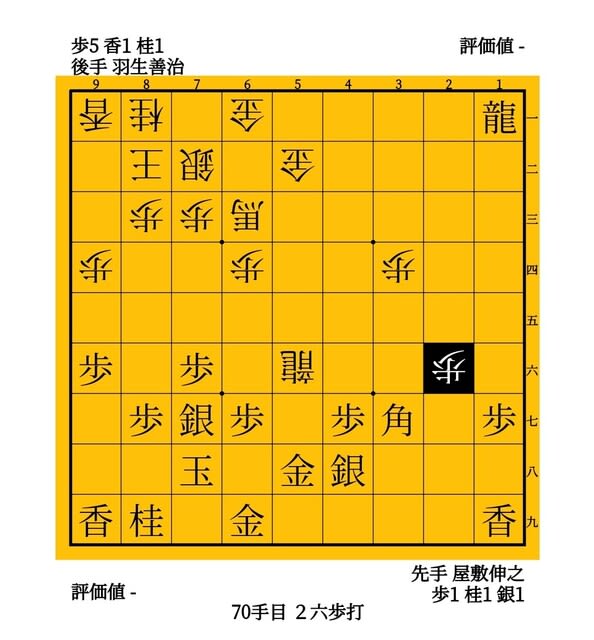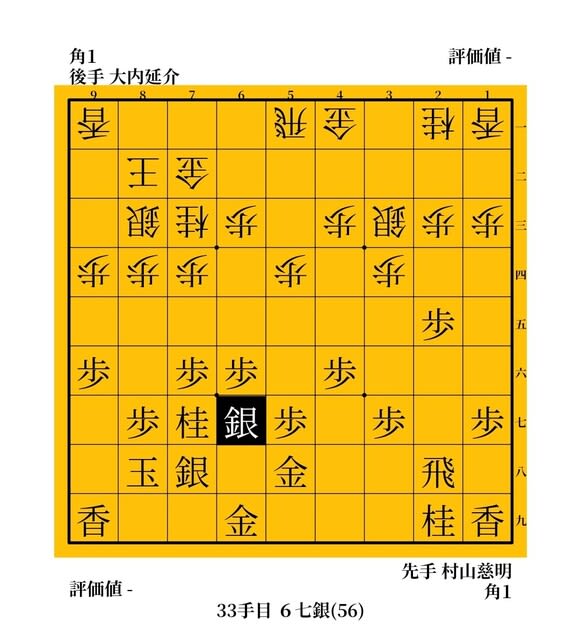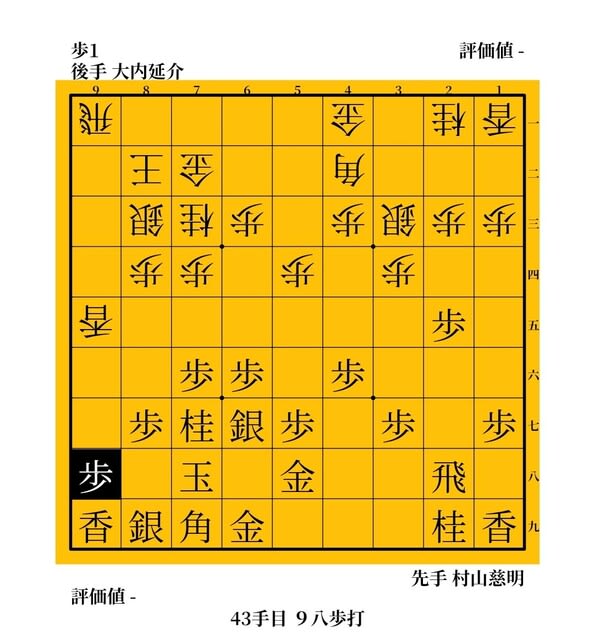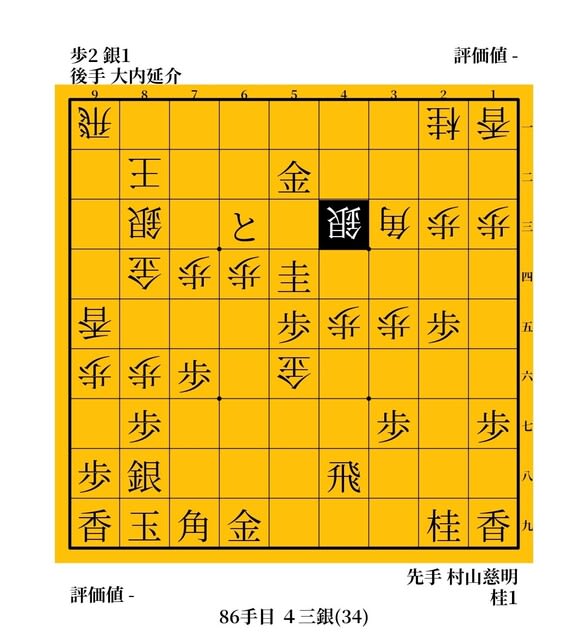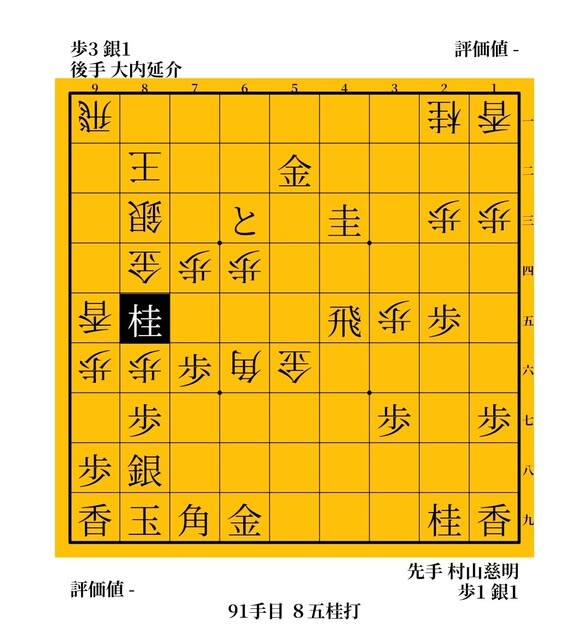「と金」というのは、メチャクチャに強力な駒である。
「成金」の語源にもなったもので、最弱の駒である「歩」が、「金」に成りあがるのだから、その痛快さといったらない。
しかも、敵に取られると、それが「歩」に戻るというのだから、ほとんどタヌキにもらった葉っぱのお札である。
この「と金」をあつかった格言も多く、
「まむしのと金」
「と金のおそはや」
「と金は金と同じで金以上」
「53のと金に負けなし」
モテモテであって、前回は行方尚史九段が、盟友藤井猛九段におみまいした「友達をなくす手」を紹介したが(→こちら)、今回はおそろしい歩の錬金術のお話をしたい。
2011年の第70期A級順位戦。
羽生善治王位・棋聖と、渡辺明竜王の一戦。
羽生のゴキゲン中飛車に、渡辺は攻めの銀を早目にくり出す、星野良生五段発案の「超速▲46銀」で対抗。
先手は馬を作るが、後手も二歩得が主張点で、難解な中盤戦。

渡辺が▲45馬と出て、後手玉のコビンをうかがいながら、△36の歩を除去しようとしたことろ。
ここで羽生が、おもしろい手を見せる。

△25角と打ったのが、ちょっと思いつかない手。
先手の飛車を押さえながら、△36の歩を守り、放っておけば△37歩成と成って、▲同桂(▲同銀)に△47角成。
という、ねらいはわかるが、これはなんとも、打ちにくい角でもある。
先手の馬に対して、後手は角を手持ちにしているのが売りのはず。
なのに、それを手放すだけでなく、働くかどうかわからない「筋違い角」に置く。
こんな生角を盤上に放って、本当に使えるのか疑問だし、そもそも取られそうでね?
事実、本譜もすぐに▲17桂から▲25桂と、この角はアッサリ取られてしまうのだが、それで局面の均衡は保てているというのだから、すごい大局観ではないか。
さすが羽生さんや、ようこんな手思いつくなあ。
感心することしきりだったが、ここでフト思いついたのは、これには「元ネタ」が、あるのではなかろうかということだ。
なんか、似たような手を見たことあるよなあと、ちょっと脳内検索してみたら、ありました。
1965年、第24期名人戦の第5局。
大山康晴名人と、山田道美八段の一戦。
先手大山の四間飛車に、山田は急戦策を取る。

後手の山田が△22角と打ったのに、▲85角と打ち返したのが「受けの大山」の見せた異筋の角。
なんと、これで先手優勢なのだが、昔なにかで、この局面を見たとき、
「これって△86銀、▲同銀、△99角成で居飛車優勢じゃね?」
なんて生意気にも指摘してみたところ、それには▲84歩、△同飛、▲97桂(!)と、こちらに跳ねるのが好手。

▲77桂には、△76歩があるから、逆モーションで端に跳んでおく。
これで次に、▲75銀から押し返して行く手があって、振り飛車優勢なのだ。
なるほどー、ええ手ですなあ。さすが大山先生や。
これらの手が、研究手なのか、それともその場でひねり出したのかはわからないが、こういう「シンクロニシティ」を感じると、今も昔も、トッププロの発想の豊かさは、変わらないんだなあとワクワクする。
ちなみに、この将棋は羽生の快勝で終わるのだが、その優位の広げ方がうまかった。

図は△55金のぶつけに、▲77馬と引いたところ。
後手が駒得なうえに、厚みでも押しているように見えるが、先手も馬の守りに、飛車の横利きもあって、決めるとなると、なかなか具体的には見えない。
こういう
「ちょっと指せそうだけど、それを優勢に拡大するための、明快な手が見えにくい局面」
というのはむずかしく、あせりを誘うところだが、羽生はいつものごとく、その課題を見事にクリアしてしまう。

△48歩成、▲同飛、△46歩で後手優勢。
この場面では、と金を作りに行くのが好着想だった。
といっても、△37歩や△36歩のような手では、なかなかうまくいかず、△21飛も金が浮いてしまって、▲55馬と取られてしまう。
とあっては、そう簡単ではなさそうだが、一回△48歩成と成り捨てて、歩の位置を下げるのがうまい着想。
感覚的には、△47の歩こそが「と金のタネ」に見えるだけに、それを捨てるというのが、なるほどというところだ。
指されてみれば簡単だが、実戦では思いつきにくい(将棋の好手はだいたいそうなのだ)。
実際、解説のプロも「いい手です」と、感心していたくらいで、次に△37桂成から△47歩成とされたら完封される。
渡辺は泣く泣く▲38歩と受けるが、今度は△58歩成とこっちを成って、▲同歩に△57歩と、こじ開けにかかる。

▲88玉の早逃げに、△58歩成、▲同飛、△56歩と、またもやバックのタレ歩。
これでとうとう、と金作りが防げない。

古い歌ではないが、まさに三歩進んで二歩下がる。
こうなると、もう先手は無限増殖してくると金で、自陣の金銀をボロボロはがされる未来しか見えないわけで、力も抜けるというものだ。
以下、後手は2枚の「まむしのと金」を使って、一気に先手陣を攻略。
これで勢いにのった羽生は、なんとこの期、9戦全勝の偉業でもって、名人挑戦権を獲得するのである。
(渡辺明の妙手編に続く→こちら)