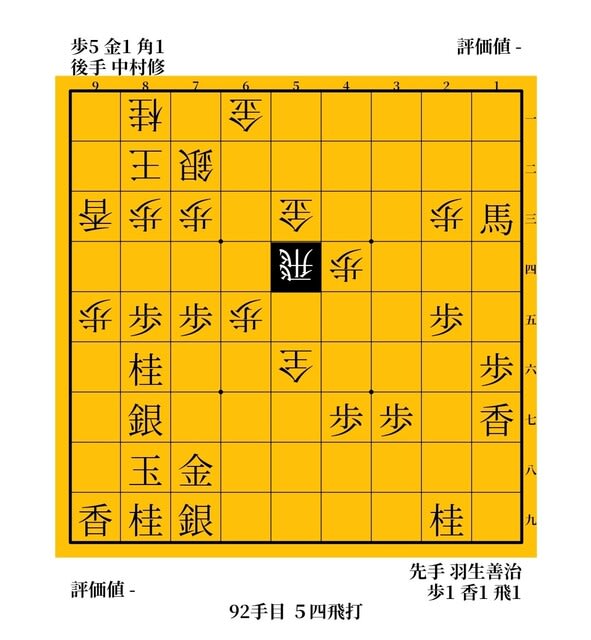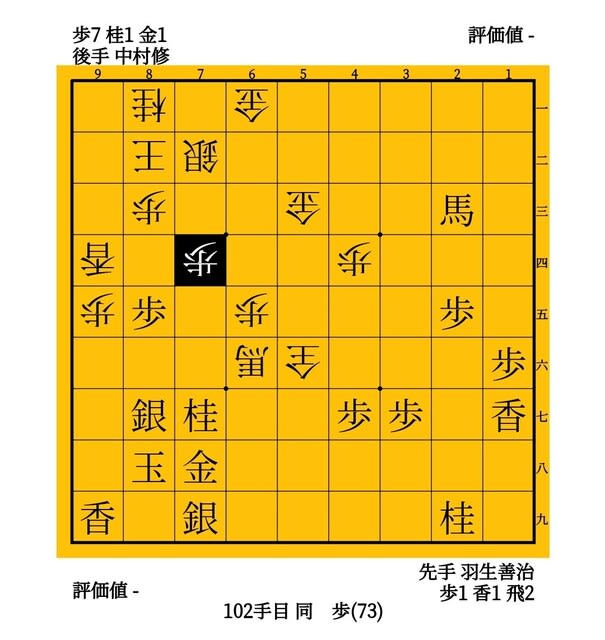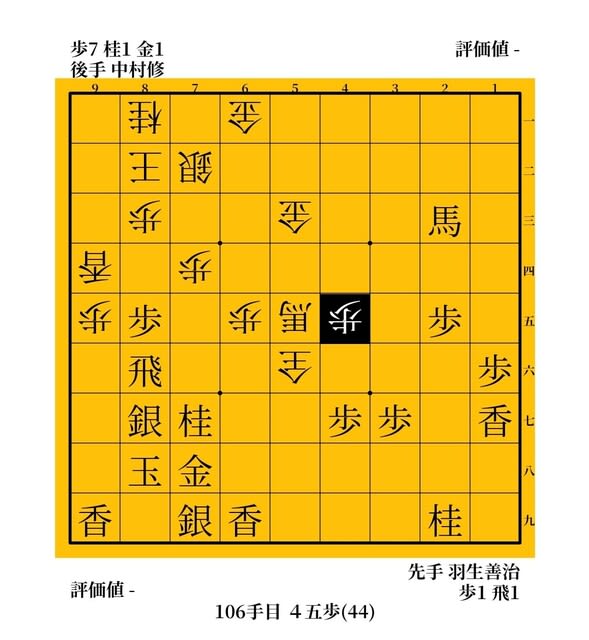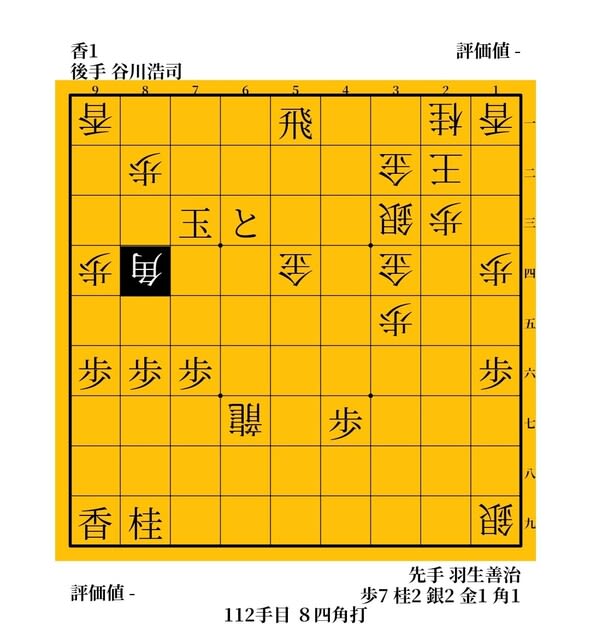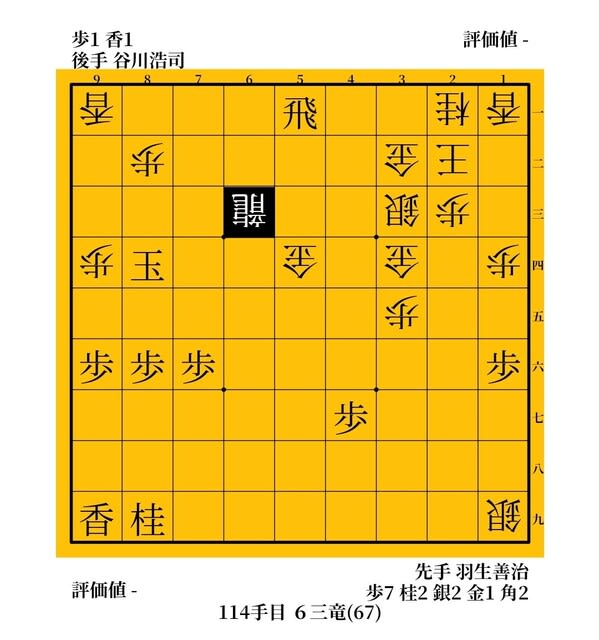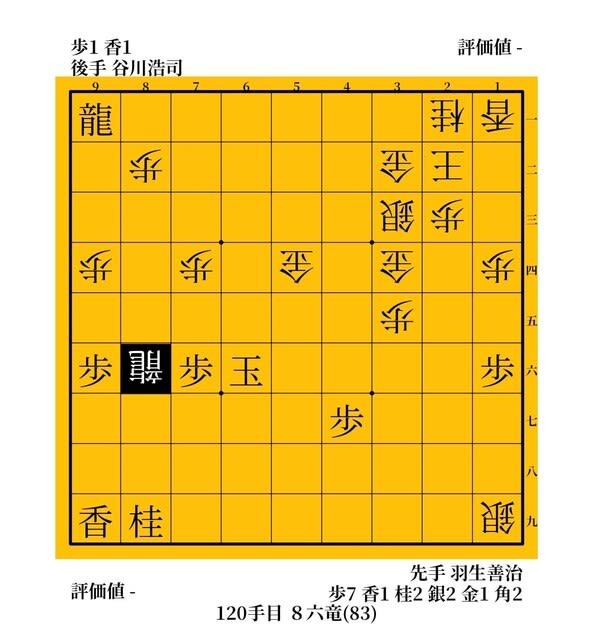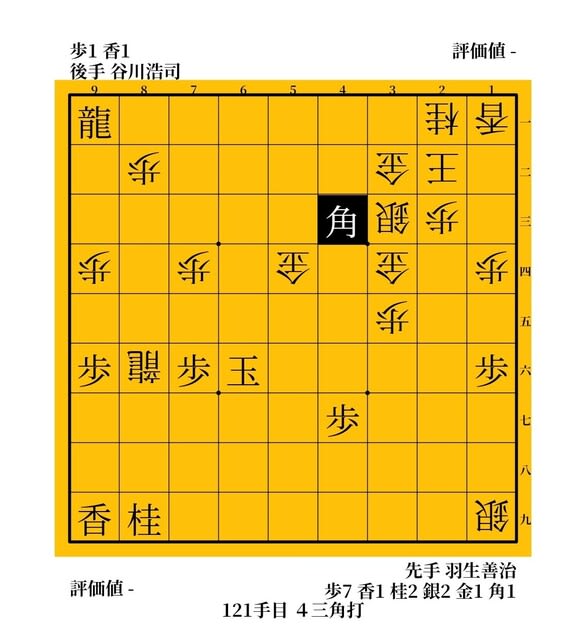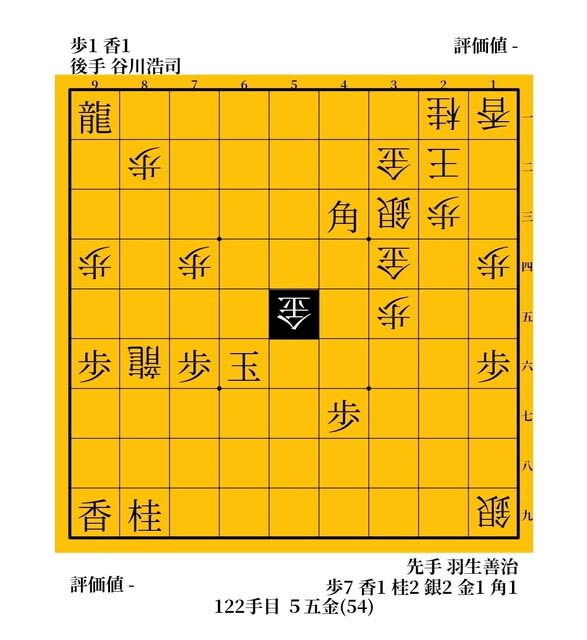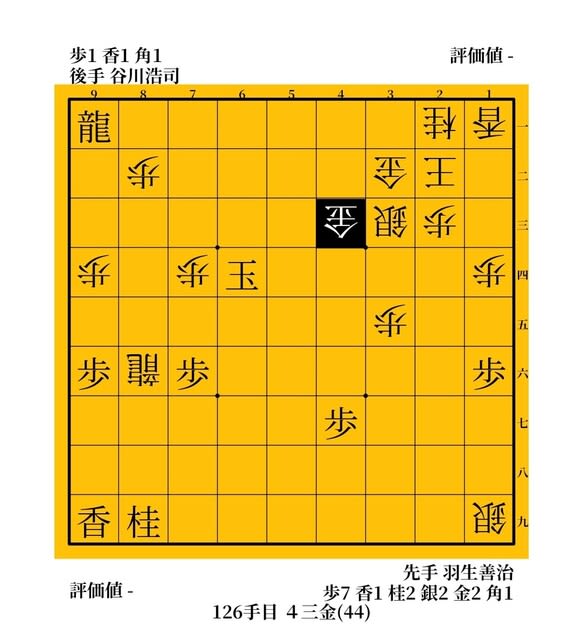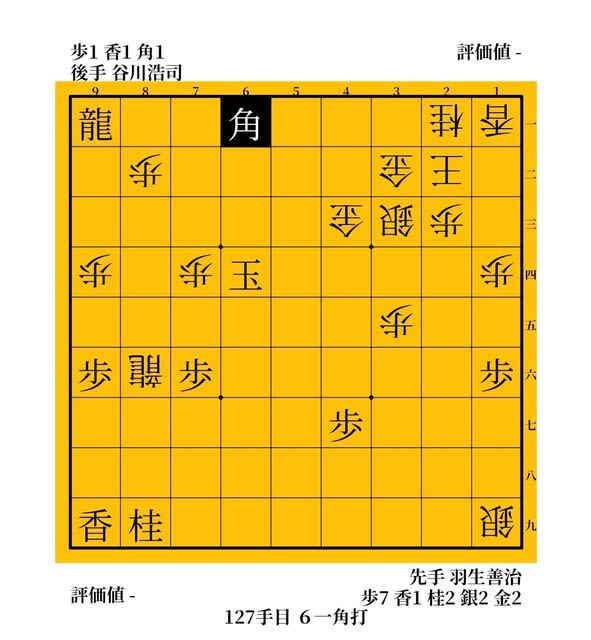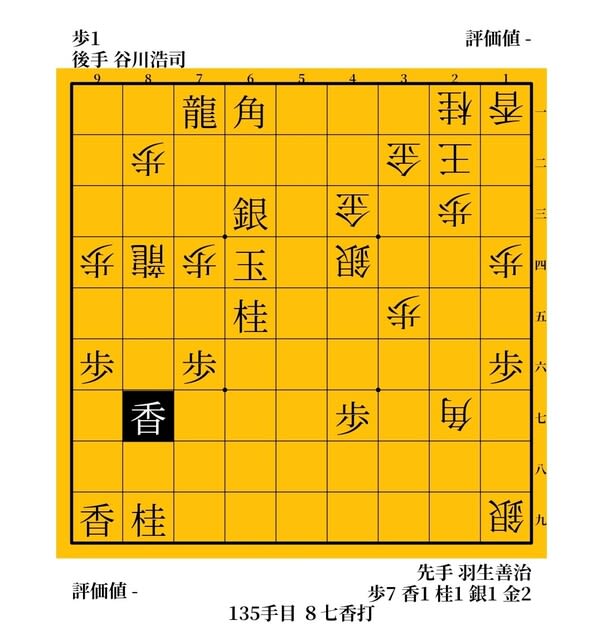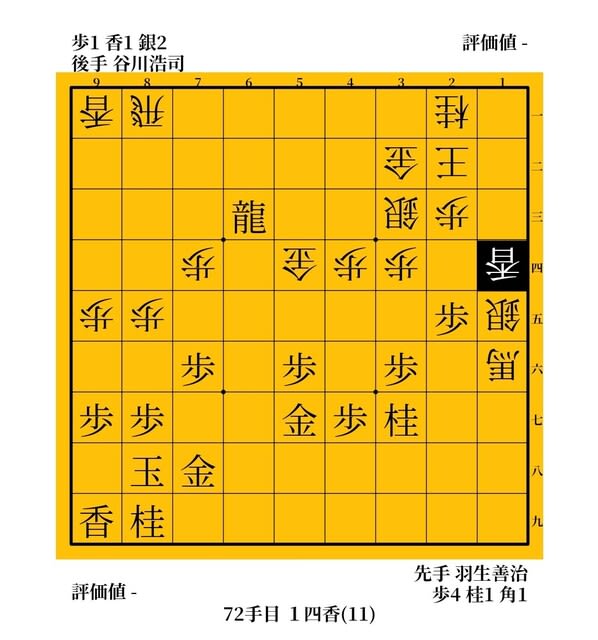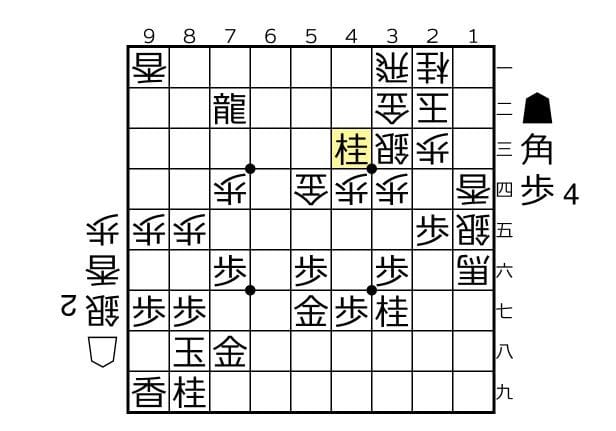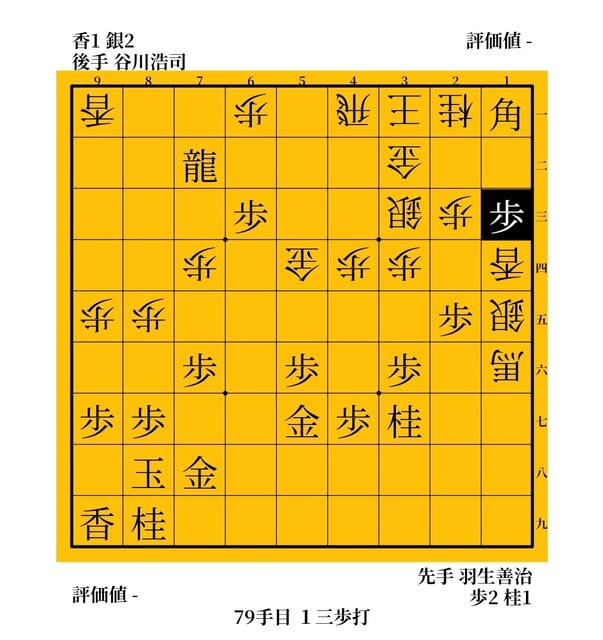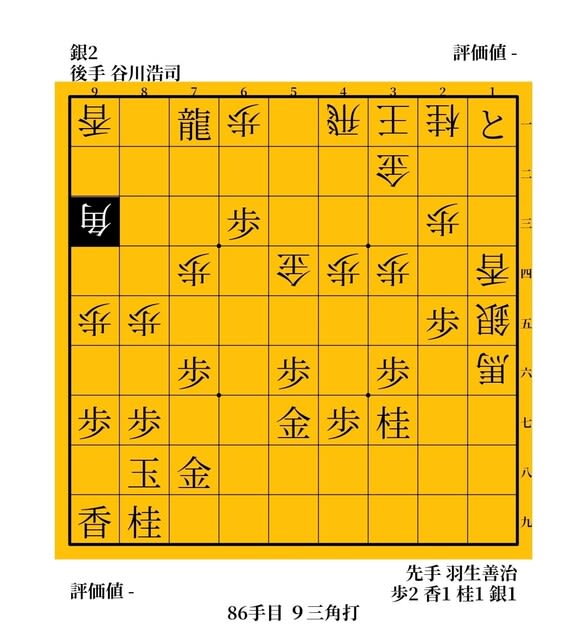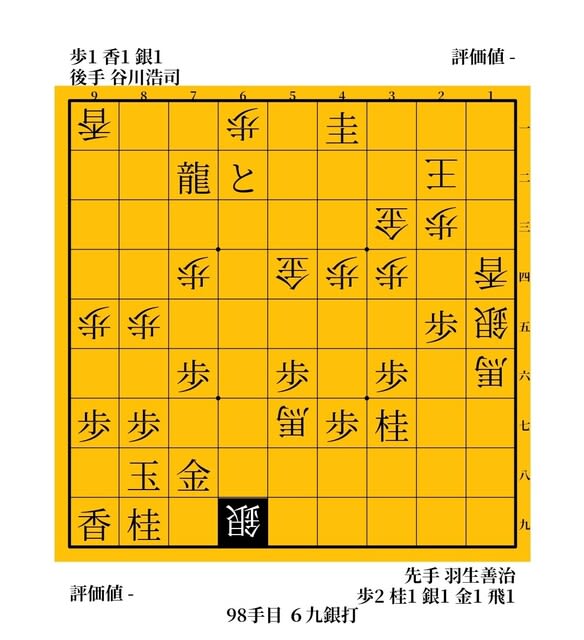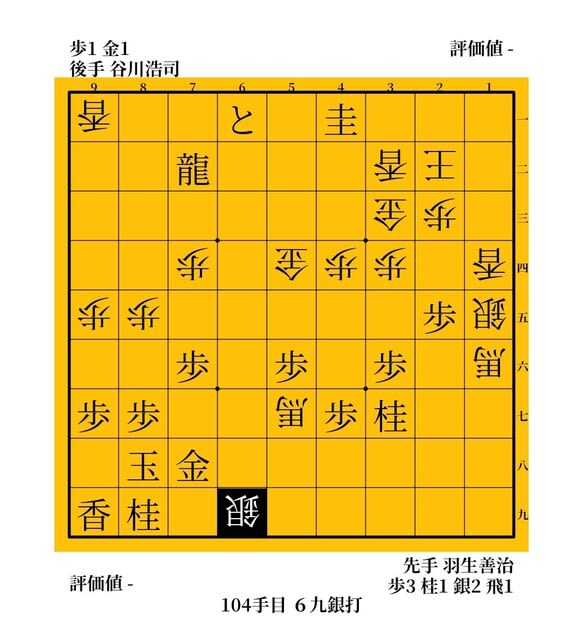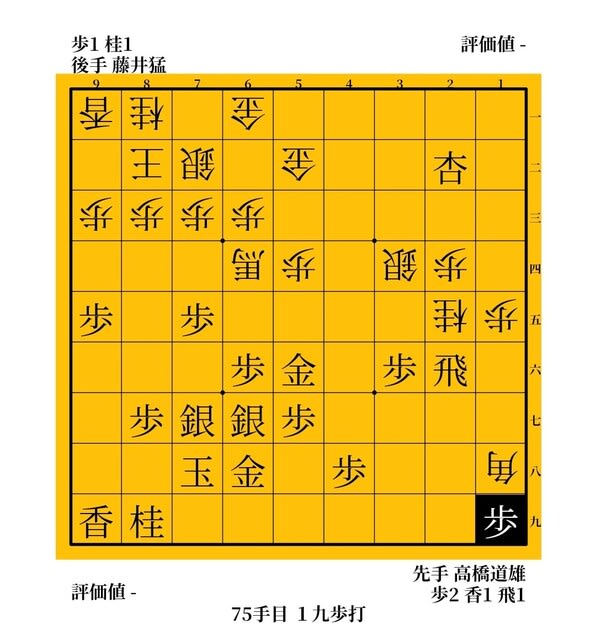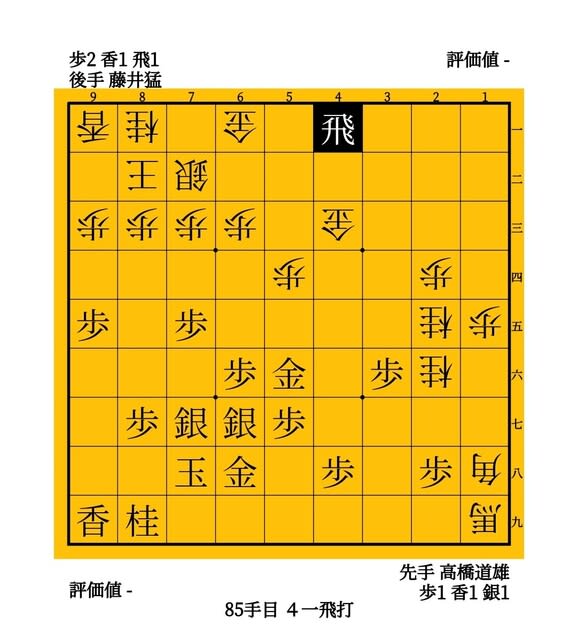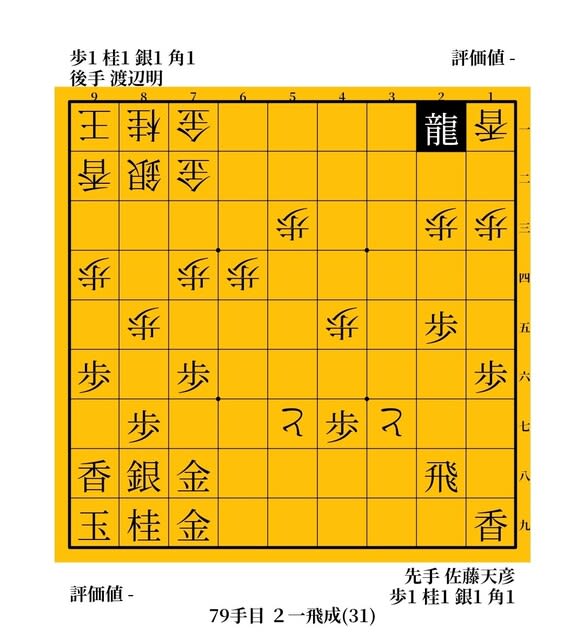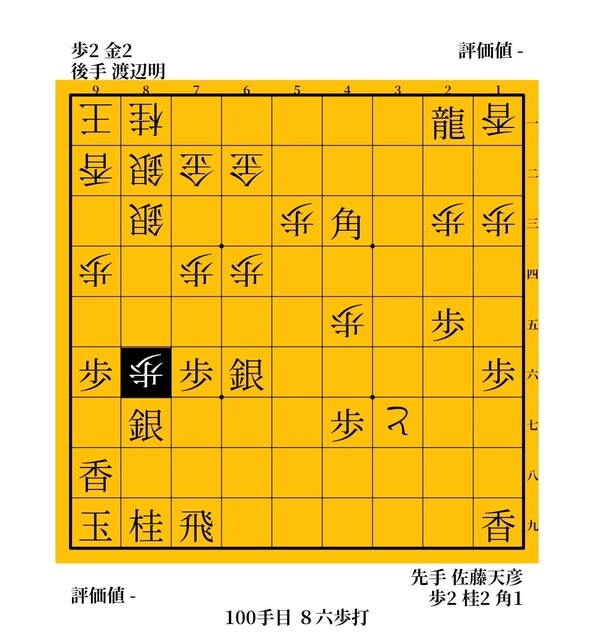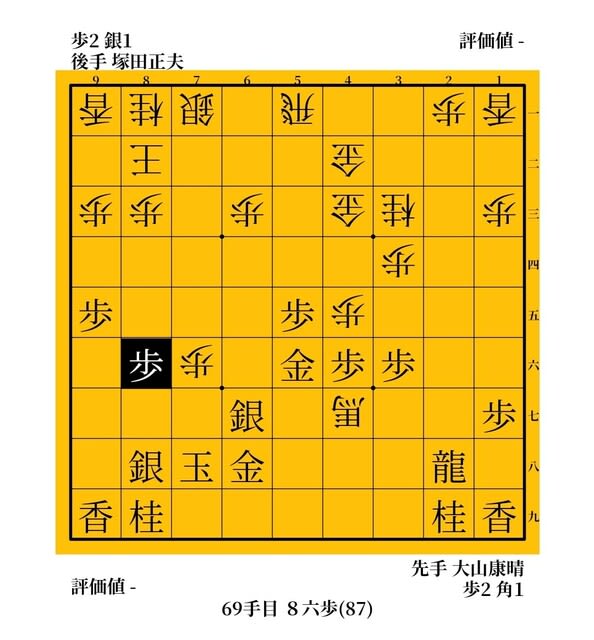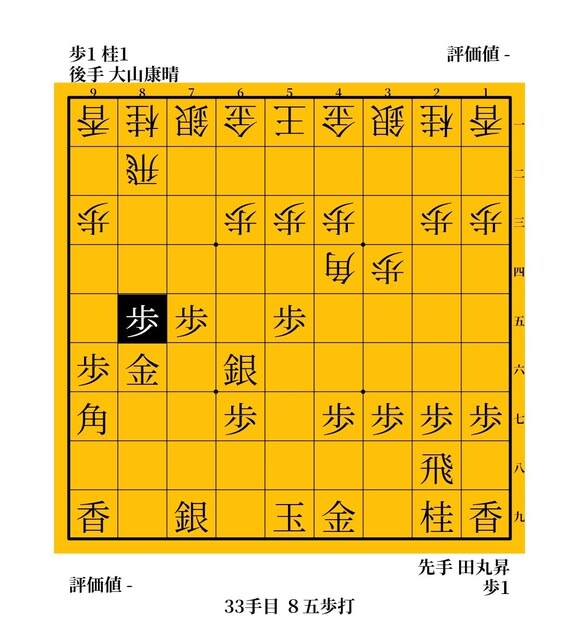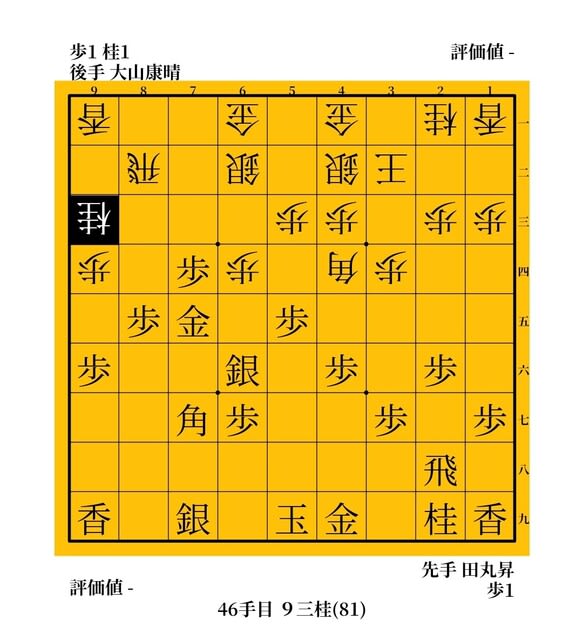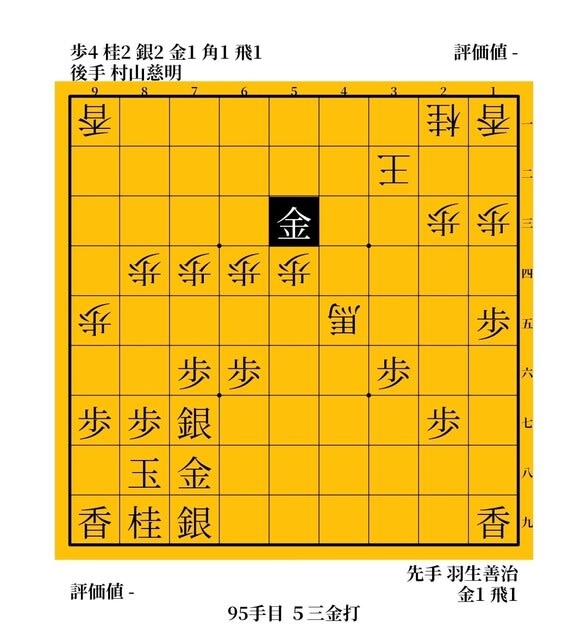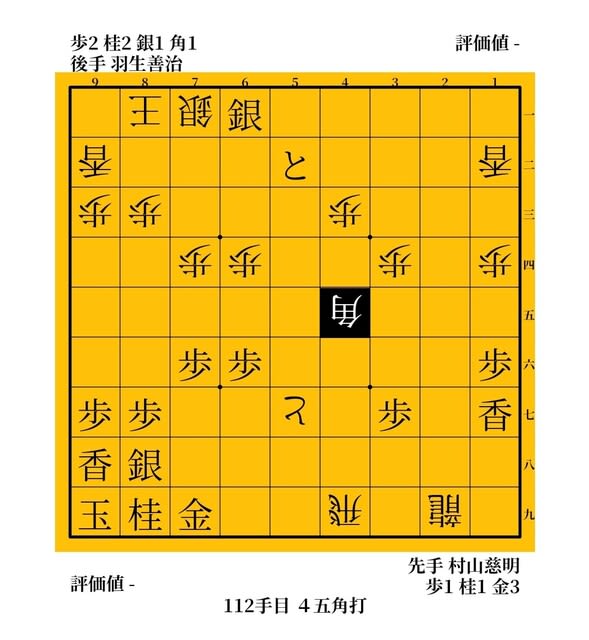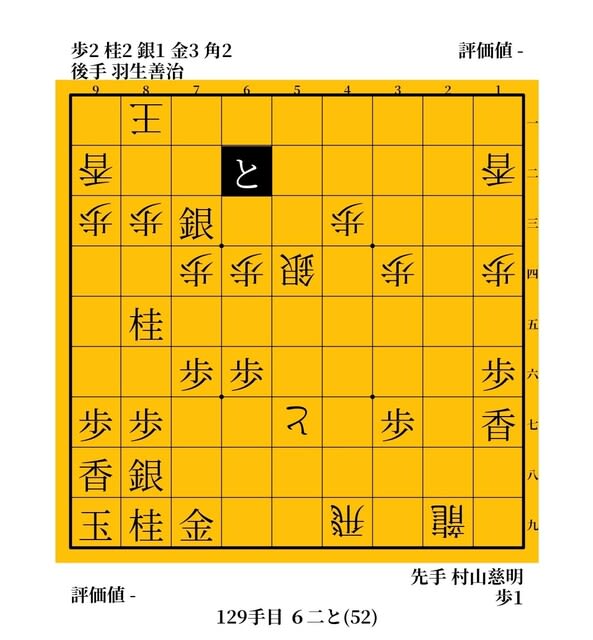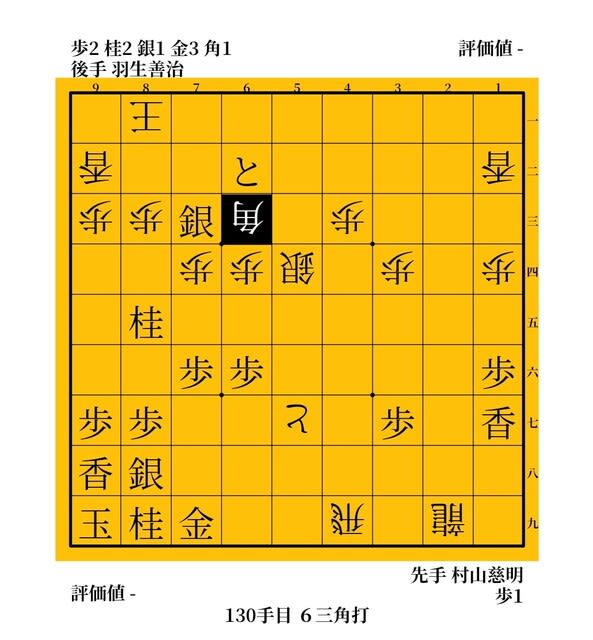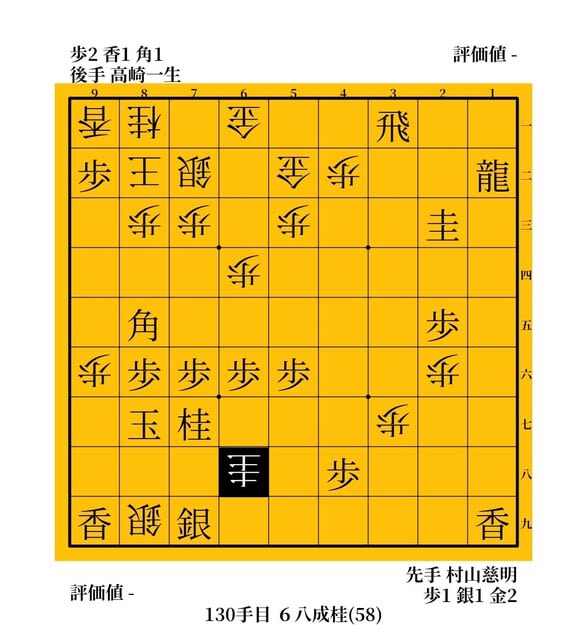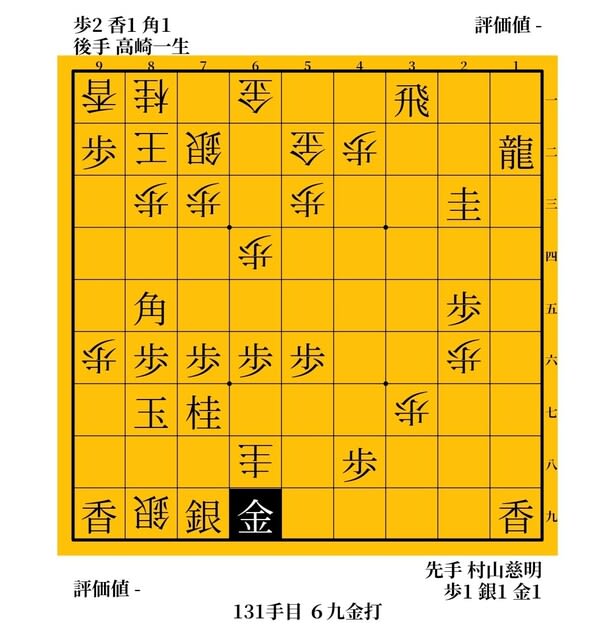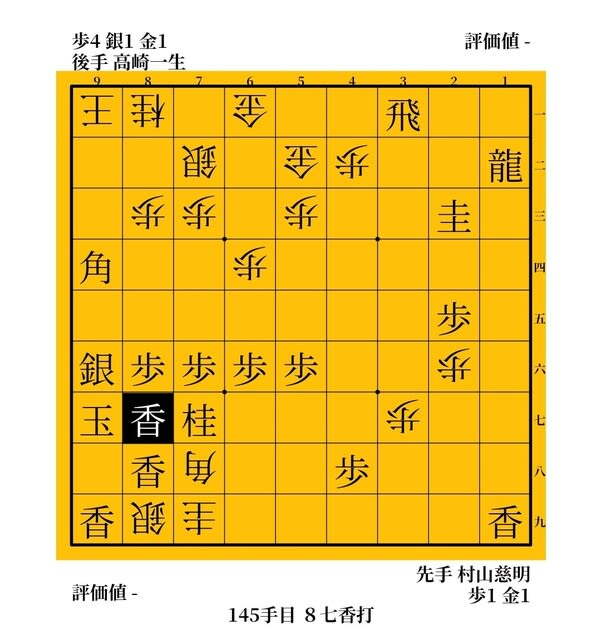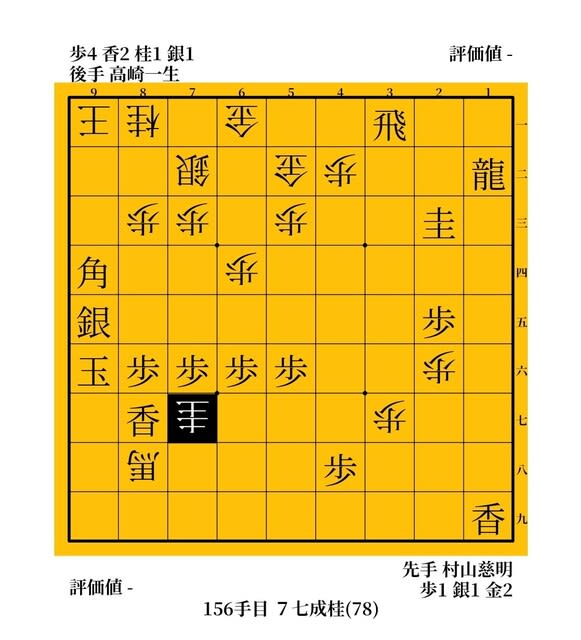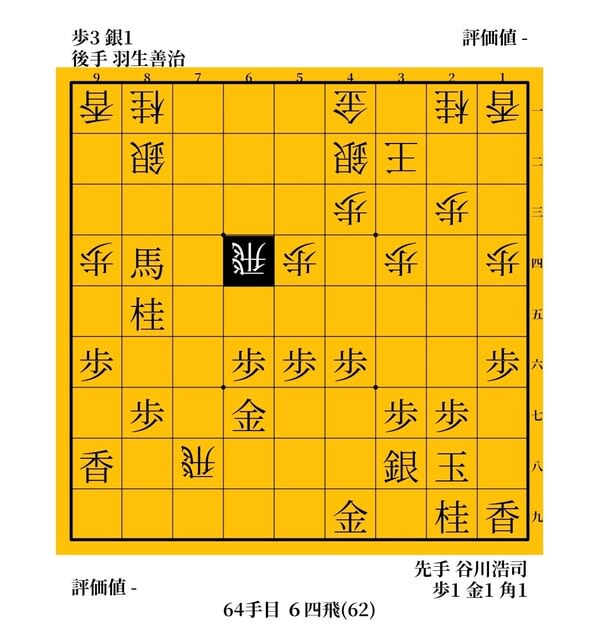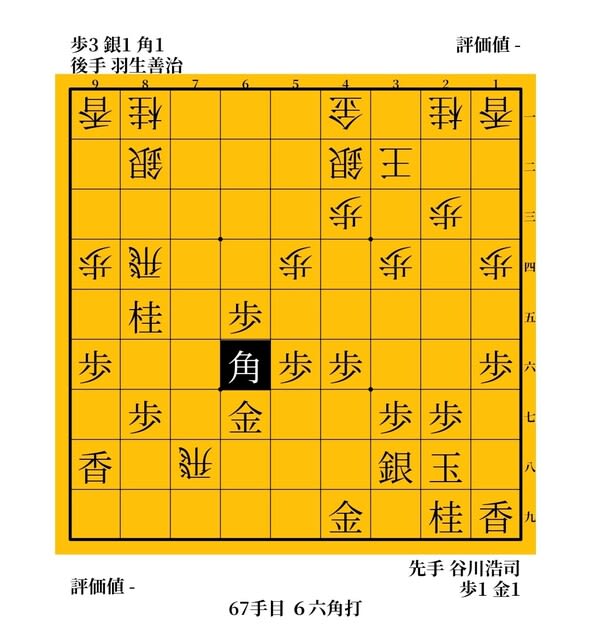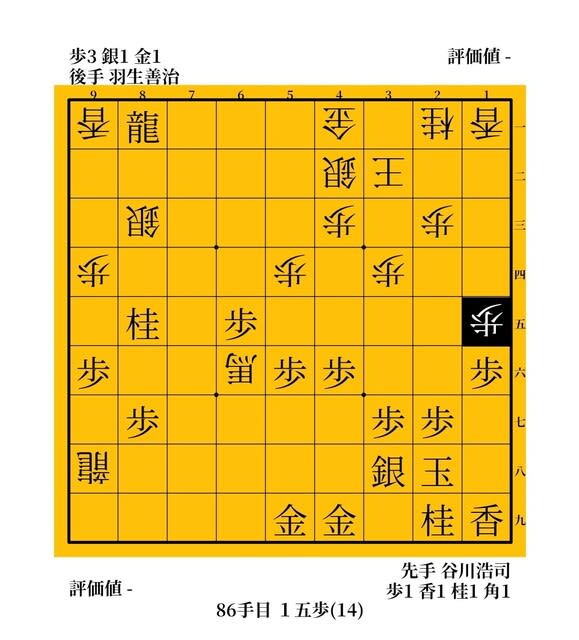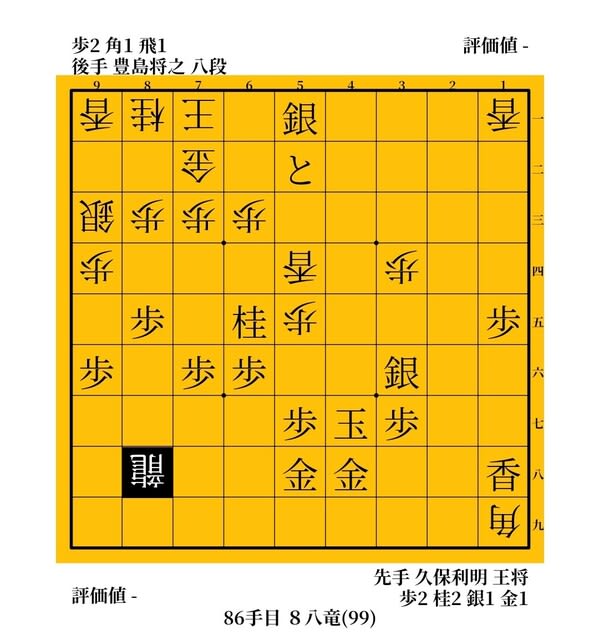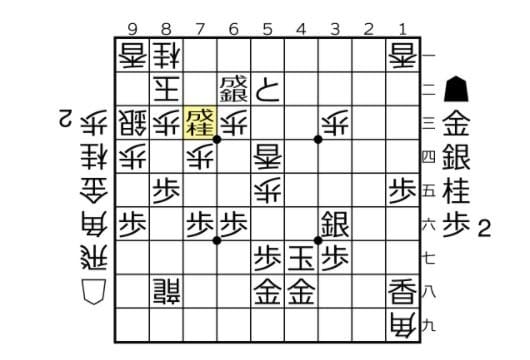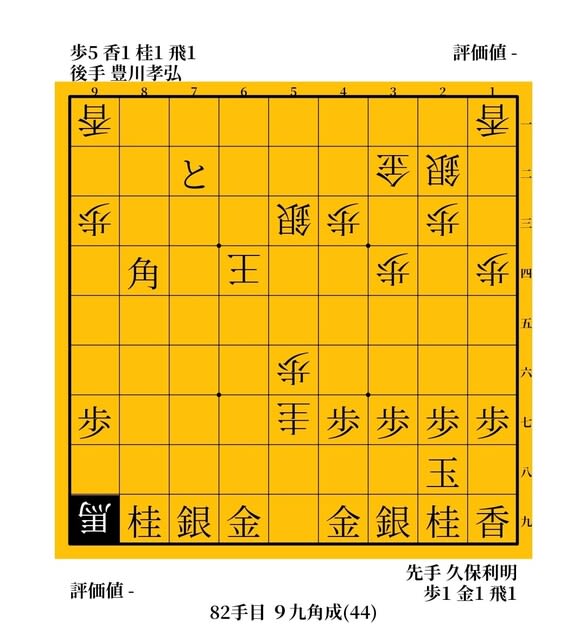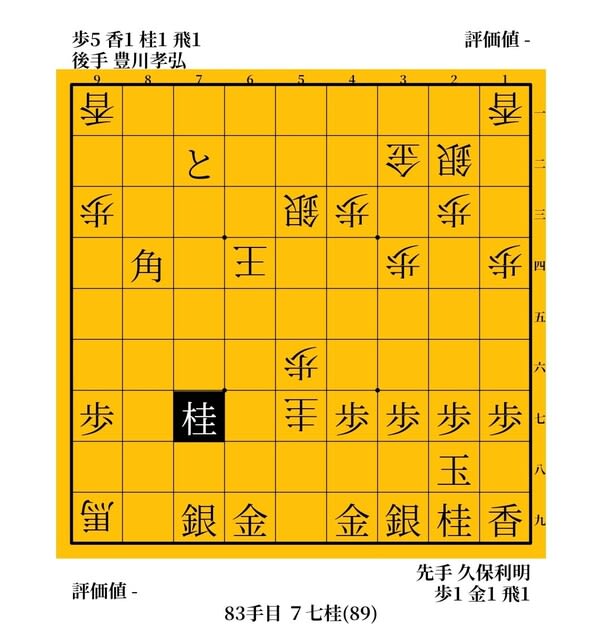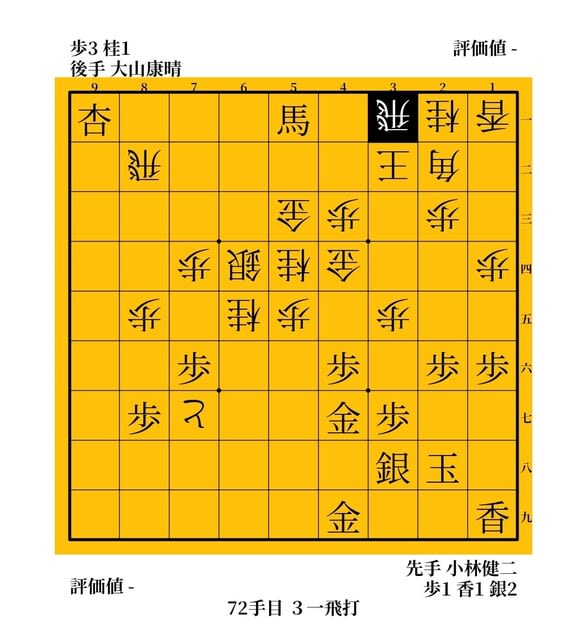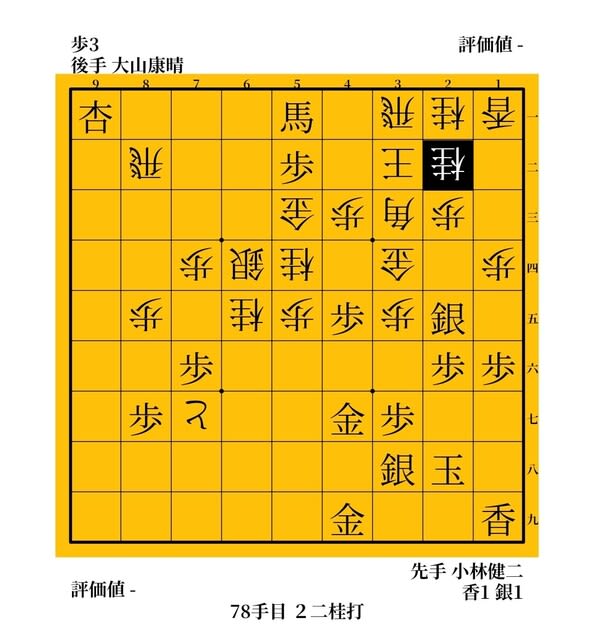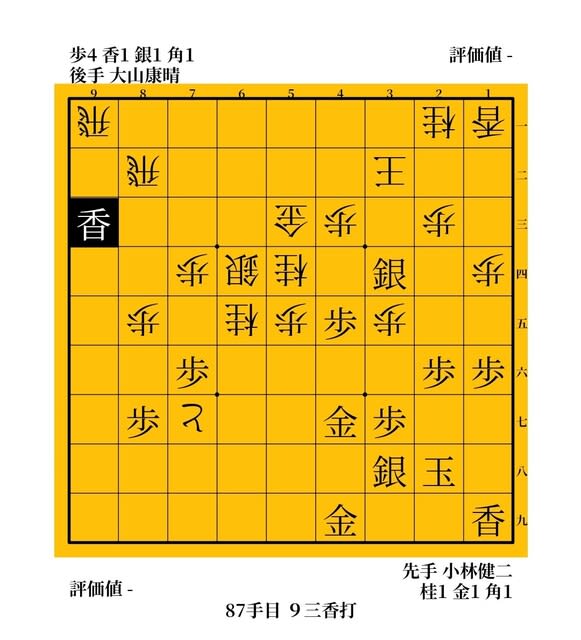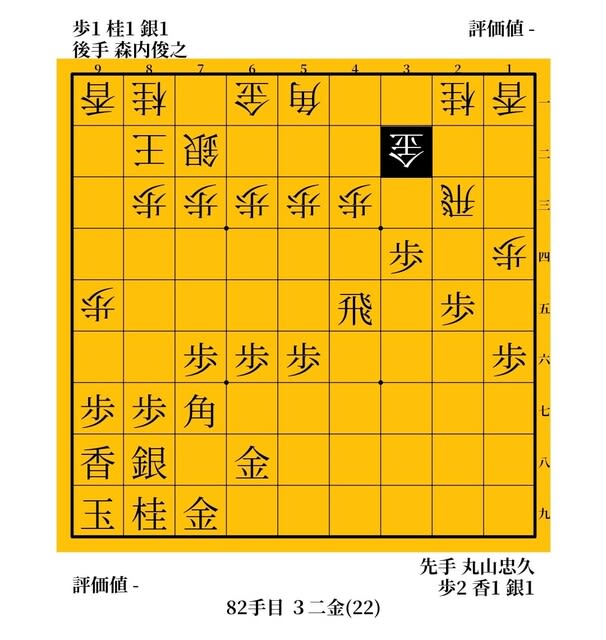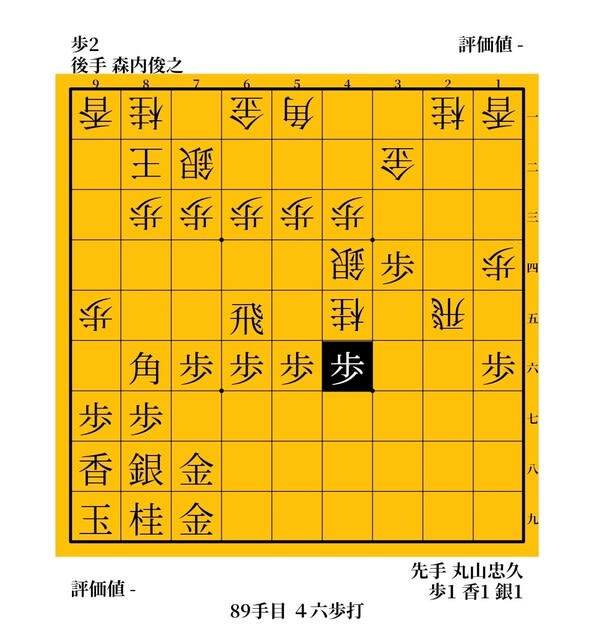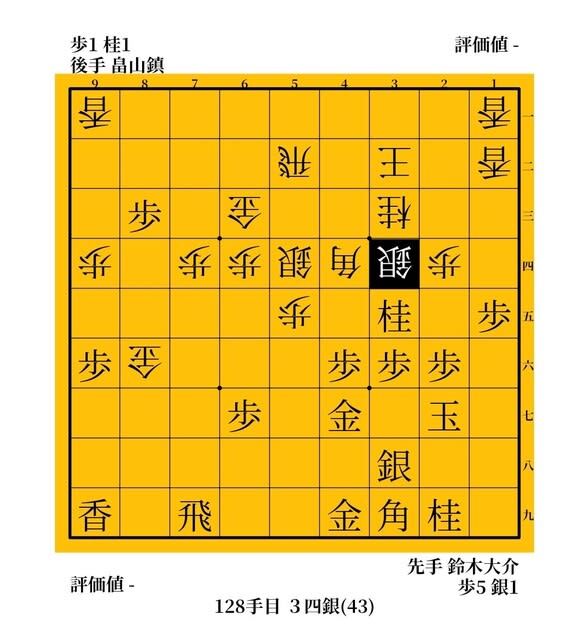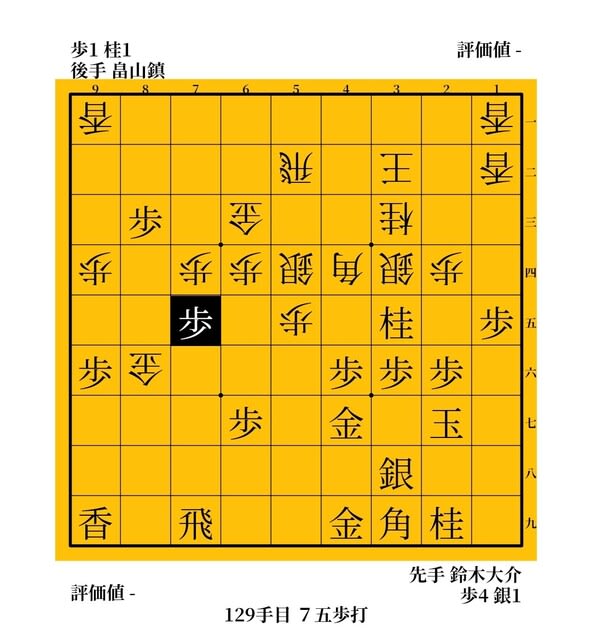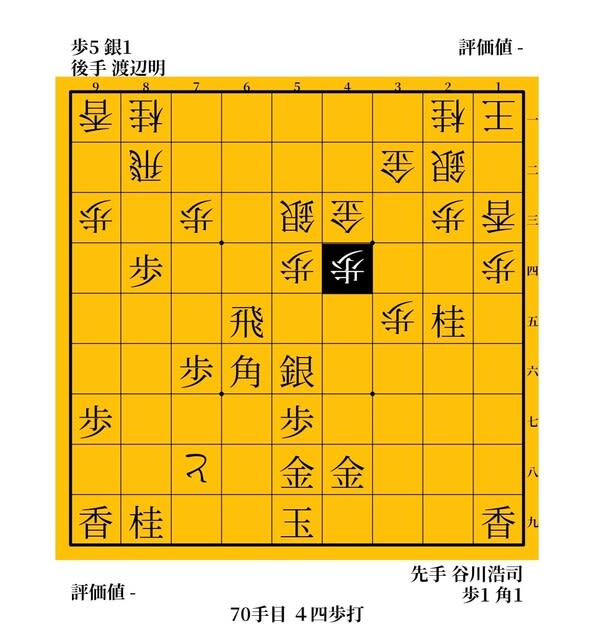「助からないと思っても助かっている」
と言ったのは、受けの達人で鳴らした大山康晴十五世名人であった。
もちろん、私のような素人レベルなら、助かっているのは、ほぼ「たまたま」の産物だが、これが達人の粋になると、
「助からないと思っても(全部読み筋だから余裕で)助かっている」
というケースもあり、その強さに感嘆することになる。
前回は「受ける青春」中村修九段の見事なしのぎを紹介したが(→こちら)、今回もまた、すばらしい受けの手を。
1987年の第46期A級順位戦。
谷川浩司王位と森雞二九段の一戦。
後手番になった森の四間飛車から、相穴熊戦に。
森が仕掛けて、激しい攻め合いになり、むかえたこの局面。

後手が△79同竜とせまったところ。
この局面を一目見て、「どちら持ちたいか」アンケートを取ったら、どういう結果になるだろう。
まあまあの人が「後手」をクリックするではあるまいか。
先手陣は▲11の馬がいるから△88銀みたいな手はないけど、その代わりに、一路上の△87桂と打つ筋があって詰む。
形は竜に当てて▲88銀だが、△78金と打って、▲79銀と取れば△87桂と吊るして詰み。
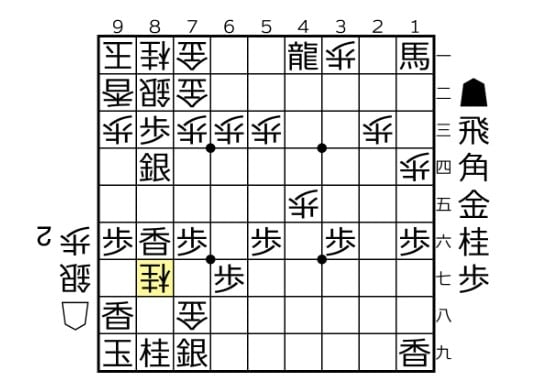
▲88金も、△87桂、▲同金、△78金、▲88馬、△同金、▲同金に△87歩と叩く。

▲同金に△78銀とか自然に攻めていけば、いずれ受けがなくなる。
とにかく先手は▲87の地点が開いてるのと、そこに敵の歩が立つのが痛すぎる。
さらには後手の持駒も豊富で、玉は絶対詰まない「ゼット」となれば、万策尽きているようにしか見えないのだ。
ところがここで、うまいしのぎがあった。
「光速の寄せ」が見せた、盤上この一手の受けとは……。
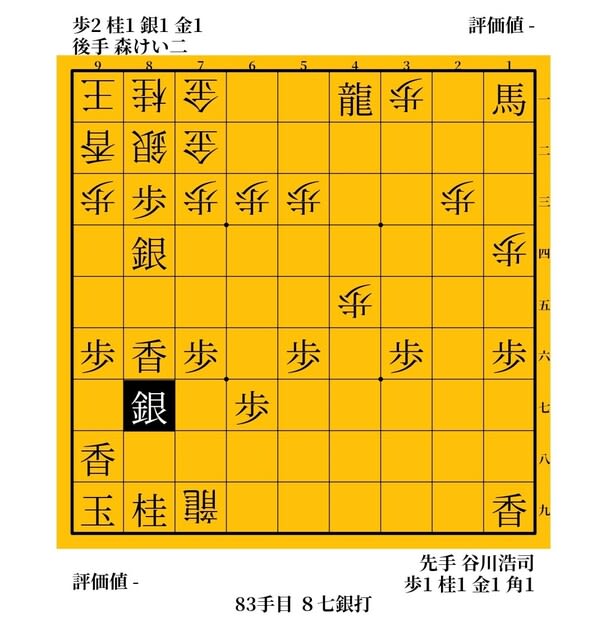
▲87銀と、ここに打つのがうまい手。
この一見フワッとした銀打で、信じられないことに、後手からこれ以上の手がない。
△87桂を防がれたうえに、▲11の馬が▲88と▲77に利いており、どのように手をつなげても、一手負けは必至なのだ。
森は△78銀と食いつくが、▲同銀、△同竜に▲88金とハジく。
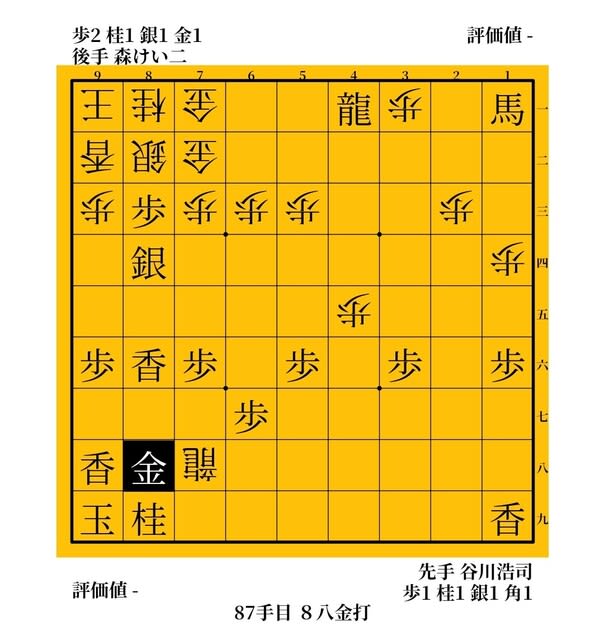
このとき竜が△79なら前述の△87桂、▲同金、△78金で寄りだが、この形だと竜がいるから△78金と打てない。
ゆえに、△87桂、▲同金には△同竜しかないが、これが一手スキになっておらず(▲11の馬を見よ!)、▲82歩成、△同金上、▲83歩が間に合う仕掛け。

 メチャクチャに迫られてる先手玉だが、とにかく馬の超長距離迎撃ミサイルが強力すぎて、どうあがいても詰みがない。
メチャクチャに迫られてる先手玉だが、とにかく馬の超長距離迎撃ミサイルが強力すぎて、どうあがいても詰みがない。
▲11から▲88へのラインが美しすぎて、後手からすれば、本当に心がなえる局面ではないか。
以下、△78金と一手スキをかけても、▲82歩成、△同金、▲83桂、△同金、▲81竜、△同玉、▲72銀から追っていけば詰む。
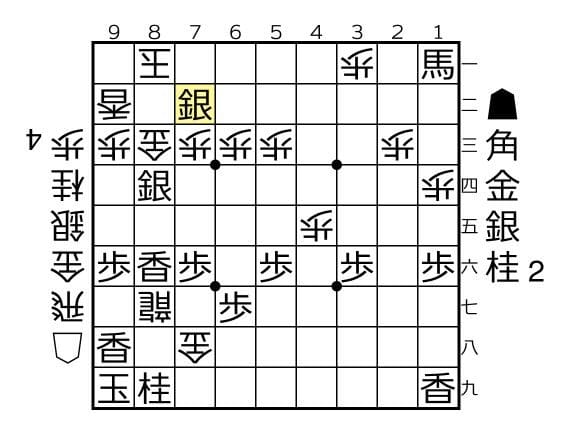
まさに、計算されつくした一手勝ち。
受けの妙手に続いて今度は「光速の寄せ」の合わせ技ときては、さしもの「終盤の魔術師」森雞二もまいった。
動きの取れない後手は△86竜と香を取ってねばるが、▲82歩成、△同金、▲75銀打が手厚い手で先手勝ち。

「前進流」と呼ばれる谷川浩司だが、受けだって見事なもの。
まさに「助からないと思っても余裕で助かっている」という、強すぎる終盤力なのだ。
(「大山康晴引退」をかけた伝説に続く→こちら)