2018年が始まりました。
12月31日は 「大祓い」 で1年のけがれを綺麗に洗い落し、新年を迎える。これは各神社でやる重要な行事。
そして、1月1日は 「歳旦祭」で歳の初めに五穀豊穣、国民の福祉安寧を皇祖・天神地祇に祈る行事である。
そこで一句
おお祓い 歳旦祭や 去年今年 (年明けから、季語3つを連ねるようなへぼ句です)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
12月30日の明治神宮


新年の参拝者300万人を想定し、本堂の前に幅50m奥行25mの真っ白な 賽銭プール が拵えてあった。
明治神宮に行く途中で、国立競技場のオリンピックに向けての工事進捗状況


隣の神宮スケート場

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1月1日 の散歩に初詣しました。
1、住吉神社
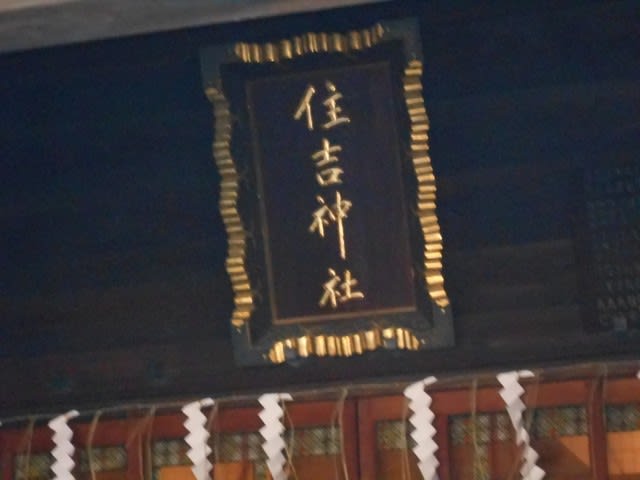

江戸時代の初期の地図には、隅田川の水の中にぽかり浮いている神社の絵がある。これが住吉神社だ。家康入部のころ、摂津の佃島の漁民を江戸につれてきた。彼らの本尊 住吉大社を分祭したのであろう。 その後隅田川の中州で時々顔を出すあたりを、大々的に埋め立て、いまの月島ができた。築島が本礼の言葉。 その後石川なんとかさんが所領し、石川島となり、寄せ場になったり、監獄になったり、石川島造船所になったり、江戸の260年は長いのだ。
2、隅田川を渡って 鉄砲洲神社にお参り



地元の小さな神社だからこじんまりでいいね。茅野輪 をくぐり、富士講の跡が残っているのもうれしいね。
幕末にこの辺りから、聖路加病院あたりが、外国人居住区になっていった。建前の尊王攘夷を言いながら、なし崩しに外国との交流を進めた幕府の知恵者が居たのだろう。
3、築地本願寺にお参りに行く。浄土真宗のお寺でも正月は、多くはないがお参りに来ていました。


本堂の内部は席が空いていた。
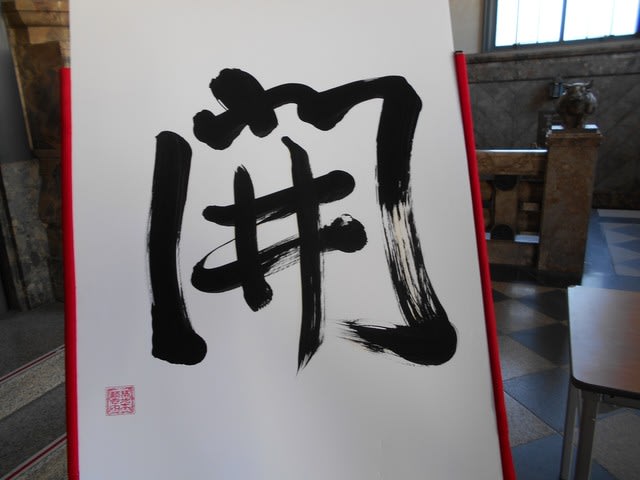
今年の 言葉 ですって。 京都清水寺では 「北」だったが、本願寺の 「開」の方がありがたみがあるね。
4、築地場外市場の先の 波除稲荷神社



場所柄、参拝客が多く、50人ぐらいはいたね。それより正月1日から営業している店があり、外国人や日本人も群がっていたね。多くは1月5日まで休みと書いてあったが。
こうじて、新年の散歩 約1万1千歩を歩きました。
このあと、一家で雑煮を食べて コゾ コトシ(去年今年)を過ごしました。
新聞とTVをみることを控えれば随分充実した生活となります。
皆様も、今年1年 息災であられますように。
私も 去年は 姉夫婦の同時死亡や、自分のネフローゼ症での入院騒ぎがありました。
本当に、一寸先は闇 無常迅速。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
12月31日は 「大祓い」 で1年のけがれを綺麗に洗い落し、新年を迎える。これは各神社でやる重要な行事。
そして、1月1日は 「歳旦祭」で歳の初めに五穀豊穣、国民の福祉安寧を皇祖・天神地祇に祈る行事である。
そこで一句
おお祓い 歳旦祭や 去年今年 (年明けから、季語3つを連ねるようなへぼ句です)
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
12月30日の明治神宮


新年の参拝者300万人を想定し、本堂の前に幅50m奥行25mの真っ白な 賽銭プール が拵えてあった。
明治神宮に行く途中で、国立競技場のオリンピックに向けての工事進捗状況


隣の神宮スケート場

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
1月1日 の散歩に初詣しました。
1、住吉神社
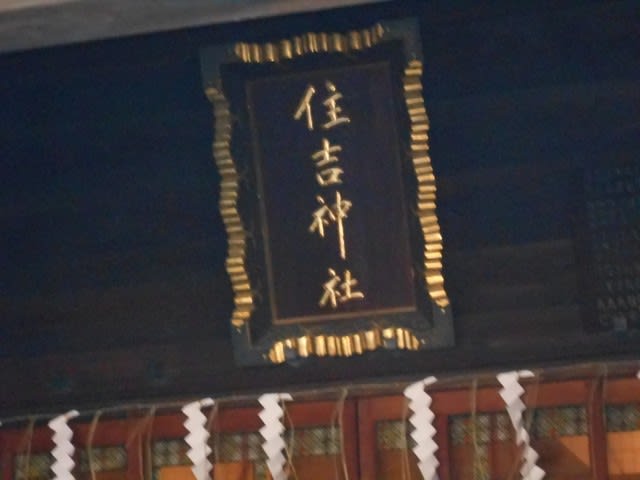

江戸時代の初期の地図には、隅田川の水の中にぽかり浮いている神社の絵がある。これが住吉神社だ。家康入部のころ、摂津の佃島の漁民を江戸につれてきた。彼らの本尊 住吉大社を分祭したのであろう。 その後隅田川の中州で時々顔を出すあたりを、大々的に埋め立て、いまの月島ができた。築島が本礼の言葉。 その後石川なんとかさんが所領し、石川島となり、寄せ場になったり、監獄になったり、石川島造船所になったり、江戸の260年は長いのだ。
2、隅田川を渡って 鉄砲洲神社にお参り



地元の小さな神社だからこじんまりでいいね。茅野輪 をくぐり、富士講の跡が残っているのもうれしいね。
幕末にこの辺りから、聖路加病院あたりが、外国人居住区になっていった。建前の尊王攘夷を言いながら、なし崩しに外国との交流を進めた幕府の知恵者が居たのだろう。
3、築地本願寺にお参りに行く。浄土真宗のお寺でも正月は、多くはないがお参りに来ていました。


本堂の内部は席が空いていた。
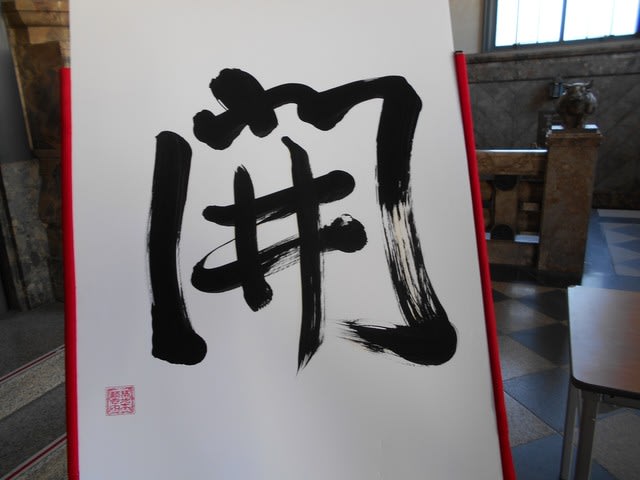
今年の 言葉 ですって。 京都清水寺では 「北」だったが、本願寺の 「開」の方がありがたみがあるね。
4、築地場外市場の先の 波除稲荷神社



場所柄、参拝客が多く、50人ぐらいはいたね。それより正月1日から営業している店があり、外国人や日本人も群がっていたね。多くは1月5日まで休みと書いてあったが。
こうじて、新年の散歩 約1万1千歩を歩きました。
このあと、一家で雑煮を食べて コゾ コトシ(去年今年)を過ごしました。
新聞とTVをみることを控えれば随分充実した生活となります。
皆様も、今年1年 息災であられますように。
私も 去年は 姉夫婦の同時死亡や、自分のネフローゼ症での入院騒ぎがありました。
本当に、一寸先は闇 無常迅速。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。









