名落語家の古典噺を聞くような

田坂具隆が監督したこの映画は、山本周五郎の三つの短編を集め、それぞれを独立した形で描いていますが、トータルとしては江戸時代を描いた周五郎の世界が堪能できるように構成されています。これはオムニバスと呼ばれる映画の形式の一つです。
当時の東映の大スター中村錦之助(後の萬屋錦之介)がそれぞれの話の主役を演じ、一人で三役を務めています。旗本の四男坊に生まれた若侍が、趣味の古書収集から幸運に恵まれる第1話「冷飯」。ここでは世間知らずで甘えん坊だが、真っ直ぐな気性を持った男を演じています。妻の不貞を疑い、上方へ逃げ出た大工が、女房恋しさに江戸に戻って来たが…という第2話「おさん」では、少しやさぐれた男の魅力を発揮します。子沢山の貧しい火鉢職人を演じた第3話の「ちゃん」では、腕はいいが、昔気質で生き方が下手な職人を演じています。それぞれが性格の異なる役柄ですが彼は見事に演じ分けています。
加えて、藤原釜足、小沢昭一、千秋実、花沢徳衛、佐藤慶、大坂志郎、北村和夫、三木のり平…、各編で別々の俳優が錦之助と絡み適材適所で名演を見せてくれます。これはかっての日本映画が豊かで豪華な俳優たちを持っていた証です。また「冷飯」の母親役の木暮実千代、「おさん」の三田佳子と新珠三千代、「ちゃん」の女房・森光子と飲み屋の女将の渡辺美佐子、と女優たちがとてもいいです。
そして「冷飯」のユーモア、「おさん」の物悲しさ、「ちゃん」の人情話と見てくると、名落語家の古典噺を聞いたような感じがしてうれしくなってきます。原作・山本周五郎、監督・田坂具隆、脚色・鈴木尚之、主演・中村錦之助のチームは、もう一本『ちいさこべ』(62)という江戸時代の大工の棟梁を主人公にした佳作を作っています。こちらもぜひどうぞ。
『赤ひげ』(65)

黒澤明は山本周五郎の大ファン
黒澤明監督が山本周五郎の『赤ひげ診療譚』を映画化しました。江戸時代、長崎帰りの青年医師・保本(加山雄三)は、親の勧めから小石川療養所で働くことに。彼はそこで出会った「赤ひげ」の異名を持つ名医の新出(三船敏郎)に感化され、医者として本道に目覚めていきます。
黒澤は、複数の物語を描いた短編集を、共同脚本の小国英雄、菊島隆三、井手雅人と共に、小石川養生所とむじな長屋の群像劇に集約し、若く未熟な医師の目を通して描く連続性を持った話にしました。同じく周五郎の原作を映画化し、同年に公開された田坂具隆監督の『冷飯とおさんとちゃん』とは異なるアプローチがなされています。このあたり、それぞれの監督の個性が垣間見えるようで面白いです。
黒澤は、養生所や長屋の巨大なセットを組み、雨といえば大雨、雪といえば大雪を降らせ、風鈴といえばたくさんの風鈴を一斉に鳴らしたりもします。ハイドンを思わせると評された佐藤勝の音楽も大いに効果を発揮し、貧乏を扱った映画なのに全体的には大作の風格が漂います。また、ヒューマニズムにこだわった黒澤映画の集大成ともいわれ、事実、三船敏郎との名コンビもこれが最終作となりました。
黒澤は周五郎の大ファンで、『赤ひげ』以前には、周五郎の『日々平安』を『椿三十郎』(62)として映画化し、『赤ひげ』以後も、『季節のない街』を『どですかでん』(70)として映画化しています。『日々平安』の主人公の侍は映画の三十郎のような剣豪ではありませんし、黒澤もできれば原作通りに描きたかったといいます。
そして黒澤の遺稿脚本は、後に黒澤組のスタッフが映画化した周五郎の『雨あがる』(00)でした。黒澤は、強い人間ばかりでなく、周五郎が描くような弱さやはかなさを持った市井の人々をもっと描きたかったのでしょう。

『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』は試写で見たのだが、ちゃんと大画面で見直してみようと思い、妻と共にTOHOシネマズ六本木ヒルズへ。
ここはドルビーアトモス方式で上映している。専門的なことはよく分からないが、要は音がいいということだ。
ロング・アゴ―。ドルビーステレオ・サラウンドで上映された『地獄の黙示録』(79)を見た時に、ヘリコプターの音が背後から聴こえてきて驚いた覚えがある。
今は“凄い音”にもすっかり慣れてしまったので、今回も特別な驚きはなかったが、目を閉じ、耳を澄ませてエンドクレジットのジョン・ウィリアムス作曲の音楽に酔いしれた。もっと音楽を聴きたかった気もする。
ところで、妻は体感型のMX4Dを体験してみたいと言い、前日もTOHOシネマズ ららぽーと船橋で鑑賞している。
ロング・ロング・アゴ―。地震を疑似体験する音響効果センサラウンド方式を採用した『大地震』(74)を見たが、今から思えば子供だましみたいなものだった。
未体験のMX4Dは、恐らくセンサラウンドの比ではないのだろうが、アクションシーンのたびに椅子が動くのでは落ち着かないのではあるまいかと想像する。激しく揺れる画面を見ると手振れ酔いを起こすぐらいだから自分にはきついのではないかと思う。
さて、今回の『~フォースの覚醒』は旧三部作へのオマージュたっぷりで、オールドファンにはたまらないものがあるが、裏を返せば旧三部作の出来のいいパロディに見えなくもない。
今度の3部作の主役は、身のこなしが良く、若さが魅力のデイジー・リドリー演じるレイだが、この映画の“裏主役”がハリソン・フォードのハン・ソロだったように、2作目と3作目はマーク・ハミルのルークとキャリー・フィッシャーのレイアが裏主役となり、それぞれがスター・ウォーズに決着を着けていくのでは…などと想像してしまう。
いずれにせよ、今回の我が家のスター・ウォーズ祭りはこれにて終了。
『南の島に雪が降る』(61)

俳優たちの至芸が見もの
この映画は、昭和19年から終戦までニューギニアの戦地で演劇活動を続けた俳優の加東大介が、自らの戦争体験を綴った小説を映画化したもので本人が主演しています。監督は久松静児です。
加東といえば、『七人の侍』(54)や『用心棒』(61)といった黒澤明監督作品から、喜劇「社長シリーズ」まで、シリアスとコメディの両方で幅広く活躍した名優です。その人がこんな過酷な体験をしていたのかと思うと胸が痛みます。
すでに日本の敗色が濃厚となったこの時期、飢餓とマラリヤの恐怖の中で日々を送る兵士たちの唯一の慰めは、演芸分隊が催す芝居の数々だったのです。
タイトルは、長谷川伸原作の舞台「瞼の母」のクライマックスで「南の島に雪を降らせる」という苦心の跡から取られていますが、紙の雪に感動して涙を流しながら死んでいく兵士を見た加東が「紙じゃねえか。こんなもんただの紙じゃねえか」と悔しそうに涙するシーンが切ないです。
この映画は、戦争の意味や、演劇の素晴らしさ、あるいは人間にとっての生きがいとは、などといろいろと考えさせてくれますが、それとは別に、多彩な俳優たちが見せる芝居が見ものです。
加東本人はもちろん、有島一郎、三木のり平、渥美清、伴淳三郎、森繁久彌、小林桂樹、西村晃、織田政雄、フランキー堺…。
彼らの至芸を見るだけでも一見の価値があります。
『三大怪獣 地球最大の決戦』(64)(1971.12.12.浅草東宝)

荒唐無稽な関沢新一の脚本
この映画は、ゴジラ、モスラ、ラドンという既成の怪獣に加えて、三つ首の宇宙怪獣キングギドラが初登場した作品です。
監督の本多猪四郎の演出、特技監督の円谷英二を中心とした特撮が素晴らしいのはもちろんですが、忘れてはならないのが脚本の関沢新一の存在です。
ゴジラの身長が50メートルという設定に対しキングギドラは何と100メートル。これではゴジラ一匹ではとてもかないません。そこでキングギドラを倒すためにモスラの説得でゴジラとラドンが共闘するという力業を発揮します。
また、ドラマ部分でも『ローマの休日』(54)を下敷きに、某国の王女に金星人が乗り移るというすさまじい技を繰り出します。王女を『007は二度死ぬ』(67)でボンドガールになった若林映子が演じています。
荒唐無稽という言葉は、まさに関沢脚本にぴったりの言葉ですが、これが理屈抜きに楽しいんです。平成のゴジラやガメラはどうも理屈っぽくていけません。
60年代の東宝は、加山雄三主演の「若大将」シリーズのように、都会的でしゃれた映画を得意にしていました。この映画にもそうした風情が漂っています。
ただの怪獣映画とバカにすることなく、思いっ切り60年代の雰囲気に浸って楽しんでください。
全ては愛する羊のために…

アイスランドの辺境の村に暮らす、羊飼いで独身の老兄弟グミーとキディ。彼らは、隣同士に住みながら、犬に手紙を運ばせる(兄弟の間を行き来する名犬!)などして40年間絶縁状態にある。ところが、羊が疫病に侵されたことから、ある秘密を共有することになる。全ては愛する羊のために…。
雄大かつ厳しい自然をバックに、ブラックユーモアや皮肉を盛り込みながら、少しミステリアスな話が展開される。寓話のような、神話のような不思議な味わいのある映画。知られざるアイスランドの人々の生活を垣間見るという意味では興味深いものがある。
カンヌ映画祭「ある視点」グランプリ受賞作。ヨーロッパの人はこういうちょっと変わったタイプの映画が本当に好きだよなあ。
『ほぼ週刊映画コラム』
今週は
フォースの力を自分の目で確かめよ!
『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』

詳細はこちら↓
http://tvfan.kyodo.co.jp/feature-interview/column/week-movie-c/1029223
メロドラマとホラーが見事に融合

この映画の主人公の水野(土屋嘉男)は、宇宙飛行に耐えるための人体実験で細胞が分裂し、肉体を気体(ガス)化させることが可能になります。
水野はガス人間となって銀行強盗をしますが、それは偏愛する踊りの師匠(八千草薫)に発表会をさせるための資金集めが目的でした。普通の人間には二度と戻れない彼の、屈折した愛情表現が不憫です。
観客は水野唯一人というラストの踊りの発表会も哀れを誘います。2009年には悲恋ものとして舞台化されています。
この映画は、監督の本多猪四郎と特技監督の円谷英二のコンビが生み出した、変態する(してしまう)人間たちの悲しさと不気味さを描いた『美女と液体人間』(58)『電送人間』(60監督は福田純)『マタンゴ』(63)の系譜に属します。
どの映画もドラマ部分と特撮が見事な融合を見せますが、メロドラマとホラーの合体という点ではこの映画が一番でしょう。
水野は、普段は普通の人間と全く変わらないのですが、一種の精神統一をすることで自由に肉体を気体化させることができます。彼が青白いガスとなって刑務所の鉄格子を抜け、あとに背広だけが残るシーン。あるいは人にまとわりついて窒息させる恐怖が特撮を駆使して描かれます。これらのシーンは、子供のときに見たらトラウマになるほど不気味です。
水野を演じた土屋嘉男は、東宝特撮映画を支えた怪優です。『地球防衛軍』(57)のミステリアン、『怪獣大戦争』(65)のX星人など、一筋縄ではいかない役を演じて楽しませてくれました。
前半から後半への転換が見事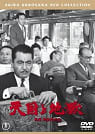
黒澤明監督がエド・マクベインの87分署シリーズの一編『キングの身代金』を大胆にアレンジして映画化しました。映画は、製靴会社重役の権藤(三船敏郎)のもとに突然「あんたの息子を誘拐した」という電話が入るところから始まります。すぐに犯人が連れ去ったのは権藤の運転手の息子だったことが分かるのですが、それでも犯人は3000万円を持って特急こだまに乗るよう権藤に命令します。折しも権藤は会社の実権を握るため、全財産をつぎ込んで自社株の買い占めを目論んでいる最中でした。
前半は、相手を間違って誘拐しても脅迫が成立するのか、権藤は他人のために身代金を出して自ら破滅するのか、というサスペンスをほぼ権藤邸だけで展開させ、まるで密室劇のような緊迫感を感じさせます。そして、こだま号に乗り込む権藤とともにカメラは外に出て、河原での子供の発見シーンで閉塞感から一気に解き放ちます。
一転、後半は徐々に犯人に近づいていく警察の必死の捜査の様子が描かれます。前半から後半への転換が本当に見事です。白黒画面の中に突如現れる煙突から出る赤い煙、ラジオから流れる「オー・ソレ・ミオ(私の太陽)」をバックに現れた、犯人のサングラスに映る月光など記憶に残るシーンが目白押し。伊丹十三の『マルサの女』(87)や『踊る大捜査線2 レインボーブリッジを閉鎖せよ』(03)など、後の映画に与えた影響も計り知れません。
マリリン・モンロー・ノーリターン

マリリン・モンロー、ロバート・ミッチャム主演の『帰らざる河』(54)を、およそ40年ぶりに再見。監督はオーストリア出身のオットー・プレミンジャー。前回見たのは中学生の時だから、この映画で描かれた男女の心の機微などは理解できるはずもない。しかもシネマスコープで撮られたこの映画の魅力は、小さなテレビ画面からは伝わってこなかった。今回は自分も中年になり、ノートリミング版を多少大きな画面で見たので、あらためて結構面白い映画だったことに気づいた次第。
舞台はゴールドラッシュに沸く米北西部の町。離れ離れになっていた息子を引き取ったマット(ミッチャム)は農場の開拓を始める。ある日、マットは河で漂流した酒場の歌手ケイ(マリリン)とその情夫のハリー(ロリー・カルフォーン)を助けるが、ハリーはマットから馬と銃を奪って逃げる。インディアンの襲撃も受けたマットたちは、ハリーの後を追って“帰らざる河”と呼ばれる急流をいかだで下ることになる…。
この映画の第一の見どころはやはりマリリンの存在感。特に、後にリーバイスのCMにも使われた、ジーンズ姿のマリリンがなんともセクシーだ。その一方、子供にギターの弾き語りをするシーンもなかなかいい。マリリンは『バス停留所』(56)でも酒場の歌手を演じていたので、この両作はイメージが重なるところがある。
もう一つの見どころは、カナダでロケされたといういかだくだりのスペクタクル。撮影はジョセフ・ラシェルで、実景とセット撮影とスクリーンプロセスを巧みに編集している。もちろん今の特撮とは雲泥の差があるが、かえってこの手づくり感やアナログ感がいいと感じた。けれどもそう感じるのはノスタルジーに過ぎないのだろうか。
全体の音楽はシリル・モクリッジが担当しているが、マリリンが甘くけだるく歌う主題歌「帰らざる河=リバー・オブ・ノーリターン」は、ケン・ダービー作詞、ライオネル・ニューマン作曲によるもの。
この曲から派生した「マリリン・モンロー・ノーリターン」を歌っていた作家の野坂昭如が先ごろ亡くなった。子供の頃に変な歌だなあと思いながら「~ノータリーン」と替えて歌った覚えがある。同じ頃、地下鉄の駅に貼られていた忘れ物注意の「帰らざる傘」のポスターも懐かしい。




















