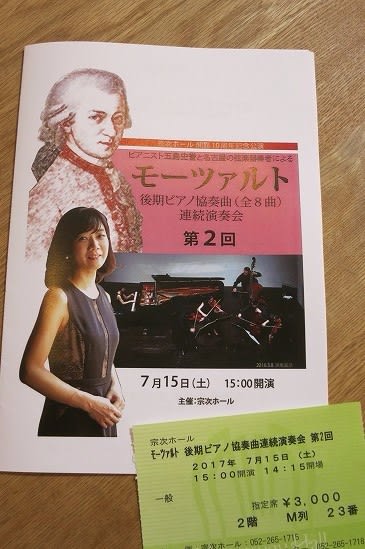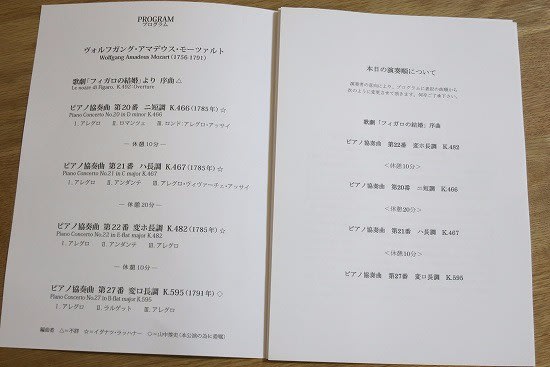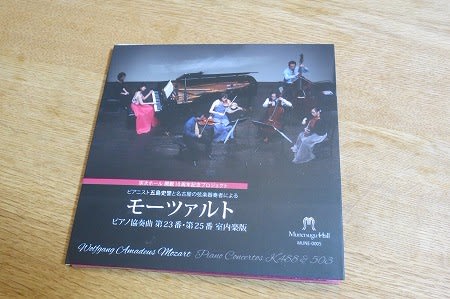グギャー・ギャギャギャ~!
庭先で、突然、とんでもなくけたたましい音がする!
耳をつんざく爆音の主は、そう、蝉君です。
我が家のベランダには、透明の庇があるのだけど、その庇から脱出できなくなり、パニックに陥った迷い蝉の悲鳴です。
ヤレヤレ・・・。
見かねて、脚立を出して、掌に掴んで、逃がしてやる。
初めての時は、すわっ、何事か!と驚いたけど、最近は、ああ、まただね・・・と慣れたもの。
彼らは、本能上、上に飛び立とうとする。
でも、透明の庇が認識できないようで、いくら試みても、庇に激突して、脱出は失敗に次ぐ失敗。
パニックになるんですね。
下向きに飛ぶとか、水平に飛ぶとか、もう少し知恵があれば、災難を免れるはずなのに・・・。
下に飛んでも、地面に激突するだけなので、上に飛ぼうとするのは、当たり前のこと。
止む得ないとは思う。
でも、彼らを見ていて思い至る。人間の行いにも、同じことはあるかも?と。
何か、行き詰った時は、努力の方向性を変えて見る。
常識ではありえないと思える方向に、敢えて進んでみるとか?
我が家の生垣は、蝉軍団のアジトと化しているようで、
至近距離から、どんでもない大合唱が轟きわたる。
窓を開けようものなら、聴覚が破壊されそう…。
しかし、子孫の繁栄のための切なる願いであり儀式であるわけで、尊重せねばなるまい。
まさに、命短し、恋せよ乙女!
少子化に歯止めがかからない日本民族は彼らから学ばないといけないかもしれない。
(今の出生率が続くと、西暦3000年に人口は2000人になって、日本民族は絶滅の危機に瀕してしまうんですね。
1000年前の平安朝を思えば、1000年は、そんなに遠い話ではない気がするのだけど・・・。
成人できたからといって、誰もが結婚できて、子を残せる時代ではなくなってきているので、
子だくさんを桁外れに優遇するとか?暴論百も承知で、昔の婚姻制も取り入れるとか?
もっとも、大量自殺するネズミではないけれど、増えすぎた種は数を減らそうとする、
巧妙なDNAの仕組みがあって、逃れられない定めなのかな?)
蝉に学ぶことも多いかも・・・。

何となく、トネリコの木を見たら、一本に10匹近く、蝉君がうようよ・・・。
いったい全体、何十匹いるんだ・・・!
蝉たちからは、人気があるみたいだ・・・。(笑)
雨が上がったら、また、蝉しぐれがやってきた!
彼らに負けないように、さぁ、練習!
(音漏れを気にせず、練習できる恩恵もあるのだ)
庭先で、突然、とんでもなくけたたましい音がする!
耳をつんざく爆音の主は、そう、蝉君です。
我が家のベランダには、透明の庇があるのだけど、その庇から脱出できなくなり、パニックに陥った迷い蝉の悲鳴です。
ヤレヤレ・・・。
見かねて、脚立を出して、掌に掴んで、逃がしてやる。
初めての時は、すわっ、何事か!と驚いたけど、最近は、ああ、まただね・・・と慣れたもの。
彼らは、本能上、上に飛び立とうとする。
でも、透明の庇が認識できないようで、いくら試みても、庇に激突して、脱出は失敗に次ぐ失敗。
パニックになるんですね。
下向きに飛ぶとか、水平に飛ぶとか、もう少し知恵があれば、災難を免れるはずなのに・・・。
下に飛んでも、地面に激突するだけなので、上に飛ぼうとするのは、当たり前のこと。
止む得ないとは思う。
でも、彼らを見ていて思い至る。人間の行いにも、同じことはあるかも?と。
何か、行き詰った時は、努力の方向性を変えて見る。
常識ではありえないと思える方向に、敢えて進んでみるとか?
我が家の生垣は、蝉軍団のアジトと化しているようで、
至近距離から、どんでもない大合唱が轟きわたる。
窓を開けようものなら、聴覚が破壊されそう…。
しかし、子孫の繁栄のための切なる願いであり儀式であるわけで、尊重せねばなるまい。
まさに、命短し、恋せよ乙女!
少子化に歯止めがかからない日本民族は彼らから学ばないといけないかもしれない。
(今の出生率が続くと、西暦3000年に人口は2000人になって、日本民族は絶滅の危機に瀕してしまうんですね。
1000年前の平安朝を思えば、1000年は、そんなに遠い話ではない気がするのだけど・・・。
成人できたからといって、誰もが結婚できて、子を残せる時代ではなくなってきているので、
子だくさんを桁外れに優遇するとか?暴論百も承知で、昔の婚姻制も取り入れるとか?
もっとも、大量自殺するネズミではないけれど、増えすぎた種は数を減らそうとする、
巧妙なDNAの仕組みがあって、逃れられない定めなのかな?)
蝉に学ぶことも多いかも・・・。

何となく、トネリコの木を見たら、一本に10匹近く、蝉君がうようよ・・・。
いったい全体、何十匹いるんだ・・・!
蝉たちからは、人気があるみたいだ・・・。(笑)
雨が上がったら、また、蝉しぐれがやってきた!
彼らに負けないように、さぁ、練習!
(音漏れを気にせず、練習できる恩恵もあるのだ)