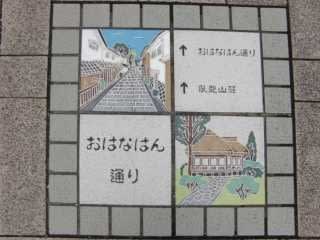旧喜多郡長浜町(ながはまちょう)は愛媛県の南予地域に位置した町です。大洲市、八幡浜市、伊予郡双海町、西宇和郡保内町に隣接。市街地は肱川河口部に集中し、肱川及び伊予灘の海岸線に沿って集落が点在。肱川の舟運によって古くから栄え、かつては上関(山口県)へのフェリー航路も就航していました。明治時代から、木材を筏に組み河口へと運ぶ筏流しが盛んになり、肱川を下ってきた木材や蝋の集散地・積み替え港として繁栄。日本の木材の三大集散地の1つに数えられていました。「町の木:珊瑚樹」「町の花:サルビア」「町の花木:サツキ」を制定。

明治22年(1889)、町村制の施行により、喜多郡長浜町・喜多灘村・櫛生村・出海村・大和村・白滝村が発足。
1955年、長浜町と喜多灘村、櫛生村、出海村、大和村、白滝村が合併、新たに喜多郡長浜町が発足。
2005年、大洲市、喜多郡肱川町、河辺村と合併、大洲市長浜町となりました。
マンホールには、船舶の航行にあわせて跳ね上がった状態の「長浜大橋」がデザインされています。


昭和10年(1935)8月に完成した「長浜橋(赤橋)」は、現役で動く日本最古の跳ね上げ式可動橋(バスキュール式開閉橋)として、2009年2月6日に国の近代化産業遺産として、また2014年12月10日には国の重要文化財に登録されました。


昭和39年12月21日制定の町章は「蛇の目は、旧藩主加藤家の紋所 で、同時にその丸形は歴史と和を 表し、青は伊予灘の碧い海、海運 水産の港町を表し、黄金色は金山 の金、みかんの黄の豊かさを表し ている。 さらに、逆三角形は肱川河口の 三角州(長浜)をかたちどり、町 の将来を末広がりになぞらえ、限 りない発展と期待を意味する。」合併協議会資料より




昭和初期の洋風庁舎建築が残る「長浜町庁舎」・・内子町の本芳我家住宅によく似た造りの「末永家住宅旧主屋」・・一番残念だったのは「登貴姫」ゆかりの観音立像を有する「沖浦観音:瑞龍寺」・・の、門前を素通りしてしまったと後になって気が付いた事・・はぁ~~~~~😥

------------------------00----------------------
旧喜多郡肱川町(ひじかわちょう)は愛媛県の南予地方、肱川の中上流域に位置した町です。大洲市、西予市、喜多郡内子町・河辺村に隣接。「町の木:松」「町の花:ツツジ」を制定。

1889年、町村制施行により、大谷村、宇和川村、河辺村が発足。
1943年、喜多郡大谷村、宇和川村、河辺村が合併し、肱川村が発足。
1959年、肱川村が町制施行し、喜多郡肱川町が発足。
2005年大洲市、喜多郡長浜町、河辺村と合併、大洲市肱川町となりました。
昭和43年制定の町章は「「町の中心を流れる一級河川「肱 川」をそのまま表し、三本の線は (川)は「町民の鐶」「地域の鐶」 「町の鐶」を求めている。 (鐶(かん):輪の意味)」合併協議会資料より

旧肱川町では、ご当地マンホールの類は発見できませんでした。

撮影日:2015年2月25日
------------------------00----------------------
旧喜多郡河辺村(かわべむら)は愛媛県の南予地方に位置した村です。西予市、喜多郡内子町、喜多郡肱川町に隣接。村域は河辺川の上流域にあり、四方を山に囲まれ隣接する町との往来も険しい峠道を越えてになり、地形は急峻。全面積の8割以上が山林の村です。「村の木:モミジ」「村の花:ツツジ」を制定。
明治22年(1889)、町村制の施行により、喜多郡山鳥坂村(やまとさかむら)・奥南村(おくなむら)が発足。
1909年(明治42年)1月1日 - 山鳥坂村、奥南村が合併、喜多郡河辺村が発足。
1943年、上浮穴郡浮穴村大字北平・川上を編入。
1943年、河辺村、大谷村、宇和川村が戦時体制強化のため強制的に合併、肱川村が発足。これにより河辺村は消滅。
1951年、河辺村が肱川村から分離して発足。
2005年、大洲市、長浜町、肱川町と合併、大洲市川辺町となりました。
昭和57年制定の村章は「「かわべ」を図案化。円は村民 の和を、上部の翼は飛躍・発展を 象徴します。」合併協議会資料より

(※)旧河辺村に関しては未訪問のため、マンホールの有無は確認できていません。