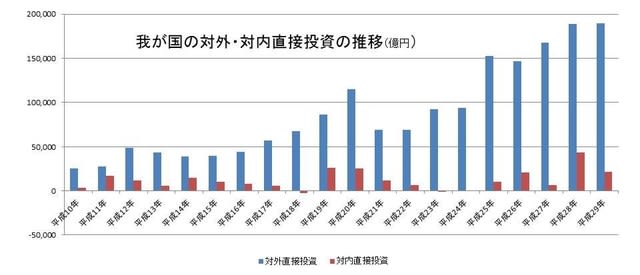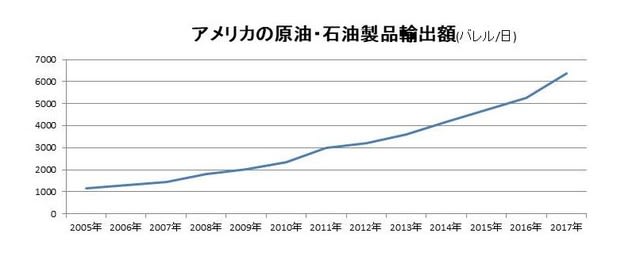トランプさんは少し変わるか・・・
株価の動きにはまるで素人の私ですが、何かこのところの、株価が順調に上がっているようです。
日経平均を見ましたら、8月は小幅な上下を繰り返していましたが9月に入ってから上昇基調を強めているように感じられます。
数字をトレースしてみましたら下のようです。

なぜ急に株価のことについて書く気になったのかと思って、自分自身を振り返ってみまあしたら、こんなことが理由のようです。
本来株価は、経済、景気、企業業績などを反映して動くものなのでしょう。しかし、世間では、良く株価は先見性があるなどといわれます。
ならば株価が上がってくれば、景気がよくなるという事なのですが、その辺りは良く解りません。株価が上がるから景気が良くなるのか、景気が良くなるから株が上がるのか、多分相互作用の繰り返しなのでしょう。
ところで、このところ、世界の経済見通しはよくありません。どこの国も経済成長率の予想を下方修正したりしているようです。
ところがその原因というのは、どうも、経済現象にあるのではなく、典型的には米中貿易摩擦などの国際的な政治力学によるところが大のようです。
ならば経済予測は簡単で、主要国のレーダーたちが、意地を張り続ければ、経済は低迷し、国際政治関係が安定すれば、経済もよくなり、恐らく株価も上がってくる、ということになるのでしょう。
単純に言えば、トランプさんの頭の中を透かして見れば、株価の動きも解るということになるのではないでしょうか。
この度、ボルトンさんが解任になったようです。タカ派だからこそ、トランプさんが大統領補佐官という要職に任命したはずでしょうが、何かタカは危険だとトランプさんに思われたような解説が多く見られます。
ということは、トランプさんはボルトンさんを任命した時よりも柔軟になったという事でしょうか。北朝鮮には大変柔軟ですが、これから、中国に対しても、アメリカ自身の痛みが大きすぎて少し柔軟にならないと来年の選挙に響くと考えたのでしょうか。
その辺りはトランプ陣営の中では、それなりに解っていて、さらに、国際投機資本筋は、地獄耳や第六感を持っていて、「これから株は買いだ」と先見性を発揮しているのだとすれば、世界中にとって大変結構なことだと思うのですが・・・。
現実には、事はそんなに単純でなくて、これからも世界中が頭を痛めるようなことが続くのかもしれませんが、さてさて、どう読めばいいのでしょうか。
株価の動きにはまるで素人の私ですが、何かこのところの、株価が順調に上がっているようです。
日経平均を見ましたら、8月は小幅な上下を繰り返していましたが9月に入ってから上昇基調を強めているように感じられます。
数字をトレースしてみましたら下のようです。

なぜ急に株価のことについて書く気になったのかと思って、自分自身を振り返ってみまあしたら、こんなことが理由のようです。
本来株価は、経済、景気、企業業績などを反映して動くものなのでしょう。しかし、世間では、良く株価は先見性があるなどといわれます。
ならば株価が上がってくれば、景気がよくなるという事なのですが、その辺りは良く解りません。株価が上がるから景気が良くなるのか、景気が良くなるから株が上がるのか、多分相互作用の繰り返しなのでしょう。
ところで、このところ、世界の経済見通しはよくありません。どこの国も経済成長率の予想を下方修正したりしているようです。
ところがその原因というのは、どうも、経済現象にあるのではなく、典型的には米中貿易摩擦などの国際的な政治力学によるところが大のようです。
ならば経済予測は簡単で、主要国のレーダーたちが、意地を張り続ければ、経済は低迷し、国際政治関係が安定すれば、経済もよくなり、恐らく株価も上がってくる、ということになるのでしょう。
単純に言えば、トランプさんの頭の中を透かして見れば、株価の動きも解るということになるのではないでしょうか。
この度、ボルトンさんが解任になったようです。タカ派だからこそ、トランプさんが大統領補佐官という要職に任命したはずでしょうが、何かタカは危険だとトランプさんに思われたような解説が多く見られます。
ということは、トランプさんはボルトンさんを任命した時よりも柔軟になったという事でしょうか。北朝鮮には大変柔軟ですが、これから、中国に対しても、アメリカ自身の痛みが大きすぎて少し柔軟にならないと来年の選挙に響くと考えたのでしょうか。
その辺りはトランプ陣営の中では、それなりに解っていて、さらに、国際投機資本筋は、地獄耳や第六感を持っていて、「これから株は買いだ」と先見性を発揮しているのだとすれば、世界中にとって大変結構なことだと思うのですが・・・。
現実には、事はそんなに単純でなくて、これからも世界中が頭を痛めるようなことが続くのかもしれませんが、さてさて、どう読めばいいのでしょうか。