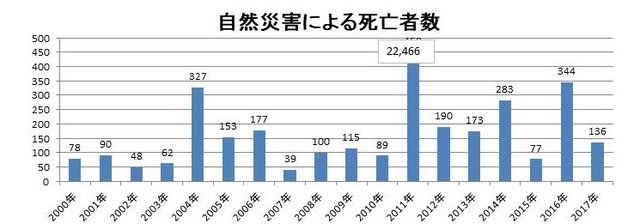ベンガル湾周辺7カ国の協力組織の活動
BIMSTEC(Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation: ベンガル湾多分野技術・経済協力イニシアチブ)という組織があります。
インド、タイ、スリランカの3カ国から始まり、その後、バングラデシュ、ミャンマー、さらにネパール、ブータンが参加して、7カ国となっています。
マスコミでは往々にして一帯一路などで勢力を拡大する中国に対抗するためといった解説がされますが、それはそれとして、7カ国は、それぞれに多様な問題を抱えながらも21世紀という「アジアの世紀」を創る重要な国々です。
その7カ国の会合が、8月30にと31日の2日間、ネパールの首都カトマンズで開かれています。
NHKの報道によれば、インドのモディ首相は、冒頭、南アジアと東南アジアの連携を深める方向を示すスピーチをされたそうですが、こうした動きが活発になり、アジアの国々が、多角的な協力体制を築きながら、共に発展する姿が見られるようになれば素晴らしいと思います。
地政学的な見方をする人たちは、アジアの巨大な2つの国、中国とインドの対抗の図式でこうした動きを説明することが多いのかもしれませんが、それはそれ、1つの見方として、いずれ世界の超大国となる(既にそうですが)中國とインドが共にアジアの発展をリードすることは、巨大で多様な可能性を生むでしょう。
すでにインドはIT技術大国としての地位を確立していますが、13億の人口を持つ民主主義国が如何なる発展を遂げるかには、世界中の多くの人々が深甚の興味を持って見守っているでしょう。
片や中国は共産党一党独裁体制を継続、習近平氏の終身国家主席の体制を整え、ユーラシア大陸からアフリカまで一帯一路の経済発展を目指しているようです。
21世紀は「アジアの世紀」と書きましたが、すでに、現実はアジアの世紀を越えて、世界の世紀、地球社会全体の姿を模索する世紀になりつつあるように感じられます。
トランプさんはその中で「2国間」に固執した動きをあらわにしていますが、地球市民にしてみれば、すでに時代遅れのようです。
願わくば、各地域、各国々が、固有の文化にはそれぞれの独自性があっても、それぞれの特徴を生かし、「争いの文化」ではなく 「競いの文化」の中で、競争的連帯(Competitive Alliance)を目指して進んでほしいと思うところです。
日本はその中でいかなる役割を果たすのか、日本のリーダーには、いよいよ本気でその問題を考えてほしいと思います。
BIMSTEC(Bay of Bengal Initiative for MultiSectoral Technical and Economic Cooperation: ベンガル湾多分野技術・経済協力イニシアチブ)という組織があります。
インド、タイ、スリランカの3カ国から始まり、その後、バングラデシュ、ミャンマー、さらにネパール、ブータンが参加して、7カ国となっています。
マスコミでは往々にして一帯一路などで勢力を拡大する中国に対抗するためといった解説がされますが、それはそれとして、7カ国は、それぞれに多様な問題を抱えながらも21世紀という「アジアの世紀」を創る重要な国々です。
その7カ国の会合が、8月30にと31日の2日間、ネパールの首都カトマンズで開かれています。
NHKの報道によれば、インドのモディ首相は、冒頭、南アジアと東南アジアの連携を深める方向を示すスピーチをされたそうですが、こうした動きが活発になり、アジアの国々が、多角的な協力体制を築きながら、共に発展する姿が見られるようになれば素晴らしいと思います。
地政学的な見方をする人たちは、アジアの巨大な2つの国、中国とインドの対抗の図式でこうした動きを説明することが多いのかもしれませんが、それはそれ、1つの見方として、いずれ世界の超大国となる(既にそうですが)中國とインドが共にアジアの発展をリードすることは、巨大で多様な可能性を生むでしょう。
すでにインドはIT技術大国としての地位を確立していますが、13億の人口を持つ民主主義国が如何なる発展を遂げるかには、世界中の多くの人々が深甚の興味を持って見守っているでしょう。
片や中国は共産党一党独裁体制を継続、習近平氏の終身国家主席の体制を整え、ユーラシア大陸からアフリカまで一帯一路の経済発展を目指しているようです。
21世紀は「アジアの世紀」と書きましたが、すでに、現実はアジアの世紀を越えて、世界の世紀、地球社会全体の姿を模索する世紀になりつつあるように感じられます。
トランプさんはその中で「2国間」に固執した動きをあらわにしていますが、地球市民にしてみれば、すでに時代遅れのようです。
願わくば、各地域、各国々が、固有の文化にはそれぞれの独自性があっても、それぞれの特徴を生かし、「争いの文化」ではなく 「競いの文化」の中で、競争的連帯(Competitive Alliance)を目指して進んでほしいと思うところです。
日本はその中でいかなる役割を果たすのか、日本のリーダーには、いよいよ本気でその問題を考えてほしいと思います。