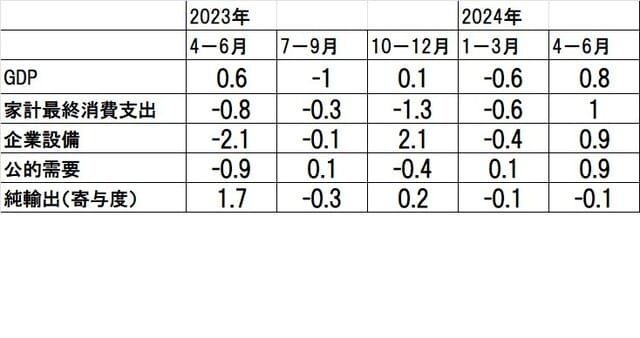8月には、何か戦争に関することばかり書いてきたような気がしますが、今日で8月も終わり。戦争に関わる事から、本来の経済に関わる事への転換をしたいと思います。
人類は戦争を嫌いながら戦争をしてきました。今もしています。戦争の始まった理由は多分、今より豊かな生活をしたいと望んだからでしょう。
そのためには望ましい土地を手に入れなければなりません。それが多くの戦争の始まりだったのでしょう。
長い人類の歴史の中で、そういう時代が随分長かったので、「土地が欲しい」という本能的な欲求が海馬の奥に染みついているのでしょうか、今のロシアもイスラエルも、自分の土地を広げたいということが大きな目的で戦争をしているようです。
ところが時代は変わりました。
今、世界で国民一人当たりのGDPが最も大きい国はルクセンブルグです。金額は13万ドル約1900万円、アジアで最も高い国はシンガポールで約8.5万ドル(約1200万円)(日本は約500万円)です。
ご承知のようにどちらも大変小さい国で、国土面積は、ルクセンブルグが日本の146分の1、シンガポールの国土面積は720㎢(東京都区部は628㎢))です。
今の世界では、豊かさは国の広さとは関係ないことが解ります。
日本もかつては戦争をして支配地域を広げれば豊かになれると考えて太平洋戦争をしたのでしょうが、その結果は、蓄積してきた資産は殆んど灰になり、国土面積は小さくなりました。窮乏のどん底から出発しなおして、馬鹿な戦争をしたと思いながら頑張って、世界第二の経済大国になりました。
何故それが出来たのか、そこには2つほど大きな条件がありました。一つは、その間ずっと平和であったこと、これは最も基本です。
もう1つは、広い意味での経済的な条件の変化です。2つあります。
- 豊かさは技術革新で実現出来る時代に入ったこと、
- 国際化、特に貿易の自由化が進んだこと、
勿論平和でないと、こういった条件も進まないわけです。今は、どんな小国でも条件さえ満たせば、いくらでも豊かな国になれることが、「既に現実になっている」という時代に入っていると言ってよいのではないでしょうか。
現生人類(ホモサピエンス)はその発生以来、生きていることの安全確保から始まって、飢えないための採集活動から農業、漁業に進歩し産業革命を経て、技術革新の時代に入って今に至っているのです。
そして第二次大戦以降は、国際的な経済活動の自由化を進め、技術革新で成果を上げれば、そこで稼ぎ出すGDPで、食料でも資源でも買える時代になったのです。
資源のある国は、高度技術を持つ国に資源を輸出することでより豊かになり、それぞれの国が、最適な方法でGDPを創出し、それを自由な市場を活用して取引し、互いに裨益するというシステムに向かって世界経済は発展してきています。
人間の知恵によって進歩してきた世界の経済システムが、人間の望む豊かで快適な社会への進歩に向かう条件の整備に成功して来たということでしょう。
この人類共通の努力を、周回遅れの知識と欲望の保有者が混乱に陥れるのが戦争です。戦争をしないことが豊かで快適な社会への王道なのです。
戦争をしないことが、平和であることが、人類社会をより豊かで快適なものにする近道だと、戦争をする人に教えてあげるのが一番大事なことのようです。