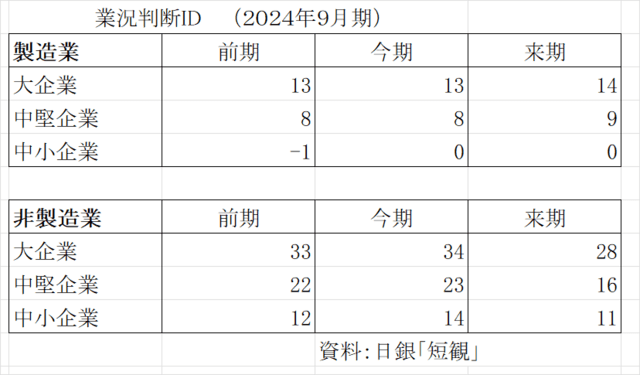日本人は昔から若いときは苦労しても真面目に働いて将来ゆとりのある生活をしようという考え方強かったようです。
「若い時の苦労は買ってでもしろ」等という諺もありますが、そういう意味では、「先憂後楽」という生き方が、誰もの身に付くような社会を作ってきたのでしょう。
そのせいか日本人は貯蓄好きです。今も、日銀の資料を見れば日本の個人貯蓄が2200兆円もあって、その半分以上は銀行預金などの安定資産です。
勤勉に働くという事と、投機的なものには手を出さず、確実な貯蓄で将来の備えるといった考え方は、日本の雇用制度や、賃金制度にも組み込まれていたようです。
丁稚奉公から出発して、番頭を目指し、将来は暖簾分けや自立で店を持つといった考え方は、近代企業になっても、同じ企業に勤めていれば、年々上がる年功賃金システムや退職金という制度で残っていました。
今では、政府は欧米流の仕事別賃金で、同じ仕事をしていればずっと同じ賃金で、高い賃金が欲しければ、高い賃金の仕事を自分で身につけるという考えのようです。
しかし今でも、非正規従業員は別として、同じ会社に勤めて、企業の中で仕事をしながら、資格・能力を高め、次第に昇進し、賃金も上がる職能資格制度が一般的です。
これは、働く人には安心感を与え、経済的安定にもつながります。そんな現状を「貯蓄」という立場から見ると下のグラフです(総務省「家計調査」:2人以上世帯)。

これは世帯主の年齢階層別の「平均貯蓄額」です。40歳未満では1千万円迄行きません。2023年は減少です。40歳代は1千万円をやっと越えています。50歳代では大分増え2000万円を越えますが.退職金の効果もあるでしょう。2023年は多少減。60歳代が退職金も加えて現状ではピークで70歳以上になると。少し減りますが、4年間多少伸びています
各世代とも低成長経済、コロナ禍の中で、その影響を受けながら何とか頑張っています。
ところで、この数字に、加えてみておかなければならないのは「負債」を差し引いた「純貯蓄額」です。(資料:仝上)

純貯蓄額は、40歳までのマイナスから出発。年代ごとに60歳代まで急速に増えて2000万円を越えています。負債の原因は殆んどが住宅ローンで約6割の世帯が背負っています、数字は背負っていない世帯も入れた平均ですから、住宅ローン負担の深刻さは解ります。
幸いなことに、この世代は働き盛りで、夫婦ともに働いているケースが多いこともあるのでしょうか、40歳代では純貯蓄のマイナスは大幅に減少します。
しかし50歳代に入っても純貯蓄は1000万円までほどが限界であまり増えません。子育て、学資の負担が大きいのでしょうか。
負債が減って純貯蓄額が貯蓄額に追いつくのは60歳代になってという事のようです。
もちろんこれは,同じ世帯がこうした経路をたどるというのではなく、現在のその年代の世帯の数字ですから、この世代別の数字の在り方は、これからの日本経済如何で変わるでしょう。
しかし、今までの日本経済の中で世代別の結果を見ても、殆んど成長のない30年ですが、日本の2人以上世帯は、その状況の中で、結果的には、着実に「我が家の将来はきっと良くなる」というに日本人らしい生き方を確り実践して来ているのではないか(特に高齢世代)という印象を受けるところです。
今後は国の方も頑張ってほしいものです。